過去のレポート大丸有 エコまちづくり解体新書
都市の魅力と環境の両立へ――「未来の交通」を探そう(高橋洋二氏)
街の安全と快適さを保ちながら環境に配慮した交通をどのように作り上げるべきか。現代の街の姿を考える際に必ず直面する問題に、大手町・丸の内・有楽町(大丸有)地区も取り組んでいる。[[電気自動車]]や自転車、水素燃料バスなどを利用するユニークな実証実験を2009年に行った。交通政策の研究者として知られる高橋洋二日本大学教授は、その実験で立案から実施、分析まで中心的な役割を果たしてきた。新しい取り組みで見えてきたものは何か。1月16日から始まる第2次社会実験を控えて、今回の社会実験の意味と、交通からみた大丸有の未来のあるべき姿を語ってもらった。
1.交通からみた大丸有地区の強みと弱み
新しい取り組みを行いやすい街

街にはそれぞれ特徴があり、また抱える課題も異なる。交通政策の研究者からみた大丸有地区の特徴は何だろうか。
大丸有地区の特徴は日本経済の中心であるということです。ここまで超一流企業が集まっている街は、他に例がありません。いわば「日本の顔」と言える重要な地域です。そして交通の利用者が会社で働くオフィスワーカーが中心であることも特徴の一つです。また地域の公共交通の存在感が、とても大きいという特徴もあります*1。日本の玄関口でもある東京駅にはJRの主要幹線、大手町駅には地下鉄が集まっています。他の国に比べて日本は鉄道の輸送に占める割合が大きいのですが、その中でも大丸有地区の大きさは際立っていますね。
さらにこの地区は、街づくりで関係者のコミュニケーションが良いという特徴があります。「大丸有協議会」*2 が、街のビルオーナーや地権者の企業・団体等によって作られています。そこが、民間主体で自発的に街の課題に取り組み、街の価値を高めようと努力しています。これまで街づくりに努力を重ねてきた歴史があるからこそ、意義のある新しい取り組みを行いやすい街となっています。他地域では関係者の合意を得ることは、様々な課題にぶつかるでしょう。この長所を活かして、未来の街の交通の姿を考えなければなりません。

「適切に機能している」と、高橋教授は大丸有地区の交通事情を評価する。しかし同時に問題もはらんでいるという。
大丸有地区で働く人は約23万人いますが、それほどの人が集まるのにこの地区では交通の混乱は起きていません。世界のどの都市でも、渋滞などで都市機能が麻痺して、経済的な損失が生まれています。それに比べれば大丸有地区の姿は素晴らしいことであると評価できます。
しかし、この地区でも問題はあります。例えば、公共交通機関での朝の混雑は世界でも有数です。人とビジネスが集まっているために物流量も非常に多くなっているのです。将来的にはこれらが悪化する可能性もあるでしょう。
大丸有地区はこの10年で大きく変わりました。再開発が進み、ビルが高層化して容積が大きくなるとともに、ショピングゾーンを併設する複合型の大型ビルが誕生しています。丸の内仲通り*3 は高級ブティックが並び、日本有数のショピング街になりました。大型店舗や大型ホテル、また劇場やホールなどの集客施設が次々に開館しています。これらは街として素晴らしいことですが、こうした人の流れの変化は大丸有地区の交通にも影響を与え始めています。大丸有地区は地下駐車場が分散している場合が多いので、車で来た買い物客や観光客は、移動の場合に一度ビルの外に出て、入り直すなどの必要がある場合があります。地下通路が発達したのにあわせて、地下駐車場もネットワーク化するなどの対応が求められるでしょう。
*1 大丸有地区の交通事情。JR東京駅には東海道新幹線をはじめとする新幹線6路線、在来線7路線が乗り入れ、JR東日本管内では第5位となる1日の乗車人員が平均39万4,135人(2008年度・JR東日本発表)。さらに、地下鉄では5路線が乗り入れる大手町駅など4駅が存在し、エリア内では、20路線13駅、1日の平均乗車人員は99万7,000人にのぼり、大丸有地区は、東京の交通の中心になっている。道路では皇居の外縁を南北に走る幹線道路の「内堀通り」に隣接している。また東京駅周辺はバスターミナルもあり、ビジネス向けのタクシーやハイヤーの利用も多い。
2.未来を見据えた交通実験その目的と内容

大丸有地区では、09年秋から環境交通の実験が行われた*4。「電気自動車タクシー」「カーシェアリング」「地区内水素燃料シャトルバス」「コミュニティサイクル」など、先進的な交通の取り組みを行い、体験者の意見を集めている。高橋教授は、この実験の立案から、実施と分析まで深くかかわった。この狙いはどのようなものか。
「車をコントロールする」ことが、現代の街づくりと交通対策の主な課題です。自動車はとても便利な乗り物ですが、増えすぎると渋滞など都市機能を麻痺させ、排気ガスや発する熱で環境の悪化や[[ヒートアイランド現象]]を引き起こします。今回の実験では、まず移動手段を「共同化」して、この街を一人ひとりが車を使わずに移動できるようにしました。車の数を減らすことにつながるためです。バス、共同タクシー、自転車など、車以外の手段を使いやすい形で街の交通に取り入れて、人々が車以外の手段で移動できるようにしました。
今はあらゆる面での交通対策で、環境問題への配慮が重要な要素として考えられています。ここ数年の社会全体の地球環境問題への高まりの中で、自動車に起因する割合をいかに減らすか、が重視されるようになっています。環境負荷を減らすための街の取り組みが社会から高く評価されるようになりました。今回の実験では環境負荷の低い[[電気自動車]]、水素自動車をはじめ、世界で関心が高まっている自転車も取り入れて社会実験を行いました。
都市間競争の時代に、街のブランド力の高まりは、経済的な価値につながる。この実験ではビジネスとの結びつきも配慮したという。
「車を使わない」「環境に配慮する」という二つの目的を進めるとともに、街の機能も損ねてはいけません。実験では、街の快適さと利便性を追求して、街の魅力を高める配慮もしました。これが実験の第3番目の目的です。

しかし、実験によってすぐに街の交通を大きく変えることはできません。将来、この実験を発展させた新しい交通形態を実現していくための情報を収集したいと考えています。そして今回のような、補助金や一部の有志による支援だけでは、事業として継続させていくのに限界があります。
実験を通じて、さまざまな交通政策の導入手法と客観的な評価を行うことは、大丸有地区はもちろん、今後の日本の交通政策を策定していく上で重要なことです。実際に実施してみないと、問題点が浮かび上がってきませんから、貴重な経験となります。大丸有地区は東京の「顔」、日本の「顔」ですから、大丸有地区で得られた知見や成果は、社会全体に広く認知されることになります。全国に対して、新しい交通システム・交通形態が大丸有で生まれつつあることを、社会により広く知らせることになります。今回、国土交通省と千代田区から支援をいただきましたが、行政も大丸有地区の存在感と影響力の大きさに期待していると思います。
*4 大丸有地区・周辺地区環境交通第1次社会実験
2009年9月から10月にかけて大丸有地区とその周辺地域で行われた実験。09年1月に国から環境モデル都市に選定された千代田区、国土交通省、東京都、そして同地区の企業などからなる大丸有協議会等が協力して、「大丸有地区・周辺地区環境交通推進協議会」が実施した。
電気自動車(EV)タクシー利用実験、EVカーシェアリング利用実験、EV急速充電器利用実験、地区内水素燃料シャトルバスの運行実験、地区内外連携のコミュニティサイクルの利用実験という5つがテーマになった。では、EVをタクシーに用いて地区内近距離移動に利用した。では、ビル内就業者の営業用として地下にEV一台を常駐させ、予約制で希望者が利用した。では応募者が東京横浜間のEV走行と充電体験を行った。さらにでは既存のバス路線が走っていない東京駅八重洲口大手町丸の内間に、次世代のエネルギーとして注目される水素燃料駆動のコミュニティーバスを15分に1本の間隔で運行した。またにおいてはマルチポート型(乗り捨て型)のレンタサイクルシステムを導入し、応募した一般の方々が体験利用をした。このポートは六本木、恵比寿にも設置した。
大丸有地区コミュニティサイクル社会実験
2009年秋には、大丸有で環境省の補助を受けたコミュニティサイクル社会実験も行われた(期間:10月1日〜11月30日、実施機関:JTB首都圏)。大丸有エリア内の丸の内仲通りを中心とした地域に自転車ポートが5箇所(新丸ビル前等)設けられ、事前登録して専用のICカードを使って借り、30分無料(超えた場合は10分100円)で利用できるというもの。どのポートでも返却できる。決済はICカードで行う。10月1日のキックオフイベントは、丸の内オアゾにて田島一成環境副大臣、石川雅己千代田区長、メルビン駐日デンマーク大使等が参列して行われ、小学生がコミュニティサイクルを体験した。
3.未来交通のユニークな実験 ー電気自動車の共同使用の使い勝手は?

[[電気自動車]]は次世代の自動車として社会的に関心が高い。そして市販が始まるなど、身近な存在になりつつある。実験では、タクシーやカーシェアリングと電気自動車の融合を試みた。
現時点(2010年1月時点)で実験結果は集計中ですが、実際に自動車を動かし、利用したことで、有意義な情報が集まりました。電気自動車は将来有望な交通手段です。試乗をすれば分かりますが、振動も排気ガスもなくて、快適な乗り物です。普及には値段が下がる必要がありますが、量産に移ればこの問題も改善していくと期待されています*5。なお、充電をする場所が少ないというインフラ上の問題があります。そのために今回は大丸有地区と横浜みなとみらい地区(ランドマークタワー)、首都高速のサービスエリアに充電器を設置しました。
EVの利用者からは、乗り心地の快適さについて高い評価を得ています。従来の自動車に比べて静か過ぎるため、歩行者向けに何らかの接近サインが必要だ、という意見が出るほどです。クリアすべきハードルがいくつかありますが、他の交通手段に比べて、電気自動車は「環境にやさしい」と注目を集め、評判が高まる一方です。なお、大丸有地区を中心に電気自動車によるタクシー事業を企画し、新年1月から運行を始めることとなっています。EVの活用方法の将来の広がりに注目したいと考えています。
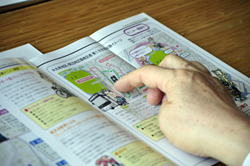
実験では、丸の内シャトルと連携する形で、これまでバス路線がなかった東京駅を一周するコミュニティーバス*6 を運行した。その動力として注目したのが、次世代エネルギーとして期待される水素燃料。水素燃料自動車はまだ一般向けに販売されていないが、無尽蔵に製造が可能なエネルギーである水素を燃料にするために、自動車などの新しいエネルギー源となることに期待されている。
バス路線のない場所にコミュニティーバスを導入することで、交通や人の動きがどのように変わるかを実験しました。これまで、銀座・八重洲地区と丸の内地区は、鉄道で分断されており、これらの地区を循環するバス路線がなかったのですが、その"ミッシング・リンク"を埋めたのです。新たなバス路線を導入して、人々が車を使わないですむように誘導することを狙いました。
水素燃料バスは、東京都市大学のサポートを受けました。このバスは静かで、乗り心地がよいと評価が高かったですね。ただし、このバスが走っていることをご存じの人が少なかったためか、利用者が予想より少なかったのは残念です。新しいことを行う場合に、いかにPRが重要か、ということを改めて感じました。一方、運用に問題はありませんでした。水素燃料自動車、またバスについても、交通を変えるポテンシャルを持っているという点に期待しています。


*5 大丸有地区・周辺地区環境交通第1次社会実験
2009年9月から10月にかけて大丸有地区とその周辺地域で行われた実験。09年1月に国から環境モデル都市に選定された千代田区、国土交通省、東京都、そして同地区の企業などからなる大丸日本では、いくつかの自動車会社が一般向けの電気自動車の販売を始めた。その価格は約460万円で、車体の大きさが同等のガソリンエンジンの軽自動車の価格100万円と比べるとまだ高額だ。各メーカーは「近年中に200万円台まで下げたい」という意向を表明している。
(写真上:三菱自動車の電気自動車「i-MiEV」)
*6 コミュニティーバスとは従来の商業バス路線が通っていないところに、自治体などが支援して運行するバス。交通手段の少ない地点や観光拠点を回るものなど目的はさまざまだが、商業バス路線の撤退が広がるなかで、全国で導入されるようになった。
(写真下:大丸有地区・周辺地区環境交通第1次社会実験で使用された、水素を燃料に利用したコミュニティーバス)
4.人気の自転車を実験に導入 ー広がる未来の可能性

世界的に自転車の利用が注目されている。一人ひとりの移動ニーズに対応でき、環境負荷がほとんどなく、また健康にもよいためだ。そしてコスト面でも安い。大丸有の環境実験でも自転車の利用を工夫した。
実験では大丸有地区のホテル、三菱ビル(スカイバスのチケットカウンター)の4か所、さらに八重洲や六本木、恵比寿の外資系ホテルに、自転車を乗り降りできる、「マルチポート」と呼んでいる場所を作りました。自転車を、利用を開始した場所に戻す方式にすると、利用者にとって使い勝手が悪くなるため、その改善策として、ポートがあるどこでも乗降可能な方式としました。またどの乗り場に何台あるのかという台数把握や予約をコンピュータで管理できるようにしました。貸し出す自転車は、坂道などでも使えるように電動モーター付きです。
外国人も含めて観光客の利用者が多かったですね。そして私の予測よりも広い範囲を、自転車を使って移動することが分かりました。利用者は皇居の外縁を回り、千代田区内にとどまらずさまざまな名所を自転車で回っていました。恵比寿や六本木は東京駅の丸の内口から5キロほど離れていますが、それでも多くの人が使いました。また予想外にビジネス目的の利用も多くあったのです。無料で目的地の近くまで行けるためでしょう。自動車の代わりになる移動手段として、都市の自転車利用には大きな可能性があると思います。


大丸有地区では国から「[[環境モデル都市]]」に選ばれた千代田区と共同して、2010年に第2次の環境交通実験を行う。そこでは自転車の利用を千代田区全域に広げる予定だ。
引き続き調査をして車から自転車へのシフトをうながしたいと思います。第2次実験では利用者の行動を把握するために、GPSを自転車に取りつけることを考えています。可能なら、そのGPSで観光や道路情報を得られるようにしたいですね。自転車利用の先進国であるオランダやドイツでは自転車の通勤やレジャーへの利用が、「かっこいい」「健康によい」と受け止められています。
しかし自転車の普及には課題もあります。自転車の数が増えれば、既存の交通を妨げることになりかねませんし、違法駐輪も増えるかもしれません。自転車の絡む交通事故が増えてしまう可能性があります。そのために将来的には、自転車専用道や、自転車駐輪場の計画的な設置も考えなければなりません。大丸有地区、そして日本全国の都市で、今後の自転車利用が広がり、車を抑制する有効な手段になる可能性があります。
5.新しい交通は「三方一両得」を生む ー街の価値を高める活動に参加を

大丸有の新しい実験は、世界の交通の流れと重なっている。脱クルマ、そして自転車や歩行などの人の力の利用、公共交通へのシフトによる移動の共同化だ。
ヨーロッパでは「車を使わせない」政策が広がりつつあります。ロードプライシング(道路課金制度)を取り入れたりするところもあります。ロンドンなどでは中心部に車が乗り入れる場合に課金をしています。また自動車の乗り入れを禁止し自転車や徒歩のみで移動するようにデザインした街もあります。
自動車以外の交通手段を優遇する「アメ」の政策に加えて、自動車の利用を禁止または規制する「ムチ」の政策を、ヨーロッパでは取り入れています。日本では、「ムチ」の政策がなかなか導入できませんが、二酸化炭素の削減という大きな目標を達成するために、自動車を強制的に使わせないという政策も一つの選択肢として、考えるべきときかもしれません。
実験によって、大丸有の未来の交通の可能性がみえてきた。この街の今後の方向性はどのような形であるべきか。
新しい政策を導入することには手間がかかります。メリットを受ける人、デメリットを負う人の双方が出てきて、調整が難しいからです。しかし交通は公共のものですから、人々が合意するまで話し合いを続けていかなければなりません。こうした話し合いは公開の場で行うべきでしょう。他人の意見を聞き、意見を交換することで、地域全体の問題を知り、「自分だけが」という考えが変わります。そして問題点も話し合いの中で分かり、関係者に共有される可能性も高まるのです。

私はそうした場で意見を求められる機会が多いのですが、「自分・他人・公共の三者が『三方一両損』となるのではなく、『三方一両得』になるように変えていきましょう」と呼びかけています。一時的に誰かが損をする場面があるかもしれませんが、交通を変えて便利にすることで街の魅力や価値が上昇すれば、最終的には誰もが利益を得ることができる可能性があるのです。そこで実際に社会実験を行い、関係者全員に長所、短所を見てもらい、体験してもらえば、見落としがちな問題点も浮かび上がり、改善のアイデアも出てくるのです。
大丸有地区は、公共交通が適切に機能している街です。これは明治時代から街づくりにかかわってきた人々の努力の蓄積と、現在ここで働く人たちの協力があるためです。ですが工夫の余地はまだあります。今回の実験で取り入れた交通手段は評判がよく、将来の普及が期待できるものでした。こうした取り組みを重ねることによって、大丸有地区には日本の環境交通のモデル都市になってほしいと考えています。
都市間競争が、日本国内でも世界の中でも起こっています。大丸有地区がそうした競争に勝ち残り、一段と魅力を持つためには、便利で快適で、環境に配慮した交通は有効な道具になります。新しい交通体系を生み出すにはこの街にかかわる人すべての協力が必要です。新しい流れを生み出す取り組みや話し合い、そして社会実験に、ぜひ参加していただきたいと思います。

「コミタク、発車オーライ! ー新たな環境交通(コミュニティタクシー)の運行スタート」
第1次社会実験として2009年9月29日から10月12日に行われた実験メニューの1つであった、環境に優しい[[電気自動車]]によるコミュニティタクシー。車両デザインや愛称等について地元で働く女性グループの意見を取り入れるなど、地域に根ざした「マイ(私達の)タクシー」として、事業化されることになりました。日の丸リムジンが2010年1月から、大手町・丸の内・有楽町エリアでのサービスを開始致します。
(画像:日の丸リムジンによるコミタクの車体イメージ)

