

トルコやブータンなど世界の難民に目を向けて来た中、今回は日本にスポットを当てた著書「日本と出会った難民たちー生き抜くチカラ、支えるチカラ」の出版イベント。
講演は、著者の根本かおるさん、難民の職業支援をおこなっているユニクロを率いる、株式会社ファーストリテイリング CSR部 ソーシャルイノベーションチームリーダー シェルバ英子さん、認定NPO法人・難民支援協会の田中志穂さん、難民を受け入れ高等教育プログラムの支援を受けて、この春青山学院大学を卒業したカディザ・へゴムさん(ミャンマー出身)。 司会は根本さんの元同僚でありテレビ朝日アナウンサー 松井 康真さんが駆けつけて下さいました。
著者 根本かおるさんのご挨拶

これだけの人が難民の事を考えてくれる事がとてもありがたいです。
よく、「なぜ難民のことを?」といろんな方々に質問されるのですが 、こう応えています。
" 私に生きるチカラをくれたのが、難民の方々だったから。 "
現在の日本での難民認定者の割合は、0.3パーセント。アメリカの53パーセントに対しとても低いのが現実です。ミャンマーに次いで多い申請国はトルコ。トルコに2年間滞在した事もありますので、この現状を見て、とても心苦しく思います。
トークディスカッション
 (左)ご自身の経験を力強く伝える カディザ・へゴムさん (右)トークディスカッション
(左)ご自身の経験を力強く伝える カディザ・へゴムさん (右)トークディスカッション
― ユニクロが難民支援として、職業援助のインターン制度を受けたへゴムさん、実際、どのような経験をされたのですか?
へゴム:少数民族出身であったために、差別や迫害などがほかの難民に比べてもとても多く、家族でバングラディッシュに逃げなんとか命が助かりました。その後、結婚をしても居場所はありませんでした。小さい頃は、「なんで自分が難民なのか?」「なぜ居場所がないのか?」と悩み続ける日々でした。
しかし、父は偉大でした。いつも、まわりの人のために生きる人でした。母国は昔、とても裕福だったという話を父から聞いたとき、将来は、父のように難民の為に生きようと思いました。しかし、十分な教育がなく、何もできないことに絶望しました。そんな時、UNHCRの支援により勉強ができる環境があると知り一生懸命勉強をして、日本の大学に入学しました。
その生活の中で、ユニクロと出会い、お金を稼ぐことで生活をする喜びを知る事ができました。
―「難民支援協会」の田中さん、難民支援の活動をする中で、どんな困難がありますか?
 左から ジェノバ英子さん、田中志穂さん 田中 :まず難民がに日本で「難民」として認められるためには、難民であることを証明しなくてはならないという手続きの壁があります。命からがら逃れてきた難民にとって、迫害を受けた証拠を持ってくることはとても難しい。しかし、現状日本では、難民認定の手続きにおいて、多くの証拠資料を提出することが求められています。
左から ジェノバ英子さん、田中志穂さん 田中 :まず難民がに日本で「難民」として認められるためには、難民であることを証明しなくてはならないという手続きの壁があります。命からがら逃れてきた難民にとって、迫害を受けた証拠を持ってくることはとても難しい。しかし、現状日本では、難民認定の手続きにおいて、多くの証拠資料を提出することが求められています。
また、手続きの期間が長く、平均で2-3年ほどかかり、その間の生活も大変です。難民申請者が急増した昨年の冬は、残念ながら十分に支援が行き届かず、家がない、その日食べるものがないという人が、路上で夜を過ごさざるを得ないという状況に陥りました。難民たちが、日本社会で孤立しないために、どうしたらいいのか?ということですが、難民が社会の一員として暮らしていけるような受け入れのあり方や地域づくりという、日本社会の課題として考えていくことが重要だと思っています。
そして、最近の私たちの支援の現場では、女性の難民が増えています。シングルマザーだったり、DV被害者だったり、かなり重い事情を抱えている人が多くいます。民族によっても異なりますが、男性に比べ、女性は家庭で家事や子育てに従事することが多く、社会から孤立しがちです。このような女性たちを対象として、伝統的なレース編み「オヤ」を使ったコミュニティ支援事業を行っています。また、オヤを通じて難民のことを知っていただく「オヤ・カフェ」というイベントも定期的に開催しています。
― ユニクロは労働支援という形で難民を受け入れていますが。
シェルバ:まず、日本人よりもガッツがあるという声が店舗からあがってきました。会社としては、勢いがあること、パワーがあることが、とてもありがたいと思いました。主婦のパートが多い昼の時間。ミャンマーの文化や食事の話などで交流が生まれ、日本の女性にとっても新しい気づきが生まれました。
へゴム:ユニクロで働く中で、ユニクロのストールを、ミャンマーの巻き方で頭に巻いていて、「いい巻き方だね!」とか、「似合っているね!」という言葉をもらったり、「ミャンマーについて教えて欲しい」という暖かい言葉をもらいました。
日本でこうして受け入れてもらったことで、もし夫に何かあってひとりになっても、こどもを支える事ができるという自信になりました。
シェルバ:ユニクロは、難民の方を受け入れることで、グローバル人材の発掘にもつながり、会社としての夢も生まれました。
へゴム:将来、バングラディッシュのキャンプの子供たちの教育をやりたいという大きな夢も持っているけれど、まずユニクロでいろんな勉強をしたいです。
シェルバ:これまで8名の従業員(全員元店長)がバングラディッシュのキャンプに人材支援で行きましたが、そのうちの7名が女性!そこでは、0からの立ち上げやリーダーとしての力を、現地で見せてきました。これからまた2人、支援に行く事になっています。
― 難民支援協会では、料理の本も?
田中:お料理であれば身近なものだと考えました。これを通じて、難民の事を知ってもらいたいと思っています。
質問タイム
― へゴムさんも難民認定を?
へゴム:身体に大きな傷がなくてはならないなど、難民である証明ができないものが多く、認定を受ける事は本当に難しいです。わたしは旦那が認定を受けたので、妻として日本に来る事ができました。
−これからもっと難民の認識を広めていくにはどうしたらいいでしょうか?
根本:人は非力ではあっても無力ではないです。
一人一人がfacebookや口コミなどで今日聞いた事を少しずつでも発信していくことで広がっていくものだと考えています。一夜にして変わらない。長期戦で考え、パワーのある若者たちの力と一緒に伝えていきたいと思います。
シェルバ: わたしたちはお客様とダイレクトに話をできる仕事をしています。ユニクロを通して難民知ってもらうという事が私たちにできることだと思います。現地にいる人材支援野社員には、facebookを使ってリアルタイムで現状を伝えているため、ユニクロを通じ、ファッションという形でも発信していく事ができてます。今後も子どもたちのプロジェクトなど、新しい形での支援なども考えています。
交流会

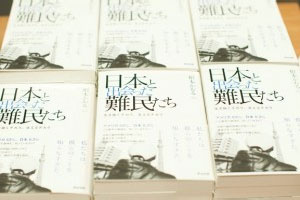 ディスカッションの勢いそのまま、交流会は行われました。
ディスカッションの勢いそのまま、交流会は行われました。
多世代多業種の方が「難民」 という共通したキーワードを様々な角度から話し合っていました。
大切なことは、言葉や単語ではなく、ひとりひとりの"意識"、"想い"や"行動"なのではないかと強く感じました。
そして、小さな課題や問題のひとつひとつを自分事として捉え、改善や解決する方法をみんなで考え続ける事が重要なのではないかと思います。結果、その繰り返しの中で生まれるモノが、これからを生きるチカラになり、自分だけでなく、誰かを支えるチカラになるのではないでしょうか。
写真:望月 小夜加
関連リンク
3*3ラボ(さんさんらぼ)
環境プロダクト「ものづくりからことづくり」研究会
3R(Reduce:減らす、Reuse:再活用、Recycle:リサイクル)と3rdプレイス(家と職場以外の場所)づくりを目指し、毎月ゲストをお招きしたセミナーを実施します。
おすすめ情報
-

【3*3LABO×難民支援協会】Refugee Talk-難民を学ぶ夕べ<年末特別版>Charity Party without Borders
2014年12月17日(水)19:00〜21:30
-

【3*3 LABO×難民支援協会】「難民×社会」のつながりの可能性を考える-日本の事例から学ぶ
2014年11月6日(木)19:00〜21:30
-

【大丸有シゼンノコパン】
大丸有の植物に江戸を「視(み)る」~人が利用してきた植物たち~
【緑地を探ろう!】2025年6月21日(土)10:00~12:00
-

【大丸有シゼンノコパン】
新緑のなかの生きものを「観(み)る」~生きもの調査にも挑戦‼~
【親子イベント/まちの生きもの】2025年5月17日(土)13:30~15:30
イベント
注目のワード
人気記事MORE
- 1
 【丸の内プラチナ大学】2024年度開講のご案内~第9期生募集中!~
【丸の内プラチナ大学】2024年度開講のご案内~第9期生募集中!~ - 2
 【大丸有シゼンノコパン】大手町から宇宙を「望る(みる)」ービルの隙間からみる、星空の先ー
【大丸有シゼンノコパン】大手町から宇宙を「望る(みる)」ービルの隙間からみる、星空の先ー - 3
 大丸有でつながる・ネイチャープログラム大丸有シゼンノコパン 冬
大丸有でつながる・ネイチャープログラム大丸有シゼンノコパン 冬 - 4
 【丸の内プラチナ大学】逆参勤交代コース 壱岐市フィールドワーク
【丸の内プラチナ大学】逆参勤交代コース 壱岐市フィールドワーク - 5
 【大丸有シゼンノコパン】【朝活】大丸有で芽吹きを「視る(みる)」ー春の兆しは枝先からー/まちの四季
【大丸有シゼンノコパン】【朝活】大丸有で芽吹きを「視る(みる)」ー春の兆しは枝先からー/まちの四季 - 6
 3×3Lab Future個人会員~2024年度(新規・継続会員)募集のお知らせ~
3×3Lab Future個人会員~2024年度(新規・継続会員)募集のお知らせ~ - 7
 【レポート】遊休資源が輝く未来へ 〜山形に学ぶ持続可能な地域づくりの挑戦〜
【レポート】遊休資源が輝く未来へ 〜山形に学ぶ持続可能な地域づくりの挑戦〜 - 8
 フェアウッド×家具~ものづくりを通じた自然や生態系への貢献~
フェアウッド×家具~ものづくりを通じた自然や生態系への貢献~ - 9
 指導経験ゼロから日本一のチームを作った「日本一オーラのない監督」が語る存在感と自己肯定感
指導経験ゼロから日本一のチームを作った「日本一オーラのない監督」が語る存在感と自己肯定感 - 10
 【大丸有フォトアーカイブ】第2回 みんなの写真展 2月21日~3月4日
【大丸有フォトアーカイブ】第2回 みんなの写真展 2月21日~3月4日


