

8,9,11
学生や社会人などを対象にした丸の内プラチナ大学の繋がる観光創造コースは、毎回の講座で様々な地域や人々を紹介し、互いを知り尊重し合えるコミュニティを形成することで地域を盛り上げていきます。2024年度同講座の最終回となるDay7が2月20日、奈良の魅力をテーマに3×3 Lab Futureで開催されました。
- 続きを読む
- 「あるもの探しのプロ」が語る奈良の魅力
「あるもの探しのプロ」が語る奈良の魅力
講師の吉田淳一氏は「この講座は『無いものねだりよりも、あるもの(人)探し!』というテーマで開催してきたが、今日は奈良愛にあふれ、奈良にしかない魅力を探して全国に広めているお二方をお迎えした。今日の講座も含めて、このコースではいろんな出会いがあったと思うので、その繋がりを大切にして、今後ぜひ各地域を訪れてほしい」と語り、講座を始めました。
 繋がる観光創造コースの講師 吉田淳一氏
繋がる観光創造コースの講師 吉田淳一氏
吉田氏から「あるもの探しのプロ」として紹介されたのは、奈良のトビラ合同会社代表社員徳永祐巳子氏と、生駒あさみ氏です。
生駒氏は茨城県出身、卒業後に東京で社会人として働いていましたが、修学旅行以来となる奈良への訪問をきっかけに、奈良の魅力にどっぷりはまってしまったそうです。生駒氏は「その年のうちにもう一度奈良を訪れただけでなく、その後も東京で働きながら新幹線や夜行バスで奈良との往復を繰り返し、最終的には1か月の半分ぐらい、奈良にいるほどでした」と言い、2014年にいよいよ奈良に移住したそうです。念願の奈良移住を果たした生駒氏は、奈良に関する様々な仕事に携わり、メディアの編集やイベントの企画運営、店舗経営、観光ツアーなど多岐にわたり奈良の魅力を伝える活動をしています。
一方、徳永氏は生まれも育ちも奈良という生粋の奈良県民で、仕事も奈良に関する情報誌や雑誌の編集に始まり、現在ではフリーランスの編集者として、25年になります。「編集の力をまちづくりや課題解決に活かす」(同氏)ための情報発信をサポートし、まちづくりや特産品のパッケージデザインなども手掛けています。さらに、NPO法人の理事長を務め、奈良の歴史・文化・自然の魅力を伝える市民講座なども開催しています。
 左:東京で働きながら夜行バスで通うほど奈良への愛を深めたと語る生駒あさみ氏
左:東京で働きながら夜行バスで通うほど奈良への愛を深めたと語る生駒あさみ氏
右:30代までは奈良に関する情報誌を長年手掛けてきたという徳永祐巳子氏
自己紹介の後は、いよいよ本題である「奈良のトビラ」に話は移っていきます。生駒氏は「皆さん奈良と言えば鹿と大仏はご存じと思うが、それだけじゃないということを今日はお伝えしたい」と語り始めました。
徳永氏は、「大仏と鹿を見るために奈良に訪れる人の多くは、外国人観光客も含めて奈良市にしか行かない。しかし奈良県には39の市町村がある。私たちは奈良のトビラを通じて、各地域の魅力を発信している」と説明します。
生駒氏と徳永氏が運営する奈良のトビラでは、奈良の名産品やユニークな商品を多くの人に知ってもらうために、アンテナストアの運営を通して情報発信を行なっています。他府県で期間限定のアンテナストアを開設し、来客者を奈良観光に誘導することも目指しています。
「アンテナストアを通じて奈良には魅力的なモノがあるということを知ってから、実際に奈良に観光に来てもらいたい。私たちは産業から観光へ誘導するハブ的な場として全国を巡っている」(生駒氏)といいます。
そして単に観光客を増やすのではなく、リピーターを増やすことが真の目的だと生駒氏は説明を続けます。「奈良は一度だけ訪れて終わりではなく、何度も来る価値のある場所。奈良の落ち着いた雰囲気や豊かな自然、文化的・歴史的な奥深さに魅力を感じてくれる人を、県外のアンテナストアを入口に奈良まで引き込みたいと思っている。一過性の観光客の増加ではなく、私たちのような奈良へ強い想いを持ってくれる人を増やしたい」

2023年にスタートした奈良のトビラは、これまでに大阪、東京、滋賀、宮城、佐賀、福岡の6都府県でアンテナストアを開催してきました。
紹介された商品の一例として、漆塗りの食器があります。「漆塗りといえば能登が有名だが、実は奈良が発祥で、奈良から能登へ伝わったと言われている。私たちは神社仏閣の漆に関わる職人さんが作る商品を販売している」と、生駒氏は話します。
また、奈良のトビラでは、奈良で出土した古代の瓦をモチーフにした月餅も人気商品だそうです。「冬はイチゴ農家を営み、春から秋の間だけ中華カフェを営むお店の商品で、1個500~600円するにもかかわらず、リピーターが続出している」(生駒氏)と紹介しました。
そのほかにも、アンテナストアではお茶やそうめん、鹿グッズなども人気だそうです。昨年東京で開催した期間中は、物販だけではなく、お寺の住職の講演会や奈良の伝統行事、若草山焼きのトークショー、古代のボードゲーム「かりうち」の競技大会など、PRイベントも開催しています。
県外で活動する一方で、奈良のトビラは平城宮跡内のいざない館に常設店をオープンし、そこでも毎月イベントを開催しています。徳永氏は「毎回参加してくれる固定ファンも多くなってきた」と話します。「他府県で開催したイベント参加者が、『実際に若草山の山焼きを見にきました』などと言って常設店を訪れてくれることが増えたので、他府県にも出向いていくことは大事だなと感じている」(徳永氏)とのことでした。

奈良愛にあふれる2人が勧める厳選スポット
2人は最後に、奈良のおすすめスポットをいくつか紹介してくれました。生駒氏と徳永氏が共通するのは平城宮跡で、生駒氏はその中でも特に大極殿、徳永氏は朱雀門だそうです。
生駒氏がそのほかに挙げたのが、奈良県天川村の洞川(どろがわ)です。「2010年に初めて洞川に泊まった時に、コバルトブルーの川の水、澄んだ空気、満開の桜に本当に感動した。洞川は修行場、大峯山に登拝するための修験者の宿場なので、夜になると錫杖(しゃくじょう)やほら貝の音が聞こえてきて、異世界にいるようだった。それから引っ越しをする2014年まで、毎月夜行バスで通った」(生駒氏)と語るほど。
歴史や文化と絡めておすすめスポットを紹介してくれた生駒氏の一方、徳永氏は奈良の空が好きだと言います。「東京から来る人にもよく言われるが、奈良の空の雲の移り変わりはすごく素敵だと思う。私たちも実際、朝起きて見上げるとすごく綺麗な空が広がっていると感じることが多い。日中の空だけでなく、夜の若草山からの夜景もゆらゆらと揺らめいている感じがものすごく奈良らしくて綺麗」(徳永氏)と話しました。
2人は他に奈良の各所を挙げ、最後に、「私たちは奈良におりますので、いつでも奈良でお待ちしています」と受講生らに挨拶をしてトークセッションは終了となりました。
 二人の軽快なトークに、時折会場は笑いに包まれた
二人の軽快なトークに、時折会場は笑いに包まれた
バスガイドの人手不足を解消する新たなサービス
奈良のトビラのトークの後、講師の吉田氏から奈良交通の「リモートバスガイド」という新たな取り組みが紹介されました。関東圏では修学旅行の定番の地である奈良県ですが、一昔前までバスガイドが当たり前のように同乗していたものの、近年の担い手不足は深刻です。奈良交通では最盛期の1980年代にはおよそ220人在籍していたバスガイドが、現在はわずか17人と10分の1以下にまで減ってしまいました。
そんな人手不足を補おうと、奈良交通では2023年から遠隔の基地局からモニター越しに観光案内をするリモートガイドを導入しました。吉田氏はリモートガイドについて、「現代の技術を使えば、このようなコミュニケーションも可能。奈良は誰もが一度は行ってみたいところなので、テクノロジーで人手不足を補っている良い例だ」と語りました。
また吉田氏は、奈良県が野球のグローブ、スキー靴、靴下の生産、そしてピアノの保有率が日本一であることなど、奈良に関するトリビアを交えながら、最後に、「奈良県内にはふるさと納税の返礼品で宿泊に使えるクーポンを発行している市町村もある。今日の話を聞いて、興味を持った人は是非実際に足を運んでみてほしい」と締めくくりました。

講座の終了後は、受講生らに奈良の食材を使った料理が提供されました。奈良県が発祥とされる竜田揚げ、倭鴨を使ったつくね煮、奈良県のアンテナショップで売り上げ1位を記録したこともある田舎あげの焼き物、大和の伝統野菜のひとつである大和まなの和え物、そして奈良県の日本酒もふるまわれました。参加者らは、これらの食を楽しみつつ、奈良県への魅力に改めて想いを馳せているようでした。
 左:奈良の食材をふんだんに使った料理の品々
左:奈良の食材をふんだんに使った料理の品々
右:講座終了後、和気あいあいとした雰囲気の交流会
生駒氏と徳永氏が語る奈良の魅力は、歴史・文化・自然が融合された素晴らしさといえるでしょう。古くからの歴史や、その中で醸成された文化、豊かな自然が混然一体となって調和し、存在しているのが奈良という土地の素晴らしさだと感じられた回でした。
丸の内プラチナ大学
あなたの「今後ありたい姿」「今すべきこと」とは?
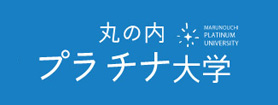
丸の内プラチナ大学では、ビジネスパーソンを対象としたキャリア講座を提供しています。講座を通じて創造性を高め、人とつながることで、組織での再活躍のほか、起業や地域・社会貢献など、受講生の様々な可能性を広げます。
おすすめ情報
-

【丸の内プラチナ大学】逆参勤交代コース 石川県七尾市フィールドワーク
2025年11月7日(金)~9日(日)
-

【丸の内プラチナ大学特別連携講座】すさきがすきさフェス Vol.1 ~須崎市交流イベント 2025 in TOKYO~
2025年10月25日(土) 16:00~19:00
-

【FCAJ共催イベント】EMICoフォーラム2025 「産学官民の地域共創の場 イノベーションコモンズの現在地とこれから」
2025年11月5日(水) 15:00~18:00
-

【レポート】AI時代に求められるコミュニティマネジャーの価値と役割
丸の内コミュマネ大学~AI×コミュニティの未来~ 2025年7月10日(木)開催
イベント
注目のワード
人気記事MORE
- 1
 【丸の内プラチナ大学】2025年度開講のご案内~第10期生募集中!~
【丸の内プラチナ大学】2025年度開講のご案内~第10期生募集中!~ - 2
 【大丸有シゼンノコパン】色彩豊かな冬の鳥を「観る(みる)」 ~極寒の今こそ絶好の"鳥"日和!~【まちの生きもの】
【大丸有シゼンノコパン】色彩豊かな冬の鳥を「観る(みる)」 ~極寒の今こそ絶好の"鳥"日和!~【まちの生きもの】 - 3
 丸の内プラチナ大学2025 逆参勤交代コース特別講座 飛騨ナイト
丸の内プラチナ大学2025 逆参勤交代コース特別講座 飛騨ナイト - 4
 大丸有でつながる・ネイチャープログラム大丸有シゼンノコパン 冬
大丸有でつながる・ネイチャープログラム大丸有シゼンノコパン 冬 - 5
 【大丸有シゼンノコパン】都心の緑地に春の目覚めを「覗る(みる)」~生きものとの共生のヒントを探して~【まちの生きもの/親子・初心者の大人向け】
【大丸有シゼンノコパン】都心の緑地に春の目覚めを「覗る(みる)」~生きものとの共生のヒントを探して~【まちの生きもの/親子・初心者の大人向け】 - 6
 【大丸有シゼンノコパン】ビルや樹々の隙間に星空を「望る(みる)」 ~「すばる」や「月」はどこにある?~【まちの星座】
【大丸有シゼンノコパン】ビルや樹々の隙間に星空を「望る(みる)」 ~「すばる」や「月」はどこにある?~【まちの星座】 - 7
 【レポート】関係資本の力を最大化する コミュニティデザインと持続的価値創造
【レポート】関係資本の力を最大化する コミュニティデザインと持続的価値創造 - 8
 3×3Lab Future個人会員~2025年度(新規・継続会員)募集のお知らせ~
3×3Lab Future個人会員~2025年度(新規・継続会員)募集のお知らせ~ - 9
 【レポート】共創がもたらす新たな価値創造 〜リビングラボが描く未来の地域経営~
【レポート】共創がもたらす新たな価値創造 〜リビングラボが描く未来の地域経営~ - 10
 【レポート】共感が未来を動かす 〜 クリエイティブが地域に灯す、新しい価値のつくり方
【レポート】共感が未来を動かす 〜 クリエイティブが地域に灯す、新しい価値のつくり方

