

コワーキングスペース、3rdプレイス同士の連携は、今までありそうで、意外になかったもの。そんな中、組織間・施設間連携を進めているのが、NTTデータが2017年7月に東京・大手町に開設した「BeSTA FinTech Lab」(BFL)と、エコッツェリア協会が運営する3×3Lab Futureです。
開所したBFLが3×3Lab Futureと定期的に合同イベントを開催することとなり、その第1弾は7月に衆議院議員・石破茂氏など豪華ゲストを招いて開催され、2回目は、次世代の投資のあり方を提示し続ける鎌倉投信の新井和宏氏がBFLにて講演。そして3回目は、場所を再び3×3Lab Futureに戻し、10月6日に開催されました。ゲストは、日本のCSR活動の草分け的存在であり、数々の主要なコンセプトを日本に導入、定着させてきた、ピーター・D・ピーダーセン氏(イースクエア共同創業者、リーダーシップ・アカデミーTACL代表、NELIS共同代表)です。
そのピーダーセン氏が、著書のタイトルでもある『レジリエント・カンパニー』(東洋経済新報社刊)をテーマに、21世紀社会を生き抜く企業のあり方を模索するのが今回のセッションです。タイトルは「しなやかで強い企業の条件~トリプルA経営のすすめ~」。後半は、ピーダーセン氏が開発した企業・組織の評価方法を実践しながらの質疑応答も盛んに行われました。
現代企業が持つべき「強さ」を歴史的に振り返る

ピーダーセン氏は「強い企業」を論じるにあたって、まず2つの視点から現代企業について疑問を提示します。
ひとつは歴史的な視点。氏によれば、会社組織のルーツは1600年代の東インド会社にあり、その流れは産業革命期の資本家による企業に引き継がれ、現代の企業にまで引き継がれています。その目的は、「生産性を高め、消費社会を実現し、豊かな人間の暮らしを世界の隅々まで行き渡らせること」。産業資本主義の拡大は人々の暮らしを一変させ、「産業革命当時には豊かさを実現できなかったところまで、行き渡らそうとしている」のが現代です。しかし、20世紀後半に至ってそこに破綻が生じていると氏は指摘、それに伴い、企業のあり方も問われるようになりました。
「豊かな消費社会を実現したが、このままでは地球が破綻するか、人間の枯渇し、荒んでしまうことが明確になり、70~90年代には企業のあり方や目的が問われるようになった。何か責任があるんじゃないか、もっと大きな役割を持っているんじゃないか。企業が未知数の領域に踏み込もうとしているのが現代ではないだろうか」(ピーダーセン氏)
環境問題を背景に広まったCSR活動、現代のキーワードになったCSV、サステナブル経営もその見直しの流れを汲むものと言えるでしょう。企業の設立を許可するモノが、最初は女王陛下、次に資本家、そして現代ではマルチステークホルダーになっていることもそのひとつの証左である、と氏は指摘します。
もうひとつの視点は「人材のマネジメント」です。「不安定」「不確実」「複雑」「不明瞭」という4つの"ふ"の時代に、どのように人材をマネジメントするのか、新しいアプローチが問われています。
「日本では今、働き方改革で働くな、と言う一方で、中国に負けないようにもっと生産性を上げろ、もっと早く走れ、なんて矛盾したことを言われ、人間がますます荒んでしまいそうな状況」(ピーダーセン氏)
これは今に始まったことではなく、ドラッカーやトフラーが散々指摘してきたことでもあると氏は指摘。
ピーダーセン氏は、この2つの視点から現代社会、現代企業が行き詰まりを見せていることを解説したうえで、「我々がやるべきこと」として、個人は「ハイプに惑わされないこと」、そして企業は「フューチャー・プルーフな組織になること」という2点を挙げています。ハイプとは誇大広告などを指す言葉で、つまり「こんな時代だからこそ、自分の軸を持って、ビジネス誌やよく分からないコンサルの言うことに振り回されちゃダメ」ということ。 フューチャー・プルーフとは「未来への耐性」。未来は予測できない。だからひとつの方向性しか持てない組織では生き残れない。「強い風にはなびき、柔軟に対応できるレジリエントなカンパニーでなければ生き残れない」と氏は説明しています。
このレジリエント・カンパニーをどうすれば作れるのか?が21世紀の組織が直面する最大の課題であるとピーダーセン氏。
「オープン・イノベーション、コ・クリエーションといろいろな言葉が出てきているが、これはつまり、新しい組織のマネジメント方法を作りだそうとする試みではないか」(ピーダーセン氏)
トリプルAの実現を社員一人ひとりが目指せ

レジリエント・カンパニーを実現するためにどうしたらいいのか。ピーダーセン氏は「トリプルA」が必要だと説いています。トリプルAとは「Anchoring」=アンカリング「Adaptiveness」=自己変革力「Alignment」=社会性 の3つです。
優れた組織の定義は「稼ぐ力を持ち続ける」、「働く人を活かす」、「社会的『善』を生み出す」という3つを同時に成し遂げることであるとし、トリプルAはその達成に不可欠な組織のベースであると解説しています。
アンカリングとは「拠り所」のことで、社員、従業員らが組織への帰属意識を持つためによって立つ場所。これは「魂のようなものかもしれない」とピーダーセン氏。自己変革力Adaptivenessについては、「Adaptabilityという言葉もあるが、こちらは外的圧力によるというニュアンスが大きい。もっと内的な、自ら変革していくという意味でAdaptivenessを使った」と解説。いわば"手先の器用さ"のようなものでもあり、変化に対して柔軟に社内で変革を起こしていく力ということになります。そして、社会性Alignmentは、「ソサエティ・イン」という言葉に近い意味合いですが、より「社会の期待の変化にベクトルを合わせる能力」というニュアンス。「社会の流れ、社会が求めるものを理解しなければ、ベクトルを合わせることもできない」とピーダーセン氏。また、これがなければ、結局企業活動と社会への影響が、トレードオフになってしまうとも指摘しています。「企業活動と社会的善が矛盾していないこと。シナジーという言葉もあるが、これを"トレードオン"と呼びたい」とピーダーセン氏は述べ、この3点を実現することが強い企業になる必要条件であると定義します。
「この3つが非常に高いレベルで達成できていれば、強い組織、強い企業と言えるのではないか。そしてこれは、水面下の組織体質であり、水面上に現れる売上や利益などからは決して読み取ることができないものだ」(ピーダーセン氏)
また、トリプルAの実現は、経営やマネジメントにコミットするすべての管理職者の責任であるとともに、非管理職者にとっても、やがてはマネジメント層に入るという意味において、決して無関係のものではないと指摘しています。
レジリエント・カンパニーの実態を事例から

そして、この分析にもとづいて開発した、トリプルAの達成度を診断するツールを解説します。ピーダーセン氏は、PwCジャパンと提携してこのツールを開発、すでに多くの企業で診断実施をしているそうです。
その結果の一例を――。2兆円以上の超大手企業40社で実施したところ、職級が上がるほど自社に対し肯定的になる傾向が見えました。部長以上級の管理職と一般社員を比較すると、総じて管理職のほうがスコアが高く、特にアンカリングの項目で差が大きい。ピーダーセン氏は「部長と課長の間でこれほど大きい差があることには驚いた」としつつ、組織の実態把握において、組織上部の人間の声だけに頼ることのリスクを指摘。
そのうえで優れた企業の実例として、サントリー、トヨタ、ソニーを紹介し、それぞれの特徴について解説しています。サントリーは創業者の「やってみなはれ」が文化として根付き、社内の自己変革力を強くブーストしています。トヨタも年間50万件にのぼる社員からの提案を受け付ける自己変革力とともに、社会の流れにアジャストするアライメントのスコアも非常に高くなっています。ソニーは逆に悪しき一例で、氏が20数年前に環境戦略でサポートした時代は優れたビジョナリーカンパニーだったそうですが、"失われた20年"を経験する間に「企業のパーパス、アンカリングの薄弱化が起きたのでは」とピーダーセン氏は見ています。内的動機づけが失われたソニーからイノベーションは起きていない。ようやく最近になって、「アンカリングの再設定の必要性に気付いてきたのでは」とピーダーセン氏は話しています。
そして、トリプルAがうまくいっていないと、現在某日本企業が陥っているような危機を引き起こす可能性が高いと話し、逆にうまく行っていると、水面上の指標ではあるが、株価にも大きく影響を与えることを解説。氏が最新著書でレジリエント・カンパニーと定義している20社の株価の変動を見てみると、非常に強い復元力があることが分かります。例えば、2008年のリーマンショック時に、S&P500の企業は2003年比で平均-19%であったのに対し、レジリエント・カンパニーは7%の上昇を見せています。「トリプルAの企業と、そうでない企業の違いを見てみると、株価と明らかな相関性がありそうだ」とピーダーセン氏。
そして、トリプルA実現のために、「まず組織の課題を体系的に明らかにすること」と、「拙速な判断を避けて」とアドバイスしています。体系的に課題を明らかにするとは、企業の強み、弱みを把握しようということ。また、拙速な判断を避けるとは、先日のトリプルAの自己評価が、職級が高い人ほど甘くなる傾向にあることを踏まえて判断しろということ。「企業で副社長以下役員から部長までを集めてセミナーをやると、最後には『よし分かった! あとはアクションだ!』と盛り上がるが、いやいやそうじゃないだろうと。その拙速な判断が間違いのもとで、職級の高くはない、一般社員の声を聞くことが非常に重要」であることを話し、講義はクローズとなりました。
ここまでのセッションで、会場からは主に職級と意識の違いの相関性について質問が集中しました。「長くいることで客観性を欠くということなのか」、「年功序列が強い日本だから、職級ではなく年齢・在職年数が変数になるのではないか」という声が上がりましたが、ピーダーセン氏によると年齢では意識に大きな差が見られなかったそうです。「帰属意識とも相関性があるかもしれない。その点、今後中途採用者との比較などもする必要があるかもしれない」とピーダーセン氏。また、男女の違いについては「驚くほど差がでなかった」とも。このほか、質疑応答の中で「社会のデザイン」に話題が及んだ際には、「日本は、政治・経済を含め、小手先のことに終始してばかりで大きな未来設計が出来ていないのではないか」と、耳に痛い指摘をしています。
自己診断で見えてきた?日本企業の課題
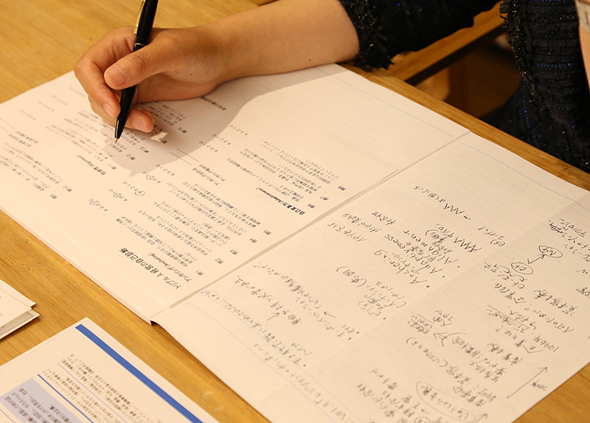
後半は、ピーダーセン氏が作成したツールを参加者も使って、自己意識をチェックしています。45問の質問に回答するもので、コンサルが行うような一般的なアンケートに比べると遥かに質問が少ない。「ああいうのはお金を余分に取るために多くしているのであって、実際は200問もいらない、45問で十分だ」とピーダーセン氏。
この結果、自社評価がトリプルA=「AAA」だったのは会場では1人。「AA」はゼロ、「A」が5人でした。ピーダーセン氏は「今まで講演でトリプルAが出たのは1人だけで、しかも社長だった」そうで、今回一般の社員でトリプルAが付いた例は非常に珍しいと話しています。今回トリプルAを付けた参加者は、某大手メーカーの社員ですが、たまたま社長に近いポジションで、トップの経営理念を多く聞かされていることも影響しているのではと分析しています。以下、一般的なボリュームゾーンとなる「BBB」は6人、「BB」は5人、「B」は5人。「CCC」以下は5名という結果が得られました。
この後、さらにこの診断結果を踏まえての質疑応答へと移り、熱のこもった議論が交わされました。グローバル企業の日本法人の評価の仕方について、社内コミュニケーションの重要性について、社会性のある経営で利益を出す方法は、といった内容です。質問というよりは参加者から意見を述べ、それに対するピーダーセン氏の意見を聞く、まさにセッションといった形でした。
その中で興味深かったのは、「経営改善はトップダウンか、ボトムアップか」という質問です。ピーダーセン氏は「これは核心を突く質問」と述べ、結論としては「レジリエント・カンパニーでは、トップダウンアップ、ボトムアップダウンがうまく回っている」と話しています。
「経営者の質が大きく左右することは間違いないが、トップが方向性を示し、それが下にきちんと伝わり、なおかつ、ボトムからの情報のアップも上へ伝わるという、通気性の良さがポイントのひとつになっている」(ピーダーセン氏)
また、「日本ではマネジャーは育ったがリーダーが育たない」という声に対しては、もともと氏が専門とする文化人類学的な分析と意見が、参加者に非常に刺さっていたようでした。 「日本は全体の規範を内在化するベクトルが強い"枠の文化"。安定性と効率化を求める時代には最適だが、これからの時代は、全体に対して個人=meを打ち出す欧米の強い"個人"がリーダーとして求められるのかもしれない」(ピーダーセン氏)
非常に地に足の着いた密度の高い議論が交わされた時間となり、参加者たちの知的欲求も大いに満足されたセッションとなりました。参加者の意識変革が、実践へ、組織の変革につながっていくよう期待しましょう。

関連リンク
地域プロジェクト
地方と都市との新しい関係を築く

「地方創生」をテーマに各地域の現状や課題について理解を深め、自治体や中小企業、NPOなど、地域に関わるさまざまな方達と都心の企業やビジネスパーソンが連携し、課題解決に向けた方策について探っていきます。
おすすめ情報
-

【レポート】豊かな自然に囲まれたサイクリングツアーとれんこん掘り体験で土浦の魅力を再発見
土浦市サイクリングウェルネス研修モニターツアー 2024年11月9日(土)~10日(日)開催
-

【レポート】遊休資源が輝く未来へ 〜山形に学ぶ持続可能な地域づくりの挑戦〜
地域活性化先進地域山形県視察 2024年10月26日(土)~28日(月)
-

【大丸有シゼンノコパン】
大丸有の植物に江戸を「視(み)る」~人が利用してきた植物たち~
【緑地を探ろう!】2025年6月21日(土)10:00~12:00
-

【大丸有シゼンノコパン】
新緑のなかの生きものを「観(み)る」~生きもの調査にも挑戦‼~
【親子イベント/まちの生きもの】2025年5月17日(土)13:30~15:30
イベント
注目のワード
人気記事MORE
- 1
 【丸の内プラチナ大学】2024年度開講のご案内~第9期生募集中!~
【丸の内プラチナ大学】2024年度開講のご案内~第9期生募集中!~ - 2
 【大丸有シゼンノコパン】大手町から宇宙を「望る(みる)」ービルの隙間からみる、星空の先ー
【大丸有シゼンノコパン】大手町から宇宙を「望る(みる)」ービルの隙間からみる、星空の先ー - 3
 大丸有でつながる・ネイチャープログラム大丸有シゼンノコパン 冬
大丸有でつながる・ネイチャープログラム大丸有シゼンノコパン 冬 - 4
 【丸の内プラチナ大学】逆参勤交代コース 壱岐市フィールドワーク
【丸の内プラチナ大学】逆参勤交代コース 壱岐市フィールドワーク - 5
 【大丸有シゼンノコパン】【朝活】大丸有で芽吹きを「視る(みる)」ー春の兆しは枝先からー/まちの四季
【大丸有シゼンノコパン】【朝活】大丸有で芽吹きを「視る(みる)」ー春の兆しは枝先からー/まちの四季 - 6
 3×3Lab Future個人会員~2024年度(新規・継続会員)募集のお知らせ~
3×3Lab Future個人会員~2024年度(新規・継続会員)募集のお知らせ~ - 7
 【レポート】遊休資源が輝く未来へ 〜山形に学ぶ持続可能な地域づくりの挑戦〜
【レポート】遊休資源が輝く未来へ 〜山形に学ぶ持続可能な地域づくりの挑戦〜 - 8
 フェアウッド×家具~ものづくりを通じた自然や生態系への貢献~
フェアウッド×家具~ものづくりを通じた自然や生態系への貢献~ - 9
 指導経験ゼロから日本一のチームを作った「日本一オーラのない監督」が語る存在感と自己肯定感
指導経験ゼロから日本一のチームを作った「日本一オーラのない監督」が語る存在感と自己肯定感 - 10
 【大丸有フォトアーカイブ】第2回 みんなの写真展 2月21日~3月4日
【大丸有フォトアーカイブ】第2回 みんなの写真展 2月21日~3月4日

