

CSRイノベーションWGが11月28日(木)、丸の内ビルディング17階のデロイト トーマツ コンサルティング株式会社で開催されました。ゲストスピーカーに、長川知太郎氏(デロイト トーマツ コンサルティング株式会社 パートナー兼CSR推進室長)と、山下智子氏(特定非営利活動法人ピースウィンズ・ジャパン コミュニケーション部 広報)、ランディ・マーティン氏(Mercy Corps(マーシー・コー)東アジアパートナーシップ開発 担当ディレクター)を迎え、講演と質疑応答が展開されました。
あいさつ〜田口氏(エコッツェリア協会)
CSRと聞いて、ぼんやりとはイメージがあるかと思いますが、自分が持っているイメージと、社会とは一緒なのか。今年はISO26000と照らし合わせ、CSRをしっかり学ぼうという会を年4回開催し、講演を聴いてディスカッションをするワークショップを展開しています。
CSRの(S)ソーシャル(R)レスポンシビリティの部分は、会社だけがなし得るものではないと思っています。NPO・NGO・地域団体とタッグを組んで力を発揮していく活動を、今後は増やしていかなければと考えています。
今日は、個人、組織としてでも気づきを得て、一歩踏み出せるような回になればいいなと思います。
企業とNPOとのパートナーシップの必要性〜山下氏(ピースウィンズ・ジャパン)
どういった観点で企業がNPOの活動に関わっているのか、NPOはどのようにそれをインパクトとして社会に還元しているか、事例を交えご紹介したいと思います。
紛争や災害に対応する緊急支援を行っている、NPOピースウィンズ・ジャパンは、アフガニスタン、イラクなど中東での人道支援を対象にスタートした団体です。昨今のアジア地域での地震津波などにも緊急人道支援を行い、世界26カ国での支援実績があります。
しかし、NGO単体ではリソースが足りないと痛感。NGO単体ではでき得ない、支援企業の方のスキル、テクノロジー、人材、資金、さまざまなリソースを組み合わせることによって、よりスケールの大きい、サステナビリティのある社会発展が望めると、現場から感じています。
企業がどのように社会課題の解決に向けて、NPOと連携していくか、営利セクターの果たすべき役割がますます大きくなっています。
デロイト流プロボノ~長川知太郎氏

本講演では、デロイト トーマツ コンサルティング株式会社(以下、デロイトと略称)でプロボノが始められた経緯と、これまでの活動の中で得た、企業と非営利団体の連携における成果や課題、気づきについて、お話いただきました。
一般的に、企業がCSRに取り組む理由は、企業が自社利益の追求に留まらず、社会の「公器」としてありたいと考えているため、だと言われています。企業の経営資源は、もともと社会からの借り物であるため、企業も社会に対して還元を行わなければ、結果として、企業も社会も滅びるだろう、と考えられているためです。
デロイトにおいても同様で、「公器」の経営を意識し、身をもって実証実験をしたいと考え、プロボノを推進されています。
プロボノの定義は、「非営利団体に対し、無償で、コンサルタントとしての専門性を提供する活動」です。社員が1,000人を越えたことを機に、目先の利益ばかりを求めるのではなく、社会市民としての責任を果たし、ビジネスで得た知見や経験を社会に無償還元することで、社会や経済のさらなる発展に貢献したいと考えたことが、プロボノを始めたきっかけだそうです。
活動を始める際、中には、企業ブランドの認知向上を目的とするかどうか、との意見が出たそうですが、現在は中長期的、また短期的リターンを一切求めず、社会をより良くするための活動をされている非営利団体に対し、その活動をより広めていただくために、コンサルタントとしての知恵や経験を活かした無償サービスを提供しておられます。
これまで提供した中で、最も多いご支援内容は、非営利団体と一緒に、中長期の経営計画を策定するプロジェクトです。そこでは戦略を描くだけでなく、実行までお手伝いされています。ただ、プロボノ活動も3年目となり、これまでのような1団体に対し1つのプロジェクトを提供する「点」での支援から、「面」での働きかけへと、モードをシフトしているそうです。
具体的な取り組みとして、非営利団体・企業間の相互連携に対するニーズの把握や、非営利団体と企業とのマッチングによる戦略的連携文化の促進、また面を切る角度を変えて、「学生コンサルティング事業」というプログラムが実施されています。このプログラムでは、若年層の社会貢献活動への参加を促すことを目的に、大学生にコンサルティングのスキル・ノウハウを提供し、準コンサルタントとして育成した上で、学生が主体となって、非営利団体に対し、若者ならではの柔軟な思考やアイデアを活かしたコンサルティングを行っています。
今後も、一つ一つのプロジェクトに加え、より効果的・効率的に貢献度合いを広げていく仕組みや仕掛けを考え、展開していきたいと、お話下さいました。
また、これまで行われてきたプロボノの取り組み例として、ピースウィンズ・ジャパンと連携された「ファンドレイジング立案プロジェクト」が紹介されました。
当時、ピースウィンズ・ジャパンは、より幅広い層からの個人支援者の拡大という課題に直面されており、より効果的なファンドレイジング戦略の立案と、実現可能性の高い実行計画策定の必要性を感じておられました。そこで、個人支援者向けファンドレイジング活動のターゲットと目標を明確化し、その実現に向けたファンドレイジング戦略と、実行計画を策定されました。
このプロジェクトは約4ヶ月間実施され、下記の4つのステップに基づき、進められました。
ステップ1では、外部・内部環境分析を行いました。内部環境については、現在のピースウィンズ・ジャパンにおける寄付者の構造(金額、人数、年代層など)を分析するとともに、どのような価値観を持ち、なぜピースウィンズ・ジャパンを応援して下さっているのかなどを、調査しました。
他方で、外部環境については、一般生活者に対しアンケートを行い、寄付に対してどのような考えを持っているのか、ピースウィンズ・ジャパンの活動に対してどのような認識を持っているのかなどを、分析しました。
ステップ2では、ステップ1の分析結果を踏まえ、ファンドレイジング戦略の仮説を立てました。どのようなターゲット層を狙うと、ピースウィンズ・ジャパンの活動内容に、最も共感を得やすいのかを特定し、詳細化して優先順位をつけました。また、各ターゲット層に対し、どういったメッセージを投げかけると、最も効果的に響くのか、なども併せて検討しました。
ステップ3では、戦略を最終化するにあたり、数値目標に基づく全体の収支シミュレーションを行いました。そして、シミュレーション結果に応じ、目標の最終調整をしていきました。
ステップ4では、戦略を具体的なアクションベースに落とした、実行計画を策定するとともに、進捗管理制度を策定し、導入しました。
このプロジェクトにおいては、より効果的なファンドレイジング戦略と、実現可能性の高い実行計画を策定することが目的だったため、合宿を開き、皆で新しい考えを発表し、それに対しての意見やフィードバックを共有する場を設けたそうです。
デロイトのプロボノに関する特徴は、メンバーのフルタイムでのアサインです。プロボノを始める際、テストマーケティングとして、非営利団体にインタビューされたのですが、その中でコンサルタントが有償のプロジェクトとプロボノを掛け持ちしている際に、有償のプロジェクトにより軸足を置かれてしまうことを、懸念する声が寄せられたそうです。したがって、デロイトではフルタイムでのアサインを前提とした、プロボノ活動が行われています。
また、このプロジェクトを通じ得た成果として、一般事業会社に対し提供してきたコンサルティングにおける方法論・経験が通用することを再確認できたことが挙げられました。そして成功事例を蓄積することで、社内におけるプロボノ気運を高めることに繋がったとともに、ピースウィンズ・ジャパンとの協働の中で信頼関係を構築できたことが、大きな成果だと話されていました。
他方で、課題として挙げられたのは、ピースウィンズ・ジャパンにおいて、仕事の進め方やペースの違いによって戸惑いを感じる方がいらっしゃったことです。より皆の状況を把握し、ペースを調整しながら進めればよかったと、反省しておられました。また、新しい考えを組織に根付かせる際に必要となる意識改革について、その重要性と難しさを再認識する契機となった、ともお話下さいました。
山下氏:プロジェクトに携わらせていただきましたが、客観的な数値に裏付けられた戦略のもと、目標値を設定し、管理できるようになったことが、大きな収穫でした。また、コンサルタントの方に客観的に組織運営を見ていただいたおかげで、様々な気づきを得ることができました。特に、これまで支援を届ける先である受益者のことばかり考えていましたが、社会における存在として、団体はどうあるべきかという視点が抜け落ちていたことに、気づかされました。そして、常駐されていたコンサルタントの方々の姿を拝見する中で、非常に大きな気づきを得ることができました。
質疑応答
・ 学生コンサルティング事業に対して質問です。このプログラムは、単位として認められるものなのか、また、ボランティアもしくはインターンシップとして行われているのか、そして有償のアルバイトで実施しているのかを、お聞かせいただきたいです。
長川氏:本プログラムは、単位の認定をしておらず、弊社インターンシップにも関係ありません。したがって、どんなにハイパフォーマンスを残した方が弊社を受けて下さっても、入社が確約されているものではありません。また、学生の方にコンサルタントとしてのプロフェッショナル意識を持っていただくためにも、少ないながらアルバイト料をお支払しています。
・プロボノをするには人員を確保しなければいけないわけですが、どのような人が対象なのでしょうか。また、評価はどのように行われているのでしょうか。
長川氏: 1500人の社員全てがプロボノの対象になっています。全員参加が基本理念です。
ただ、パッションを持った人を優先したいと考えているため、日頃からプロボノを希望する人のリストを作り、まずはそこにノミネートしていただいています。そして、プロジェクトにその方々を優先的にアサインするよう手配をしています。
また、プロボノ参加者を通常のプロジェクトと同じように評価しています。マネジャー以上の管理職には売り上げ責任がつくため、プロボノが有償だった場合の価値換算が行われ、カウントされる仕組みとなっています。
・プロボノ後、戦略は根付いたのでしょうか?
山下氏:答えはYESです。根付いている点が二つあります。
一つが、私たちのファンドレイジング部門が、目標に対してどれ程達成できたのかを、明確化できるようになったことです。
二つ目は、投資しようという観点が生まれたことです。限られた資金の中で、できるだけ多く受益者に届けようというのが大半なのですが、私たちの活動を存続させるために支援いただく、という観点を持ち併せたことで、活動に広がりを持つことができました。
長川氏:ファンドレイジング戦略をお手伝いした後、現在では引き続き、学生コンサルタントによって、若年層にフォーカスしたファンドレイジング戦略を立案しています。若年層に、どのように呼び込み、そしてどのように寄付してもらうかを詳細化するお仕事と、呼び込みの部分でイベント運営などをお手伝いさせていただいています。
・プロボノをされる方が抱えている案件があった場合、他の方に預けるということですか。
マネジャー未満のスタッフは、組織としての仕事があるわけではなく、日々プロジェクトの仕事をしているため、プロジェクトが終了すると同時に、次の仕事としてプロボノにアサインされます。他方で、マネジャー以上のメンバーは、日頃やっている仕事を調整して、プロボノに移っていただいています。
・プロボノに参加された方の感想というのは、どのようなものが上がってきたのでしょうか。
長川氏:ポジティブな感想としては、組織変革の重要性についての気づきです。日頃、何万人という大きな組織の一企業部門で仕事をしていることが多いので、自分自身がやった仕事が現場の方にどう受け入れられて、自分が現場の人の日々の行動をどう変える可能性があるのか、肌で感じられないことが実は多いです。
しかし、プロボノでご一緒させて頂いている団体は100人未満のところが多く、一人一人の顔が見える中で、これは良かった、悪かった、実際にやりやすい、やりにくいなどを、ダイレクトに感じることができます。その中で、コンサルタントとしてのやりがい、変革の難しさ、大切さを気づきとして挙げてくれるメンバーが多くいます。
・ 人事評価のシステムがすぐに承認された訳ではないと思いますが、色々な意見が出た結果としてこのような制度が承認されたのか、あるいは、スムーズに承認されたのか、をお聞かせください。
長川氏:色々な議論があった結果、承認されました。承認された要因は大きく二つあって、一つは社長の大きなバックアップがありました。プロボノ活動を無事にキックオフするにあたり、非常に大きな支援になりました。もう一つは、丁寧に意見をヒアリングし、合意形成を丁寧に行うことです。時に、描いていたプロボノの定義と異なる意見が出てきましたが、一つ一つ、丁寧に調整を図り、最終的には社長のバックアップのもと、うまくスタートさせることができました。
コーポレート・ディビジョン・パートナーシップ〜ランディ・マーティン氏
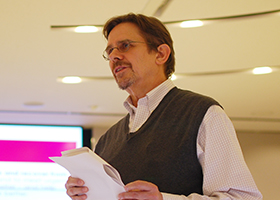
マーシー・コーは、アフリカ、南アジア、中東における人道支援に関わってきました。2011年の東日本大震災をきっかけにピースウィンジャパンとともに日本での活動を始められたそうです。
現在では40カ国での支援活動を展開。スタッフが世界に3,500名、95%が現地で採用したスタッフです。受益者は1,900万人に及びます。
資金は政府機関、企業からの寄付、一般社会からの寄付で成り立っています。
活動内容は大きく分けてふたつ。ひとつは緊急支援です。紛争、災害などの緊急支援に対応する活動です。もうひとつは長期的視野を持った開発・発展に関わっています。緊急支援でその国に入り、すぐ抜けるのではなく、その国の経済発展をどのように盛り返すかに関わっています。
日本でも緊急支援から外れた後は、現在まで長期的視野を持った発展を考えられてきました。日本の復興のために、約15億円を集め、ピースウィンズ・ジャパン以外とも協力し進められています。開発・発展というフェイズを考えた時に、どう関わっていくか非常に重要だと考え、信頼と理解を得た上で、さまざまな団体とパートナーシップを組み、フェイズの組み立てを行われています。
NGOと企業のパートナーシップ事例は多くあります。水に関連する施設・設備を提供している多国籍企業のミッションは、水に関して何でも解決しよう。マーシー・コーでも、発展に必要不可欠な水がミッションになっているので、良いフェイズを組むことができたそうです。
パートナーシップを組むにあたって、企業側からNGOを見る観点として重要なのは、透明性です。透明性があり、それが信頼に足るかどうか、注意して見なければいけません。NGO側はそれに答える形で、目的は何なのか、そこから得られるものはなんなのか、それらをクリアにして透明性をはかることが重要だそうです。
コミュニケーションと信頼も、もちろん重要です。トップ同士の会談だけではなし得ないことも、中間経営層同士のコミュニケーションでなら、なし得るケースがあり、そこには長い時間をかけた議論が必要だと考えられています。企業からは提案書を書いてくれと言われることが多いそうですが、お互いが何を求め、何を大切にしているかが先で、提案書は最後。パートナーシップを組むには、お互いの価値観を合わせることが大切で、それには長い時間がかかると感じていると話されました。
企業から求められるものは色々ありますが、昨今では物を送りたい、企業からボランティアに人材を派遣したいというものがあります。しかし、これは気をつけなければいけません。現地のニーズと異なる可能性があるからです。適正性や、よい介入だったのかを考える必要があり、ニーズと違う物・人材を派遣してしまった場合、現地の発展を阻害する要因にもなり得ます。もちろん、物的支援、ボランティアが助けになるケースは非常に多くありますが、お互いメリットがあるのか感じなければいけないそうです。
CSVの観点も重要です。さまざまな言葉の定義がインターネットなどで出回っていて、その中のひとつとして、興味関心をお互いがシェアするという意味もあります。シェアすることによって、プロジェクトを持続性のあるものにすることができると考えられています。
企業とだけパートナーシップを組む訳ではなく、NGO同士で組み、活動も行います。日本での活動はピースウィンズ・ジャパンをはじめ、日本のNGOを通しての活動です。ピースウィンズ・ジャパンとは、日本だけでなく、他国でも共に活動されています。ピースウィンズ・ジャパンがマーシー・コーから5,000万円の支援金を受け、干ばつに悩む人々への支援もされました。 今後もパートナーシップを組み、さまざまな活動をされていく予定だと話されました。
質疑応答
・ 企業との対話の始め方はどのようにしているのですか?
ランディ氏:どのような関係性を普段持っているかにもよりますが、リサーチし、自発的に対話していきます。
・ 日本企業への期待はありますか?
ランディ氏:私は、現在日本にいる唯一のマーシー・コーのスタッフです。東北の支援を最後までやり遂げるため、日本のNGOの能力強化をはかるために、滞在しています。残念ながら我々は日本のNGOではないので、まずこれから日本の企業とは対話していきたいと考えています。
また、日本のNGOともより関係を強化していきたいと考えていて、マーシー・コーと共に世界中で事業を行っていくパートナーを求めています。日本のNGOは、パートナーシップを組まなければ、非常に小さな組織団体と言えます。何らかの助けが必要であると考えています。小さな団体のNGOでも、他の国に支援をしていきたいというNGOがありましたら、ぜひ教えていただきたいと思います。
CSV経営サロン
2011年からサロン形式でビジネスに関する様々なプログラムを提供。発足当初から小林光氏に座長を、2017年からは吉高まり氏に副座長をお願いし現在に至っています。
2015年度からは「CSV経営サロン」と題し、さまざまな分野からCSV経営に関する最新トレンドや取り組みを学び、 コミュニケーションの創出とネットワーク構築を促す場として取り組んでいます。
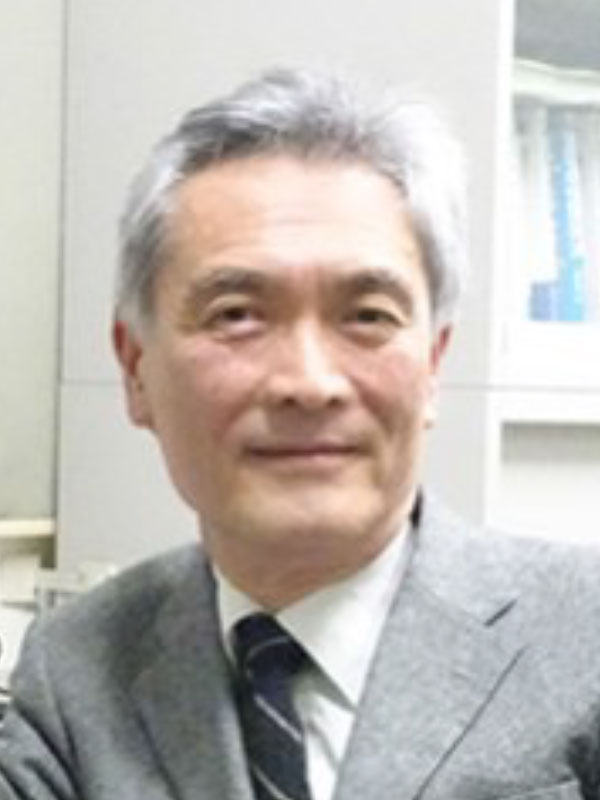
座長:小林光 氏
東京大学先端科学技術研究センター研究顧問 /
教養学部客員教授
慶應義塾大学経済学部卒(1973年)、東京大学大学院工学系研究科都市工学専攻修士、博士(2010・2013年、共に工学)。
1973年環境省(当時環境庁)入省。京都議定書交渉の担当課長、環境管理局長、地球環境局長、官房長、総合環境政策局長、2009年から2011年まで次官を務め退官。
慶應大学教授、米国イリノイ州にて派遣教授、2016年から現在まで東京大学客員教授。その他日本経済研究センター特任研究員、国立水俣病研究センター客員研究員、地方の環境審議会委員や脱炭素対策検討の委員等を歴任。
再生可能エネルギーを主要なエネルギー源とする資源循環型の社会を構築するために必要な価値観の転換、諸制度の整備などに取り組む。

副座長:吉高まり 氏
一般社団法人バーチュデザイン代表理事 /
東京大学客員教授/
慶慶應義塾大学総合政策学部特別招聘教授
明治大学法学部卒、米国ミシガン大学環境サステナビリティ大学院科学修士、慶應義塾大学大学院政策・メディア科博士(学術)。
IT企業、米国投資銀行等での勤務を経て2000年より現三菱UFJモルガン・スタンレー証券において気候変動関連の資金枠組みづくり、カーボンクレジット組成などに関与。政府、地方自治体、金融機関、事業会社などに向けて気候変動、GX、サステナブルファイナンスの領域について講演、アドバイスなどを提供し、新たにサステナビリティ経済の推進の実装を図る。
おすすめ情報
-

【レポート】SMBCと東近江市の事例から学ぶ、国内で進むネイチャーポジティブ✕金融の動向
CSV経営サロン2024年度第3回2024年11月25日(月)開催
-

【レポート】日本のネイチャーポジティブ×水をリードするサントリーグループの理念とは
CSV経営サロン 2024年度 第2回 2024年9月17日(火)開催
-

【大丸有シゼンノコパン】
大丸有の植物に江戸を「視(み)る」~人が利用してきた植物たち~
【緑地を探ろう!】2025年6月21日(土)10:00~12:00
-

【大丸有シゼンノコパン】
新緑のなかの生きものを「観(み)る」~生きもの調査にも挑戦‼~
【親子イベント/まちの生きもの】2025年5月17日(土)13:30~15:30
イベント
注目のワード
人気記事MORE
- 1
 【丸の内プラチナ大学】2024年度開講のご案内~第9期生募集中!~
【丸の内プラチナ大学】2024年度開講のご案内~第9期生募集中!~ - 2
 【大丸有シゼンノコパン】大手町から宇宙を「望る(みる)」ービルの隙間からみる、星空の先ー
【大丸有シゼンノコパン】大手町から宇宙を「望る(みる)」ービルの隙間からみる、星空の先ー - 3
 大丸有でつながる・ネイチャープログラム大丸有シゼンノコパン 冬
大丸有でつながる・ネイチャープログラム大丸有シゼンノコパン 冬 - 4
 【丸の内プラチナ大学】逆参勤交代コース 壱岐市フィールドワーク
【丸の内プラチナ大学】逆参勤交代コース 壱岐市フィールドワーク - 5
 【大丸有シゼンノコパン】【朝活】大丸有で芽吹きを「視る(みる)」ー春の兆しは枝先からー/まちの四季
【大丸有シゼンノコパン】【朝活】大丸有で芽吹きを「視る(みる)」ー春の兆しは枝先からー/まちの四季 - 6
 3×3Lab Future個人会員~2024年度(新規・継続会員)募集のお知らせ~
3×3Lab Future個人会員~2024年度(新規・継続会員)募集のお知らせ~ - 7
 【レポート】遊休資源が輝く未来へ 〜山形に学ぶ持続可能な地域づくりの挑戦〜
【レポート】遊休資源が輝く未来へ 〜山形に学ぶ持続可能な地域づくりの挑戦〜 - 8
 フェアウッド×家具~ものづくりを通じた自然や生態系への貢献~
フェアウッド×家具~ものづくりを通じた自然や生態系への貢献~ - 9
 指導経験ゼロから日本一のチームを作った「日本一オーラのない監督」が語る存在感と自己肯定感
指導経験ゼロから日本一のチームを作った「日本一オーラのない監督」が語る存在感と自己肯定感 - 10
 【大丸有フォトアーカイブ】第2回 みんなの写真展 2月21日~3月4日
【大丸有フォトアーカイブ】第2回 みんなの写真展 2月21日~3月4日

