

10月5日、CSV経営サロン第2回セミナーがエコッツェリアで開催されました。CSV経営サロンは、大丸有に籍を置く企業が一体となってCSVビジネス、オープンイノベーション創発プラットフォームを目指すもの。昨年までの環境経営サロンと、CSRイノベーションワーキンググループが発展的に統合され、企業のマネージャークラス、経営層を主な対象に開催されています。
サロンには、CSVビジネスのシーズを現場で見て学ぶフィールドワークと、座学とワークショップで各企業の持つリソースやニーズをあぶり出すセミナーの2種類があります。10月5日に開催されたのはセミナーの第2回目。ゲストスピーカーには、CSVビジネスの雄、キリン株式会社CSV推進部長の林田昌也氏を迎え、キリンが取り組んできたCSV事業のこれまでと現状、そしてこれからについて語っていただきました。また、後半は、小林光道場主による"模範稽古"と、"かかり稽古"という名のワークショップを行い、参加者の理解を深める作業を行っています。ファシリテーターは企業間フューチャーセンターの臼井清氏、塚本恭之氏が務めました。
- 続きを読む
- 世界の動きを解説
世界の動きを解説

会に先立ち、クレアンの水上武彦氏から、9月に開催されたワークショップイベント「NPO/NGOと企業間のパートナーシップによるCSV~The Power of CSV Partnerships~」のレポートがありました。FSG(Foundation Strategy Group)、クレアン、ジャパン・プラットフォーム、JPモルガンなどが主催するもので、タイトルの通り、CSVの連携において、NPO、NGOとのパートナーシップがテーマのイベント。当日は内外のさまざまなCSV事例の検証や分析を行い、近年の傾向や求められる要素の確認が行われたといいます。
水上氏はその概要を説明するとともに、「NPO、NGOと企業が連携するのがグローバル・スタンダードになっている」と話し、これからは「セクター内に留まることなく、ひろく企業、非営利セクター、行政と、より広くパートナーシップを結ぶことが求められ、それを実現する人材を"トライセクターリーダー"が重要になってくる」と、世界のCSVのトレンドを語りました。
復興支援がCSVの起点
 キリン絆プロジェクトのサイトより
キリン絆プロジェクトのサイトより
続くゲストスピーカーの講演で、キリンCSV推進部長の林田氏から、キリンが取り組むCSVの現状の紹介がありました。キリンは福島県産の梨を使った「氷結」などCSVに様々取り組んでおり、この日も東日本大震災の復興活動におけるCSV事業が主なテーマとなりました。「復旧」を主目的とした復興の第1フェイズでも多彩な活動に取り組んでいますが、この日の話題は林田氏が「農業・水産業復興支援の第2ステージ」と呼ぶ、一歩進んだ復興支援活動の話題が中心となりました。
 キリン・林田氏林田氏によると第2ステージは「経済的な自立を目指す復興支援」であり、"生産から食卓までの支援"をテーマに、「地域ブランド創生支援」「6次産業化推進と販路拡大」「担い手・リーダー育成支援」を3本柱にして進められています。支援先は、被災3県で、農業支援25地域、水産支援14地域(福島除く)に及びます。
キリン・林田氏林田氏によると第2ステージは「経済的な自立を目指す復興支援」であり、"生産から食卓までの支援"をテーマに、「地域ブランド創生支援」「6次産業化推進と販路拡大」「担い手・リーダー育成支援」を3本柱にして進められています。支援先は、被災3県で、農業支援25地域、水産支援14地域(福島除く)に及びます。
「気仙沼茶豆」「麓山高原豚(はやまこうげんとん)」といったプロダクトのブランド化もあれば、女川市で取り組んだ包括的な「AGAINおながわ」にまつわるプロジェクトもあります。こうした取り組みについて、林田氏は「CSVとして見た場合、飲料メーカーとして短期的に成果が見えるものではない。企業イメージ、お客様から見た企業の好意度や親近感からスタートするもの」と話します。
「女川のプロジェクトで、改めてまちづくりに取り組んでいる町のリーダーとネットワークができたことで、5年後、10年後まで視野に入れ、長期的な視点で成果を考えたい」とも話しています。リーダーや行政の方々とのつながりから町民・市民の方々へ企業の存在感が伝わっていけば、例えば町の飲食店で扱われるビールの種類にも好影響が出ると考えることもできるということです。「もちろん、それを端的な目標にするのではなく、人とつながることが、広い意味で様々な成果につながることを認識させ、巻き込む社員を増やしていきたい」と林田氏は話しています。
人のつながりが生むCSV
 TONO BEER EXPRIENECEのサイトより
TONO BEER EXPRIENECEのサイトより
人と人のつながりがさらに際立つのが、人材・リーダー育成事業の「農業トレーニングセンター 『パドロン ブランド育成、販路拡大』支援」と、そこから発展したプロジェクトの数々です。
再三触れてきたように、農業トレセンは丸の内朝大学発のプロジェクト。東北の若手生産者とのつながりを深め、東京のオフィスワーカーのリソースを農業復興支援に投入しようとしたもの。そのトレセンからさらにスピンアウトしたのが岩手県遠野市のパドロンプロジェクトです。遠野とキリンはホップの契約栽培で52年の歴史がありますが、生産者の高齢化による後継者不足が大きな課題となっています。遠野の若手生産者が着目していたスペイン産のビールに合う野菜「パドロン」の育成を取り組みの柱にし、遠野発の新たな作物として様々なアクションを行い、地元の生産者の育成にも寄与しました。パドロンプロジェクトでも販路拡大に取り組み、「例えば、キリンシティでメニューとして採用しました。ビールとの相性がとても良く、2014年には枝豆以上の売上となった」そうです。
このパドロンプロジェクトは、単にパドロンのブランド化にとどまらず、非常に多様な人材を巻き込んだネットワークでパドロンとホップを中心にした新しい遠野の町づくりに発展していきます。
プロジェクトは「遠野TKプロジェクト第2ステージ」へと進み、"Tono Beer Experience"をキーワードに、市民参加型ホップ収穫祭、ビアツーリズムの開発、シェフズツアーの仕組み化などを行っています。
推進のため必要な制度とルール
 キリンのコーポレイトサイトより
キリンのコーポレイトサイトより
林田氏によると、CSV事業推進のために、企業組織も大幅に改編されました。2013年に国内の飲料事業を一体化したキリン株式会社を設立し、「CSV本部」を設置。R&Dのセクションと並んで本部化しています。この2部署は「企業の価値を生む部署」と定義され、「ブランドを基軸とした経営」というキリンの企業経営の中核的な存在となっています。
そして、「企業理念」を「社会課題の解決=社会的価値」に照合し、「製品・サービス」「バリューチェーン」「地域社会」という3つのアプローチで、6つのテーマで取り組んでいる方針を説明。中でも6テーマのうち「人や社会のつながりの強化」「健康の増進」の2つは「キリンならではのテーマ」と位置付けて最も力を入れて取り組んでいます。
最後に「とはいえ、CSVの取り組みはまだまだ不十分。私自身長年マーケティングの仕事をしてきたが、CSVのテーマは単なる課題の解決ではなく、開発というか新たな創造があってはじめて意義があり、社会にも受け入れられる。様々な社会的課題はつきつめれば『世界をより良い場所にする』ということ。CSVをめぐる議論が激しくなることもあるが、そんなときは、その目的を思い出し、より良い地球を次世代に残すためにどうするか、キリンとして何ができかを考える。それがお客様のためであり、社会のためであり、企業のためになる」と締めくくりました。
CSVをどう理解するか

インプットトークの後は、恒例となった「稽古」という名のワークショップへ。最初に道場主の小林氏と林田氏による「模範稽古」としての対談が行われました。最初に小林道場主からは「世界的に見ても立派なCSVだが、社員、社内にはどう理解されているのか、認知度はどんなものか」という質問が出されました。キリンといえばCSV業界では著名ですが「実際には社内認識は6割程度がポジティブ。4割はニュートラルだが"自分ゴト化できない"というスタンス」なのだとか。「結局ひとりひとりの社員におちていくものであり、志と個々の体験に基づくもの。長い道のりだと思っている」と今後の展望を語ります。
また、一方でCSVの認知が高いならではの問題もあります。それは「それはCSVですか?と訊いてくるような"CSV原理主義"みたいな人間が出てくる」ことだという。林田氏は「だから社内ではCSVという言葉は使わない」。会場から「じゃあCSVをどう説明するのだ」と質問が上がると「社会課題の解決がお客様の幸せと同義だと。日々の幸せを阻害するものは何か、我々の商品や行動によって、その要因をなくしていくということを考えよう。ひいてはそれがキリンにも還ってくる。それがCSVなのだ。」など、細かな事例から、理念的なところまで、さまざまな質問・意見が飛び交う模範稽古となりました。
議論を深めるヒントに

その後、各テーブルで取り組む「かかり稽古」では、「CSV経営の視点でどう新プロジェクトを生み出すか」を前提に、「そのために必要なことは何か」「地域プロデューサーの立場から見て必要なもの、こだわるべきポイントは何か」といったテーマでダイアログを行いました。
基本的には企業のマネージメント層が多く参加するサロンのため、各テーブルでは、経営レイヤーでの考え方や判断についての意見が多く交わされたようでした。最後には、各テーブルの意見のシェアも行っています。
これまでのサロンとは異なり、参加者は必ず対話として意見を述べる場があります。アウトプットのためにはインプットされた内容をよりよく理解する必要があるため、それだけに参加者ひとりひとりが"持ち帰る"ことができたものも多かったようです。ワークショップの後の懇親会でも、理解をさらに深める意見を交わす姿が数多く見られました。
関連リンク
CSV経営サロン
2011年からサロン形式でビジネスに関する様々なプログラムを提供。発足当初から小林光氏に座長を、2017年からは吉高まり氏に副座長をお願いし現在に至っています。
2015年度からは「CSV経営サロン」と題し、さまざまな分野からCSV経営に関する最新トレンドや取り組みを学び、 コミュニケーションの創出とネットワーク構築を促す場として取り組んでいます。
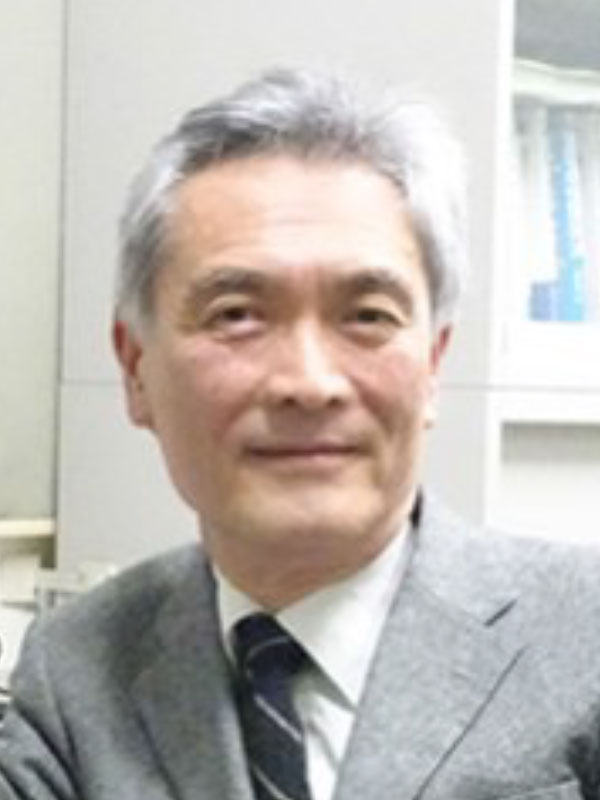
座長:小林光 氏
東京大学先端科学技術研究センター研究顧問 /
教養学部客員教授
慶應義塾大学経済学部卒(1973年)、東京大学大学院工学系研究科都市工学専攻修士、博士(2010・2013年、共に工学)。
1973年環境省(当時環境庁)入省。京都議定書交渉の担当課長、環境管理局長、地球環境局長、官房長、総合環境政策局長、2009年から2011年まで次官を務め退官。
慶應大学教授、米国イリノイ州にて派遣教授、2016年から現在まで東京大学客員教授。その他日本経済研究センター特任研究員、国立水俣病研究センター客員研究員、地方の環境審議会委員や脱炭素対策検討の委員等を歴任。
再生可能エネルギーを主要なエネルギー源とする資源循環型の社会を構築するために必要な価値観の転換、諸制度の整備などに取り組む。

副座長:吉高まり 氏
一般社団法人バーチュデザイン代表理事 /
東京大学客員教授/
慶慶應義塾大学総合政策学部特別招聘教授
明治大学法学部卒、米国ミシガン大学環境サステナビリティ大学院科学修士、慶應義塾大学大学院政策・メディア科博士(学術)。
IT企業、米国投資銀行等での勤務を経て2000年より現三菱UFJモルガン・スタンレー証券において気候変動関連の資金枠組みづくり、カーボンクレジット組成などに関与。政府、地方自治体、金融機関、事業会社などに向けて気候変動、GX、サステナブルファイナンスの領域について講演、アドバイスなどを提供し、新たにサステナビリティ経済の推進の実装を図る。
おすすめ情報
-

【レポート】SMBCと東近江市の事例から学ぶ、国内で進むネイチャーポジティブ✕金融の動向
CSV経営サロン2024年度第3回2024年11月25日(月)開催
-

【レポート】日本のネイチャーポジティブ×水をリードするサントリーグループの理念とは
CSV経営サロン 2024年度 第2回 2024年9月17日(火)開催
-

【大丸有シゼンノコパン】
大丸有の植物に江戸を「視(み)る」~人が利用してきた植物たち~
【緑地を探ろう!】2025年6月21日(土)10:00~12:00
-

【大丸有シゼンノコパン】
新緑のなかの生きものを「観(み)る」~生きもの調査にも挑戦‼~
【親子イベント/まちの生きもの】2025年5月17日(土)13:30~15:30
イベント
注目のワード
人気記事MORE
- 1
 【丸の内プラチナ大学】2024年度開講のご案内~第9期生募集中!~
【丸の内プラチナ大学】2024年度開講のご案内~第9期生募集中!~ - 2
 【大丸有シゼンノコパン】大手町から宇宙を「望る(みる)」ービルの隙間からみる、星空の先ー
【大丸有シゼンノコパン】大手町から宇宙を「望る(みる)」ービルの隙間からみる、星空の先ー - 3
 大丸有でつながる・ネイチャープログラム大丸有シゼンノコパン 冬
大丸有でつながる・ネイチャープログラム大丸有シゼンノコパン 冬 - 4
 【丸の内プラチナ大学】逆参勤交代コース 壱岐市フィールドワーク
【丸の内プラチナ大学】逆参勤交代コース 壱岐市フィールドワーク - 5
 【大丸有シゼンノコパン】【朝活】大丸有で芽吹きを「視る(みる)」ー春の兆しは枝先からー/まちの四季
【大丸有シゼンノコパン】【朝活】大丸有で芽吹きを「視る(みる)」ー春の兆しは枝先からー/まちの四季 - 6
 3×3Lab Future個人会員~2024年度(新規・継続会員)募集のお知らせ~
3×3Lab Future個人会員~2024年度(新規・継続会員)募集のお知らせ~ - 7
 【レポート】遊休資源が輝く未来へ 〜山形に学ぶ持続可能な地域づくりの挑戦〜
【レポート】遊休資源が輝く未来へ 〜山形に学ぶ持続可能な地域づくりの挑戦〜 - 8
 フェアウッド×家具~ものづくりを通じた自然や生態系への貢献~
フェアウッド×家具~ものづくりを通じた自然や生態系への貢献~ - 9
 指導経験ゼロから日本一のチームを作った「日本一オーラのない監督」が語る存在感と自己肯定感
指導経験ゼロから日本一のチームを作った「日本一オーラのない監督」が語る存在感と自己肯定感 - 10
 【大丸有フォトアーカイブ】第2回 みんなの写真展 2月21日~3月4日
【大丸有フォトアーカイブ】第2回 みんなの写真展 2月21日~3月4日

