

9,11,17
「丸の内プラチナ大学 「繋げる」観光コース。本講座は、町全体で旅行者をもてなし、「人」と「人」が繋がる新たな観光スタイルが世界各地で発生していることを鑑みながら、日本でも人・文化を「和える」ことで持続可能な地域観光を創造するコースです。講師は、インバウンド・地域創生等を含め地域のエコシステム創造において、省庁、自治体企業等への講演、コンサル支援を行っている吉田 淳一氏。年間90の講演を行っており、映像を駆使し世の中のサービス・技術トレンドを情報のシャワーのように伝える講演、通称"吉田劇場"で、非常にユニークでインタラクティブな講義を展開します。最終日であるDAY6には、宮崎県小林市から10人以上の地域関係者も講義に参加し、「Local to Local」を共通キーワードに様々な事例紹介が行われました。
Local to Local による異地域連携観光
第1回から第5回の授業の間には、 "Local to Local" というキーワードを挙げて地域観光への取り組みについて説明がなされてきました。しかし、一般の市民や地元の人たちにとって大事なことは、民間・企業・地元の人がフィールドの中で一緒になって化学反応を起こし、唯一無二の価値を創造するということだと、吉田氏は伝えます。さらにその中でも、一番大事なことは「人と人」。つまりは、地域と地域の人と人とを結びつけることで、幅と深さのあることができるようになる、と述べています。
「地方地域の団体だけでなく、実は行政・国の方でも、広域の『地域間連携』施策を行っています。47県には『よろず支援拠点』と呼ばれる施設がありまして、各県の地元の企業の立ち上げを"無料"で支援する取り組みです。たとえば北海道と沖縄が直接に繋がってノウハウの情報交換をする、といったことがいま実際に起きています。『よろず支援拠点』がハブとなり、県を跨いで相談事を受ける・指導するということが今、可能になっているのです。また、世界から訪れる訪日観光客たちからすれば、北海道と沖縄は日本地図上ではほぼ同じ位置のような地理感覚に感じられています。つまりは、北海道の特産品が沖縄で買えたり、またその逆ができることは、『日本に来れば良いものが買える』という付加価値として彼らの目には映るのです。それゆえ、日本の商材をいたる地域で見せていこう、という国策としての狙いがここにはあります」(吉田氏)

「和える」観光というスタイル
自分たちが持っている地域の唯一無二の商材を「地産地消」してもらうということを地域興しでは思い描きがちですが、是非「和える」というキーワードを覚えていって欲しい、と吉田氏は言います。ここで吉田氏が紹介したのが、江戸時代から160年の歴史がある京都の老舗料亭、「下鴨茶寮」についてのビデオクリップ。同店はくまモンをプロデュースした小山薫堂氏が2016年より経営を引き継ぎ代表を務めており、その小山さんが考える日本の魅力を表すキーワードが「和える」です。
" 日本では日本のことを「和」と言いますが、和という漢字は、「なごみ」であり、「やわらぎ」であり、「あえる」という読み方ができます。そして「和える」とは異なるものを組み合わせること。日本の歴史を振り返ればまさに和える歴史であったと小山さんは言います。たとえば中国から漢字が伝わると、それまで口頭で伝えていた日本語の発音をその音に似た漢字にあてるなどして"ひらがな"を生み出しました。そのほか食べ物にしても着るものにしても、外国から入ってきたものを日本らしく「和える」ことで自分たちのものにしてきたのです。 小山さんはそのコンセプトを京都の老舗料亭でも表現しようと考えました。たとえばそれは、"産地を一皿に和える料理"です。日本料理だからといって京都の地産地消にのみこだわるのではなく、あえて日本全国のおいしいものを一皿の中にぎゅっと詰め込む。例えば一つの小鉢には、栃木産のグリーンアスパラガス、熊本産のフルーツトマト、兵庫産の蛸、滋賀・琵琶湖産の稚鮎が使われています。京都に来た方が、京都で日本のほかの地域の魅力に気付くことが出来る。その地域についてもっと知りたくなる、行きたくなる。そういう想いを抱いてもらえる仕組みづくりとしての「和える」という考え方だと小山さんは言います "
「ほかにも東京・谷中にあります『澤の屋旅館』というのは、実はフロント側の方に観光情報を含めて全国の色々な情報をキュレートしています。ですから、ここに行けば様々な情報として触れる・ストーリーとしてわかる仕組み作りがされています。こういった仕組み作りがこれから非常に大事になってくるんじゃないかと思っています」(吉田氏)
ICTが可能にする「空間共有」の効能
吉田氏が所属するNTTグループを含め通信業界は、様々な通信・インターネットを生業とした企業体でありますが、0と1から構成される無機質なデータの中にも"人の気持ち"を入れるという試みが近年なされてきました。ICT技術による映像と音声を介して、離れた場所にいる人たちの想いをもつなげる──それが「気持ちを含む空間共有」になるのだと吉田氏は言います。「空間共有」の基本は、離れているもの同士が、互いの映像・音声をリアルタイムで見聞きしながらコミュニケーションを取ることです。こう言うと単なるTV会議のように聞こえるかもしれませんが、空間共有のポイントは、映像と音声が繋がっているだけにとどまらず、 "人の気持ち"が伝わるような工夫をうまく取り入れることで、通信をしている人同士のお互いの感じ方、距離感、協業・連携の度合いがまったく変わってくることだと言います。今回の講座では、そういった空間共有で「心」が通った次の2つの実例が紹介されました。

・「シンクダイナー」au by KDDI 東京と大阪、400kmの距離を1つのテーブルでつなぐ特別なレストランが 12月24日にだけオープン。 1日1組限定で、遠くはなれた二人が、 ひとつの空間の中で同じ時間を楽しむことができる "心と心をつなげる"インタラクティブなディナーサービスとして提供されます。リアルタイム通信に加えて、双子の店舗スタッフがそれぞれのお店に出てくるという小粋な仕掛けもあり、距離を隔てていても相手がまるですぐ傍にいるような気持ちをICTで共有できるという事例。 http://connect.kddi.com/sync/dinner/
・「つながる教室」NTT西日本 とある田舎町の小学校に、遠隔授業という形でこれまでにない教育環境を作ることで、子どもたちに新しい価値観の広がりを感じさせるというコンセプトのテレビCM。撮影は、リアルタイムで2つの地理的に離れた教室を実際につないで行われ、「地域の活性化」をテーマに生徒たちはスクリーンを通して向かい合い、活発な議論を交わしました。地元自慢や地域紹介など自由な意見がたくさん飛び出し、まるで同じ教室にいるかのような一体感ある雰囲気がICTで生まれた事例です。 https://www.ntt-west.co.jp/ad/company/tsunagaru.html
「『空間共有』は、私と3×3 Lab Futureを運営するエコッツェリア協会、そして前小林市長の肥後さんとで4年前から取り組んでいることです。一つの考え方として、各地域が観光DMOで映像配信などをやっていらっしゃいますが、映像配信するだけでは、なかなか人ってその地域に行こうとは思いづらいですよね。WEBコミュニケーションの仕組みを使って現地の人と直接会話をしてみて、そこで初めて深くて意義のある口コミになってくるんじゃないかと考えて、実証実験を続けてきています。いくつか事例をご紹介しますと、東京の参加者と小林市の農家民泊のお母さんたちとをライブ中継で繋いで『がね』と呼ばれる郷土料理を作ったり、農家の人が鶏を絞めて料理を作る様子と東京のシェフが料理を作る様子を中継したり、東京の人と小林の人とでライブ中継でのアイデアソンをやったり...。今はこういったことをやれるチャンスが広がっている時代なのです」(吉田氏)
さらに、吉田氏が取り組んだLocal to Localの取り組み実例として、青森とイタリアのトリノを「空間共有」で繋いだ事例が紹介されました。このプロジェクトは、「青森もトリノも少量多品種で生産しているがために大量輸出が難しいものの、非常に良いものを作っているのだから、それでお互いに化学反応を起こそう!」と、お互いに特産品食材を送り合い、各地でシェフが料理を作り、ライブ中継でフィードバックをするという趣旨の催しです。
・『Local to Local 青森×イタリアがつながる新しい地方創生のカタチ』 青森からは、りんご・柿・ニンニク・日本酒などが送られ、トリノからはワイン・チョコレート・パスタ・生ソーセージなどの特産品が相互に送り合われました。そしてイベント当日には、青森県八戸市のキッチンスペース、トリノのリストランテ、そして東京のイベント会場である3×3 Lab Futureの3会場が、インターネットを介して動画と音声の双方向のライブコミュニケーションでつながる環境が設けられました。地方の企業が海外展開を考える際にはロットの問題に直面しますが、お互いのニーズが合えば少量ロットでも交流ができることから、地方と地方を直接結び独自ルートを構築させて販路拡大を行うという狙いが本プロジェクトには込められています。 https://inforium.nttdata.com/event/aomori_italy.html
 青森・イタリア・東京の3元中継の様子
青森・イタリア・東京の3元中継の様子
最後は「小林市ナイト」×「鬼丸食堂」で体感
この日の最後は「小林市ナイト」ということで、"湧き水の街" 宮崎県・小林市に関わる人たちによる入れ替わり制の座談会。
 前小林市市長 肥後正弘氏(左上)、小林まちづくり会社 訪日外国人向け小林市観光推進担当 ロレーヌ・ロジェ氏(右上)、宮崎こばやし熱中小学校校長 原田英男氏(左下)、ダイワファーム 大窪和利氏(右下)
前小林市市長 肥後正弘氏(左上)、小林まちづくり会社 訪日外国人向け小林市観光推進担当 ロレーヌ・ロジェ氏(右上)、宮崎こばやし熱中小学校校長 原田英男氏(左下)、ダイワファーム 大窪和利氏(右下)
 「鬼丸食堂」鬼丸美穂氏(左上)
「鬼丸食堂」鬼丸美穂氏(左上)
丸の内プラチナ大学
あなたの「今後ありたい姿」「今すべきこと」とは?
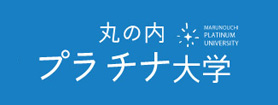
丸の内プラチナ大学では、ビジネスパーソンを対象としたキャリア講座を提供しています。講座を通じて創造性を高め、人とつながることで、組織での再活躍のほか、起業や地域・社会貢献など、受講生の様々な可能性を広げます。
おすすめ情報
-

【レポート】自分らしい自由な働き方や暮らしを求めて、実践者に学ぶ起業のリアル
【丸の内プラチナ大学】ライフシフト起業コースDay5 2024年12月23日(月)開催
-

【レポート】復興に向け奮闘する七尾市民、復興支援型逆参勤交代の可能性を考える
【丸の内プラチナ大学】逆参勤交代コース・石川県七尾市フィールドワーク 2024年12月6日(金)~8日(日)開催
-

【大丸有シゼンノコパン】
大丸有の植物に江戸を「視(み)る」~人が利用してきた植物たち~
【緑地を探ろう!】2025年6月21日(土)10:00~12:00
-

【大丸有シゼンノコパン】
新緑のなかの生きものを「観(み)る」~生きもの調査にも挑戦‼~
【親子イベント/まちの生きもの】2025年5月17日(土)13:30~15:30
イベント
注目のワード
人気記事MORE
- 1
 【丸の内プラチナ大学】2024年度開講のご案内~第9期生募集中!~
【丸の内プラチナ大学】2024年度開講のご案内~第9期生募集中!~ - 2
 【大丸有シゼンノコパン】大手町から宇宙を「望る(みる)」ービルの隙間からみる、星空の先ー
【大丸有シゼンノコパン】大手町から宇宙を「望る(みる)」ービルの隙間からみる、星空の先ー - 3
 大丸有でつながる・ネイチャープログラム大丸有シゼンノコパン 冬
大丸有でつながる・ネイチャープログラム大丸有シゼンノコパン 冬 - 4
 【丸の内プラチナ大学】逆参勤交代コース 壱岐市フィールドワーク
【丸の内プラチナ大学】逆参勤交代コース 壱岐市フィールドワーク - 5
 【大丸有シゼンノコパン】【朝活】大丸有で芽吹きを「視る(みる)」ー春の兆しは枝先からー/まちの四季
【大丸有シゼンノコパン】【朝活】大丸有で芽吹きを「視る(みる)」ー春の兆しは枝先からー/まちの四季 - 6
 3×3Lab Future個人会員~2024年度(新規・継続会員)募集のお知らせ~
3×3Lab Future個人会員~2024年度(新規・継続会員)募集のお知らせ~ - 7
 【レポート】遊休資源が輝く未来へ 〜山形に学ぶ持続可能な地域づくりの挑戦〜
【レポート】遊休資源が輝く未来へ 〜山形に学ぶ持続可能な地域づくりの挑戦〜 - 8
 フェアウッド×家具~ものづくりを通じた自然や生態系への貢献~
フェアウッド×家具~ものづくりを通じた自然や生態系への貢献~ - 9
 指導経験ゼロから日本一のチームを作った「日本一オーラのない監督」が語る存在感と自己肯定感
指導経験ゼロから日本一のチームを作った「日本一オーラのない監督」が語る存在感と自己肯定感 - 10
 【大丸有フォトアーカイブ】第2回 みんなの写真展 2月21日~3月4日
【大丸有フォトアーカイブ】第2回 みんなの写真展 2月21日~3月4日

