

開講にあたって
丸の内プラチナ大学がいよいよ開講しました。
"プレ講座"ですが内容は本番以上に充実しています。「地域デザインコース」「農業ビジネスコース」「CSV実践コース」の3コースに加え、共通講座を3回開催。計12講座が開催されることになります。
この日は共通講座の第1回目(DAY1)。最初にエコッツェリア協会・田口氏から講座を担当する講師陣の紹介があり、続いて、株式会社三菱総合研究所(以下、三菱総研)の松田智生氏のショートプレゼン。松田氏は改めて、シニアの活躍が求められていることやセカンドキャリアにとって必要な事柄が示され、いよいよプレ講座の本格開講です。
- 続きを読む
- 小宮山氏「プラチナ社会」を熱く語る
小宮山氏「プラチナ社会」を熱く語る

基調講演は、松田氏が所属する三菱総研の小宮山宏理事長。東京大学の総長を経て三菱総研の理事長に就任。"プラチナ社会"の提唱者としても知られ、次世代の社会のあり方を広く模索し、提唱し続けています。今回の基調講演は「アクティブシニアが牽引するプラチナ社会」と題し、歴史の中から見えてくる日本・日本人像、そこから立ち現れてくる未来の社会像について語りました。
 三菱総研・小宮山宏理事長
小宮山氏が示したキーワードは3つあります。
三菱総研・小宮山宏理事長
小宮山氏が示したキーワードは3つあります。
・日本人の誇り
・量的飽和
・寿命の飽和
いずれも小宮氏らが提唱するプラチナ社会につながる現在を考える上で重要なキーワードです。かつて、植民地開発に躍起になっていた西欧列強と出会った日本は、植民地にされず、明治維新による新たな政治体制を築き、産業革命を成し遂げました。この産業革命を行えたかどうかが現在、先進国に数えられる国になるかどうかの岐路だったと小宮山氏は指摘します。さらに、先進国への道を歩み出すことができたのは、江戸時代の寺子屋に代表される日本の教育水準の高さにあったと続けました。このことは、「日本人は誇りにしていい」と小宮山氏。
また、1970年代のオイルショックも大きな危機でしたが、その危機対しても日本人は、徹底した技術革新を行い、力強く乗り越えてきたことを紹介しました。
原油の高騰は、原材料を持たずに工業立国を成し遂げた日本にとって、産業界だけでなく国としても死活問題でした。しかし、「日本は屈しなかった。企業は徹底した省エネを実現し、新しい日本独自のものづくり文化の創成を成し遂げた。これも誇りにしていい」と小宮山氏は強く指摘しました。今、環境問題の先進的課題解決国としてドイツの名が挙がっているが、日本はすでに1970年代から取り組んで実績を重ねてきていること――このことは、他国に範をとる以前に誇りに思っていい。小宮山氏の指摘はいずれも、参加者だけでなく日本人に誇りを取り戻させてくれるものでした。
そして、産業革命を成し遂げた国は今、先進国として新たな課題に直面していると言います。その背景には、かつて経済成長で一致していた国民共通の目的がなくなったことがあります。たしかに、白物家電を手に入れて文化的な生活を送ることが庶民の願いでしたが、今、家庭内には高性能の家電品があふれています。車も多くの人が手に入れました。これを小宮山氏は「量的飽和」と称しました。さらに日本人は高寿命という、世界中でも特異な高齢化社会に向かって邁進していることも指摘。明治維新の頃の平均寿命は31歳。それが今、男性の平均寿命が80歳を超え、女性は90歳に近づこうとしているのが日本の高齢化の現状。これを小宮山氏は「寿命の飽和」と呼びました。
「私たちは"自由"になった」
「量的飽和」「寿命の飽和」という言い方はネガティブに過ぎるかもしれません。小宮山氏は、これをポジティブに捉えれば「我々はより自由になったということ」と説明します。量的飽和とは、食べるものに困らない、日々の生活に不足がないということ。それは「死にたくない」という根源的な欲求を満たしているということで、長寿命化によって、我々は、より長く、より良い人生を歩めるようになった。それが「人生の質」を求める「プラチナ社会」なのだと小宮山氏は定義します。
そして、「発想を豊かにすれば、もっと自由になれる」とも指摘。例えば、少資源国という認識も発想を変え、エネルギー消費は減っていること、都市にある資源の再利用を行えば資源を自国で賄うことができる。自由発想からは「壊すものの中に必要なもの(資源)がある」という工学系出身の小宮山氏ならではの発想も紹介しました。そうなれば、資源自給国家を目指すことも可能。これは決して夢物語ではありません。このような自由発想の先に、輝く未来、「プラチナ社会」が実現すると小宮山氏は熱く語りました。
キャリアデザインワークショップ(前半)――キャリアデザインは振り返りから

小宮山氏の基調講演を受けて実施されたワークショップ。講師を務めたのは、Life Creator Laboratory代表の輿石範子氏と株式会社キュムラス・インスティチュート代表取締役の岩井秀樹氏。輿石氏は能力開発やキャリア支援に携わり、岩井氏は東北復興や地域創成を実際に促進しているフィールドワーカーの実践者。両氏ともキャリアデザインに精通したプロフェッショナルです。
この日、両氏が示したのはA3サイズの1枚の記入シート。「社会的視点」「個人の視点(過去・現在)」、「個人の視点(未来)」の3つの記入欄があり、小宮山氏の講演を踏まえ、社会の動向と個人のアクションが関連付けられるようになっています。個人のキャリアの"棚卸し"という目的もあるでしょう。
その上で求められるのは「柔らかさ」。質の高い社会の実現に向かうには何が必要か。そこには、「やわらかな創造性が求められる」と輿石氏。このワークでは、それぞれが記入する個人ワークと、参加者同士のシェアとダイアログ(対話)が行われています。
そして、ここで行った振り返りは、キャリアデザインワークショップの「後半」につながっていきます。後半ではコミュニケーションの活性に向けた講義が行われますが、今回のワークでは、参加者のコミュニケーション能力の課題も浮き彫りになってくるようでした。
 輿石氏輿石氏は最後に、「やりたいことを記入したシートは目に見えるところに置いておいてほしい」と参加者へ話しました。言語化や文字化した「やりたいこと」は印象に残り、脳が覚えてくれるのです。これまでセカンドキャリアを正しく踏み出し、成功するためには踏み出す一歩手前での「準備期間」の必要性が繰り返し述べられてきましたが、まさに、その準備期間のマインドセットが、今回の講座だったのかもしれません。
輿石氏輿石氏は最後に、「やりたいことを記入したシートは目に見えるところに置いておいてほしい」と参加者へ話しました。言語化や文字化した「やりたいこと」は印象に残り、脳が覚えてくれるのです。これまでセカンドキャリアを正しく踏み出し、成功するためには踏み出す一歩手前での「準備期間」の必要性が繰り返し述べられてきましたが、まさに、その準備期間のマインドセットが、今回の講座だったのかもしれません。
まとめ――より実践的な内容のプレ講座に
これまで丸の内プラチナ大学は、来年度の本格開校を目指して、講座内容の立案・検証、自主ゼミナールなどを試みてきました。そうした試みの上に立って開講された今回のプレ講座ですが、これからの各コースではフィールドワークなども含まれており、より実践的に組み立てられています。
今回はプレ講座の第1回(DAY1)で、3つのコースそれぞれにつながる基礎講座です。 岩井氏によると、各コースの参加者の半数以上が、初めて丸の内プラチナ大学に参加する人とのこと。セカンドキャリアのスタートには準備期間が必要であることは再三言われてきたことですが、この前後半2回の基礎講座で、しっかりとマインドセットを行うことができそうです。次回のキャリアデザインワークの後半講座では、より実践的なコミュニケーション、合意形成のあらましなどを学ぶとのことで、今から開催が楽しみです。
関連リンク
丸の内プラチナ大学
あなたの「今後ありたい姿」「今すべきこと」とは?
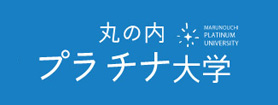
丸の内プラチナ大学では、ビジネスパーソンを対象としたキャリア講座を提供しています。講座を通じて創造性を高め、人とつながることで、組織での再活躍のほか、起業や地域・社会貢献など、受講生の様々な可能性を広げます。
おすすめ情報
-

【レポート】自分らしい自由な働き方や暮らしを求めて、実践者に学ぶ起業のリアル
【丸の内プラチナ大学】ライフシフト起業コースDay5 2024年12月23日(月)開催
-

【レポート】復興に向け奮闘する七尾市民、復興支援型逆参勤交代の可能性を考える
【丸の内プラチナ大学】逆参勤交代コース・石川県七尾市フィールドワーク 2024年12月6日(金)~8日(日)開催
-

【大丸有シゼンノコパン】
大丸有の植物に江戸を「視(み)る」~人が利用してきた植物たち~
【緑地を探ろう!】2025年6月21日(土)10:00~12:00
-

【大丸有シゼンノコパン】
新緑のなかの生きものを「観(み)る」~生きもの調査にも挑戦‼~
【親子イベント/まちの生きもの】2025年5月17日(土)13:30~15:30
イベント
注目のワード
人気記事MORE
- 1
 【丸の内プラチナ大学】2024年度開講のご案内~第9期生募集中!~
【丸の内プラチナ大学】2024年度開講のご案内~第9期生募集中!~ - 2
 【大丸有シゼンノコパン】大手町から宇宙を「望る(みる)」ービルの隙間からみる、星空の先ー
【大丸有シゼンノコパン】大手町から宇宙を「望る(みる)」ービルの隙間からみる、星空の先ー - 3
 大丸有でつながる・ネイチャープログラム大丸有シゼンノコパン 冬
大丸有でつながる・ネイチャープログラム大丸有シゼンノコパン 冬 - 4
 【丸の内プラチナ大学】逆参勤交代コース 壱岐市フィールドワーク
【丸の内プラチナ大学】逆参勤交代コース 壱岐市フィールドワーク - 5
 【大丸有シゼンノコパン】【朝活】大丸有で芽吹きを「視る(みる)」ー春の兆しは枝先からー/まちの四季
【大丸有シゼンノコパン】【朝活】大丸有で芽吹きを「視る(みる)」ー春の兆しは枝先からー/まちの四季 - 6
 3×3Lab Future個人会員~2024年度(新規・継続会員)募集のお知らせ~
3×3Lab Future個人会員~2024年度(新規・継続会員)募集のお知らせ~ - 7
 【レポート】遊休資源が輝く未来へ 〜山形に学ぶ持続可能な地域づくりの挑戦〜
【レポート】遊休資源が輝く未来へ 〜山形に学ぶ持続可能な地域づくりの挑戦〜 - 8
 フェアウッド×家具~ものづくりを通じた自然や生態系への貢献~
フェアウッド×家具~ものづくりを通じた自然や生態系への貢献~ - 9
 指導経験ゼロから日本一のチームを作った「日本一オーラのない監督」が語る存在感と自己肯定感
指導経験ゼロから日本一のチームを作った「日本一オーラのない監督」が語る存在感と自己肯定感 - 10
 【大丸有フォトアーカイブ】第2回 みんなの写真展 2月21日~3月4日
【大丸有フォトアーカイブ】第2回 みんなの写真展 2月21日~3月4日

