

快晴の伊豆熱川でフィールドワーク
前日までは雨、翌日からは再び気候が崩れるという谷間の日、伊豆熱川は好天に恵まれました。都内から伊豆へ向かう電車の車窓からは遠く、白い冠雪をいただく富士の山容が望まれました。農業ビジネスコースのフィールドワークは、この好天だけで成功が約束された感がありました。
JR東海道線と伊豆急線を乗り継ぎ伊豆熱川駅へ。ホームに降り立つとすぐ、温泉の香りが鼻腔をくすぐってきます。駅のすぐ近くに源泉井戸が見え、白く蒸気が沸き立っていました
丸鉄園は伊豆熱川駅の北側、伊豆高原につながる山塊の南斜面に位置しています。寂しい町中の道を抜け、狭い山道を登った先に森。その入口に丸鉄園の事務所が見えました。いよいよ農業ビジネスコースのフィールドワーク講習の始まりです。
実践フィールドワーク=丸鉄園モデルに接して

会場へ向かう前、講師の中村氏は、きょうのフィールドワークの位置づけを次のように語っています。「"生"の地域資源に触れて、その活用を考えてほしい。それに加えて、丸鉄園にひそむ課題などに気づいて、解決するためのアイデアなども出してほしい」。
さらに中村氏は、今後の農業ビジネスのビジョンを"プラチナファーム"として展開していくことも視野に入れ、丸鉄園をそのモデルケースにしたいと考えているようでした。
さて、その丸鉄園。もともとは無農薬みかん栽培をメインに、10年ほど前から観光農園を行っています。この日、園に到着したのは12時半あたり。ちょうど空腹を感じる時間帯ですが、最初の課題は「釣り」。みかん園と釣りでは、少々ミスマッチな感を否めませんが、園内に湧く湧水は活用資源の1つ。清涼な湧水では、健康なニジマスやイワナが育つのだそうです。

丸鉄園には釣り池が2つあり、上の池にイワナ、下の池にニジマスが放たれています。参加者にはここで試練が課せられました。昼食用のイワナとニジマスそれぞれ1匹ずつを釣るという難問......っ! 参加者の多くは釣り経験に乏しく、とくに渓流の釣りは初めてという人がほとんどでした。しかし、餌の付け方や当たりの見方など簡単な説明を受けて釣り始めるとすぐ、歓声が沸きました。ニジマス池に入った人たちの立てる竿の先、釣り糸に銀鱗が光っていました。神経質で釣りにくいと説明のあったイワナ池のほうでも歓声が続きました。
昼食用とはいえ、参加者はただ釣りに興じているわけではありません。目的は農業ビジネスコースのキーワードに挙げられている「地域資源」に触れることです。綺麗な湧水や池の立地、斜面の道の両脇を覆うクマザサなど丸鉄園の資源は豊富です。これらの資源に触れ、気づきを得て、その活用のアイデアへ結びつけることが本来の目的です。
さっそく触れた丸鉄園の資源の優位性は、昼食のときに明らかになります。それは、イワナとニジマスに川魚特有の臭いがないことでした。
釣り上げたイワナやニジマスのサイズはいずれも、おおよそ20センチ前後。イワナのほうがやや小ぶりという感じでしょうか。イワナは塩焼きで、ニジマスは唐揚げで食することになりましたが、ここで両魚種ともに川魚特有の臭みがないことに気付きます。参加者の間からも「臭みがまったくない」と驚きの声がありました。いずれも渓流魚なので中流域に棲むコイやフナなどの魚種より臭いはきつくないのですが、丸鉄園のイワナとニジマスは、かすかな臭みもなく、上質な肉味をじっくり味わうことができました。

これは池に注がれている湧水に理由がありました。たしかに、いい水なのでしょう。水面を通して遊泳するイワナやニジマスの魚体を見ても、傷1つ見当たりません。多くの釣り堀で見かけるヒレが白く溶け出したような病気の個体も見当たらなかったのは参加者も気づいたのではないでしょうか。この「湧水」は丸鉄園の大きな「資源」の1つです。
こうした地域の資源に直接触れることで、参加者のアイデアもより現実味を加え、ブラッシュアップされていくはずです。
興味津々の農業ロボットとみかん園散策
 ロボットを説明するはたらくロボット株式会社の蒲谷氏。右足についたピンク色のアタッチがセンサーに反応する
ロボットを説明するはたらくロボット株式会社の蒲谷氏。右足についたピンク色のアタッチがセンサーに反応する
昼食の少し前、釣ったイワナやニジマスの下ごしらえが行われている間に、まだ馴染みの薄い農業ロボットの説明を受けています。
丸鉄園入り口の広場に置かれた1台の荷運用の手押し車。一見ただの手押し車ですが、はたらくロボット株式会社の田口直樹氏らが開発した農業ロボット仕様の農具です。開発のコンセプトは、「重いものを自動的に運ぶ」。
取り付けられたセンサーは、農業現場に存在しない色彩を制御用に用いるなどの工夫がされています。坂なども取っ手を持っているだけで自走するなど、蒲谷氏は性能や仕様などを実演しながら説明、農業ロボットの展望や役割を紹介してくれました。見慣れない装置をつけた手押し車を取り囲んだ参加者の目は興味津々。参加者の多くが初めて見る農業ロボットに強く惹かれている様子でした。
農業ロボットの実力を堪能したあとは園内散策です。園長の太田氏の案内で、丸鉄園の主幹事業であるみかん園へ。南の海方面に下る斜面にミカンの木が並びます。丸鉄園では温州みかんだけでなく、レモンやオレンジ、伊予柑など他の柑橘類も多く育てています。なかには、日本に栽培法が伝わる前に取り組んだという歴史を感じさせるワシントン・ネーブルの古樹もあり、参加者は、その資源の豊かさに魅了されているようでした。
 ワシントンネールブルの古木の説明をする太田氏
ワシントンネールブルの古木の説明をする太田氏
みかん園では、参加者は実ったミカンの木の間で園主の太田氏からミカン栽培の手間や課題、丸鉄園で実践している無農薬栽培の説明を受けました。こだわりの栽培法やミカンの木の健康を測る尺度など興味深い内容に参加者の頷く回数も多くなっていました。話の中には無農薬で美味しいみかんを育てるための技術紹介もあり、それはそのまま承継問題と絡んで、絶やすのはもったいないという声も聞かれました。
太田氏の説明の後は、ミカンの採取、試食の時間です。参加者は各自ミカンの木に手を伸ばし、太田氏の説明にあった「実をつかんだら左右に動かすようにすると簡単に取れる」を実践します。この日、参加者が味わったのは早生種のミカンでした。
採れたてのジューシーなミカンで喉を潤した一行が次に向かったのは、イチゴ栽培のハウス。みかん園より少し斜面を下ったところにあり、ここでもこだわりの無農薬栽培が実践されていて、その美味しさは来園者に人気だということでした。

ワークショップではより現実的なアイデアや課題解決案が飛び出す
 ワーク終了後は乾杯して慰労。これも立派な現地視察のひとつ
ワーク終了後は乾杯して慰労。これも立派な現地視察のひとつ
みかん園、いちごハウスと見て、園内レストランに戻った参加者に待っているのは、ワークショップ。前回決められた4つのグループに分かれ、それぞれの「気づき」を書き出すところからワークは始まりました。この日はここまで、丸鉄園の持つさまざまな「資源」に触れてきました。園内の道を自分の足で歩いて感じた課題なども強く感じ取っているようでした。こうした「地域資源」や課題に直接触れたために、参加者の意見出しもより具体的になっています。気づきは用意されたポストイットに1枚1件で書き込まれて、たちまちグループのテーブルの上はポストイットで埋められていきます。
個人ワークのあとはそれぞれに気づきに対する意見交換が行われ、アイデアのシェア作業に移りました。気づきやアイデアは分類され、A3サイズの用紙に貼り付けられ、分類名が記入されます。同様の作業はこれまでのプレ講座の共通講座や農業ビジネスコースの前回の講習でも行っているので、ワークそのものはスムーズに進行していきます。やはり、実践に向けての学びは、「習うより慣れろ」ということでしょうか。慣れた分、参加者の思考もスムーズでアイデアはより具体的なものになってきている感じがしました。 最後はそれぞれのグループの代表者が発表を行います。
農業ビジネスの可能性に迫る
最後に、「いま丸鉄園のモデルは注目されている」と中村氏。丸鉄園を「プラチナファーム」として展開するということは、個人経営の限界を産・官・学・民が協働で打開し、これまで気づかなかったものも含めて地域資産を見直し、ビジネスに発展させる、その実例になるということ。この実践と検証を通して、協働スタイルはもちろん、事業承継の課題も解決されると期待できます。
実際の資源に触れた体験学習からは、中村氏の掲げた3つのキーワード「協働」「地域資源(地域資産)」「持続可能性」の大切さと意味がより鮮明に伝わってきました。農業ビジネスコースは次回、今回の体験をもとに「農業ビジネスの可能性」にさらに迫る講座を予定しています。
関連リンク
丸の内プラチナ大学
あなたの「今後ありたい姿」「今すべきこと」とは?
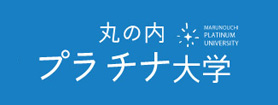
丸の内プラチナ大学では、ビジネスパーソンを対象としたキャリア講座を提供しています。講座を通じて創造性を高め、人とつながることで、組織での再活躍のほか、起業や地域・社会貢献など、受講生の様々な可能性を広げます。
おすすめ情報
-

【レポート】自分らしい自由な働き方や暮らしを求めて、実践者に学ぶ起業のリアル
【丸の内プラチナ大学】ライフシフト起業コースDay5 2024年12月23日(月)開催
-

【レポート】復興に向け奮闘する七尾市民、復興支援型逆参勤交代の可能性を考える
【丸の内プラチナ大学】逆参勤交代コース・石川県七尾市フィールドワーク 2024年12月6日(金)~8日(日)開催
-

【大丸有シゼンノコパン】
大丸有の植物に江戸を「視(み)る」~人が利用してきた植物たち~
【緑地を探ろう!】2025年6月21日(土)10:00~12:00
-

【大丸有シゼンノコパン】
新緑のなかの生きものを「観(み)る」~生きもの調査にも挑戦‼~
【親子イベント/まちの生きもの】2025年5月17日(土)13:30~15:30
イベント
注目のワード
人気記事MORE
- 1
 【丸の内プラチナ大学】2024年度開講のご案内~第9期生募集中!~
【丸の内プラチナ大学】2024年度開講のご案内~第9期生募集中!~ - 2
 【大丸有シゼンノコパン】大手町から宇宙を「望る(みる)」ービルの隙間からみる、星空の先ー
【大丸有シゼンノコパン】大手町から宇宙を「望る(みる)」ービルの隙間からみる、星空の先ー - 3
 大丸有でつながる・ネイチャープログラム大丸有シゼンノコパン 冬
大丸有でつながる・ネイチャープログラム大丸有シゼンノコパン 冬 - 4
 【丸の内プラチナ大学】逆参勤交代コース 壱岐市フィールドワーク
【丸の内プラチナ大学】逆参勤交代コース 壱岐市フィールドワーク - 5
 【大丸有シゼンノコパン】【朝活】大丸有で芽吹きを「視る(みる)」ー春の兆しは枝先からー/まちの四季
【大丸有シゼンノコパン】【朝活】大丸有で芽吹きを「視る(みる)」ー春の兆しは枝先からー/まちの四季 - 6
 3×3Lab Future個人会員~2024年度(新規・継続会員)募集のお知らせ~
3×3Lab Future個人会員~2024年度(新規・継続会員)募集のお知らせ~ - 7
 【レポート】遊休資源が輝く未来へ 〜山形に学ぶ持続可能な地域づくりの挑戦〜
【レポート】遊休資源が輝く未来へ 〜山形に学ぶ持続可能な地域づくりの挑戦〜 - 8
 フェアウッド×家具~ものづくりを通じた自然や生態系への貢献~
フェアウッド×家具~ものづくりを通じた自然や生態系への貢献~ - 9
 指導経験ゼロから日本一のチームを作った「日本一オーラのない監督」が語る存在感と自己肯定感
指導経験ゼロから日本一のチームを作った「日本一オーラのない監督」が語る存在感と自己肯定感 - 10
 【大丸有フォトアーカイブ】第2回 みんなの写真展 2月21日~3月4日
【大丸有フォトアーカイブ】第2回 みんなの写真展 2月21日~3月4日

