
イベント特別イベント・レポート
【レポート】AI時代に求められるコミュニティマネジャーの価値と役割
丸の内コミュマネ大学community frontline#02~AI×コミュニティの未来~ 2025年7月10日(木)開催

多様なつながりを育み、イノベーションの種を生み出していく共創型のコミュニティやコミュニティマネジャー(以下、コミュマネ)の在り方を探求するため、第2回丸の内コミュマネ大学が7月10日、東京・大手町の3×3Lab Futureで開催されました。丸の内コミュマネ大学は年4回開催予定で、今回は第2回目です。テーマは「AI×コミュニティの未来」。ゲスト講師は、企業やインキュベーションスペースを中心にコミュマネ育成に取り組む株式会社qutori CEOの加藤翼氏で、コミュニティにとってのAIの価値や付き合い方などについて学びました。
AI時代、コミュマネはコミュニティの価値観や倫理を設計する存在に
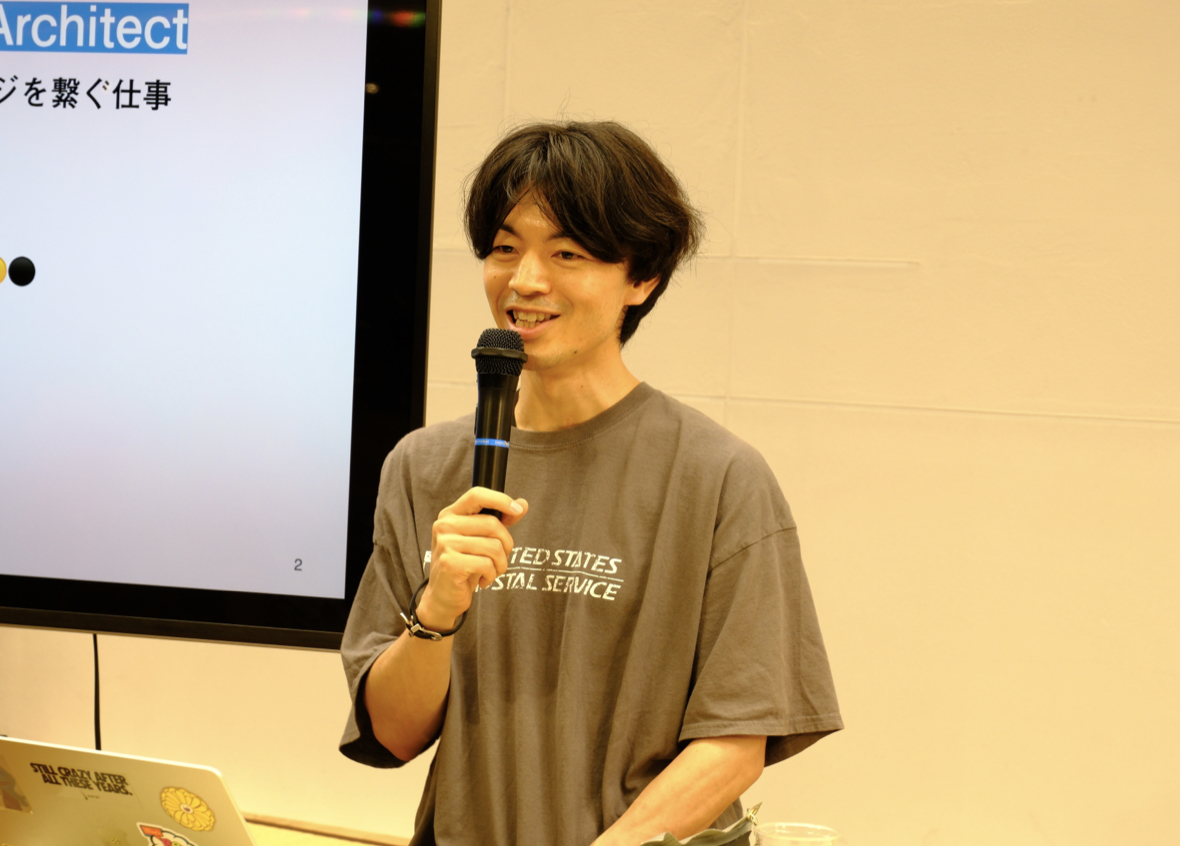 株式会社 qutoriのCEOであり、自身もコミュマネとして活躍する加藤氏
株式会社 qutoriのCEOであり、自身もコミュマネとして活躍する加藤氏
冒頭3×3Lab Futureや、食事でつながる場を提供する「shokujii」で発注したお弁当の紹介が行われた後、加藤氏が登壇しました。
同氏は自らも共創をテーマにしたコミュマネとして、多分野のコミュニティを横断する事業を手がけるほか、コミュニティマネジメントに特化したプロフェッショナルファーム「BUFFコミュニティマネジャーの学校」も運営しています。加藤氏は「ビジネスに限らず、皆さんの身近にも様々なコミュニティがある。より良い未来社会には、人の存在、人の可能性、人の倫理が必要で、すべての組織でコミュニティマネジメントが当たり前になる社会を目指している」と語りました。
 参加者は、食事でつながる場を提供する「shokujii」でお弁当を注文し、食事をしながら講演を聴講した
参加者は、食事でつながる場を提供する「shokujii」でお弁当を注文し、食事をしながら講演を聴講した
加藤氏は、まず概論としてコミュマネの心構え、コミュニティの定義や変遷などを語りました。加藤氏はコミュマネの心構えを「正解を出すよりも問いを出そう」、「ポジティブに受け入れよう」などと紹介した後、「コミュニティマネジメントでは、抽象概念が多く、属している企業や地域で使う言葉も変わる。それをみんなで共有するためには、メタファーや物語の力が有効」と、たとえやストーリーの活用も心構えとして挙げました。
またコミュニティの特性としてチームとの違いを紹介し、「サッカーで言えば、サポーターがコミュニティで、ピッチで戦っている選手がチーム。価値を共有しているコミュニティは多少サボっても目的を失わないが、目標に向かうチームはサボったら目的を達成できない」と話しました。
 会場のほとんどの席が埋るほどの盛況ぶり
会場のほとんどの席が埋るほどの盛況ぶり
加藤氏によれば、コミュニティという概念は、古くは牧草地などの共有財を分配・管理するための集団に端を発し、時代が進むにつれて生態系や地球全体を一つのコミュニティとするような広い視野へと発展してきました。インターネットの登場により、コミュニティはネットワーク化され、ハブを持たない自律分散モデルやホラクラシーにより、一人ひとりが意図を持って動く時代になり、今やAIの活用が始まっています。さらに現代では、コロナ禍で三密回避などの行動変容を促す潮流があったように、コミュニティはかつての「観察する対象」から「マネジメントする対象」へと変わってきているとも加藤氏は語っていました。
AI活用による4つの利点
概論の後、本題であるAIとコミュニティの関係に話題は移りました。加藤氏は、コミュマネにとってのAI活用の利点を4つ紹介しました。まずは、SNS投稿文のクオリティやトンマナの管理などコンテンツ作成や企画業務の効率化です。次にイベント運営の自動化と効率化で、加藤氏も企画作業のほか「イベント後のアンケート収集・分析などもAIに任せている」と語りました。3点目としては、メンバーとのコミュニケーションの円滑化で、コミュニティのガイドラインや資料をもとにメンバーや外部とのコミュニケーションを自動化することが可能になっています。そして最後に加藤氏はコミュニティ分析とインサイトの発見を挙げ、コミュニティの動向やメンバーの貢献度もAIが分析してくれる時代になっていると述べました。これらのメリットから加藤氏は「AIを使えば業務の設計を根本から見直すことができる。その結果、雑務を徹底的に減らし、コミュマネはメンバーとの対話時間を多く確保できるようになる」と話しました。
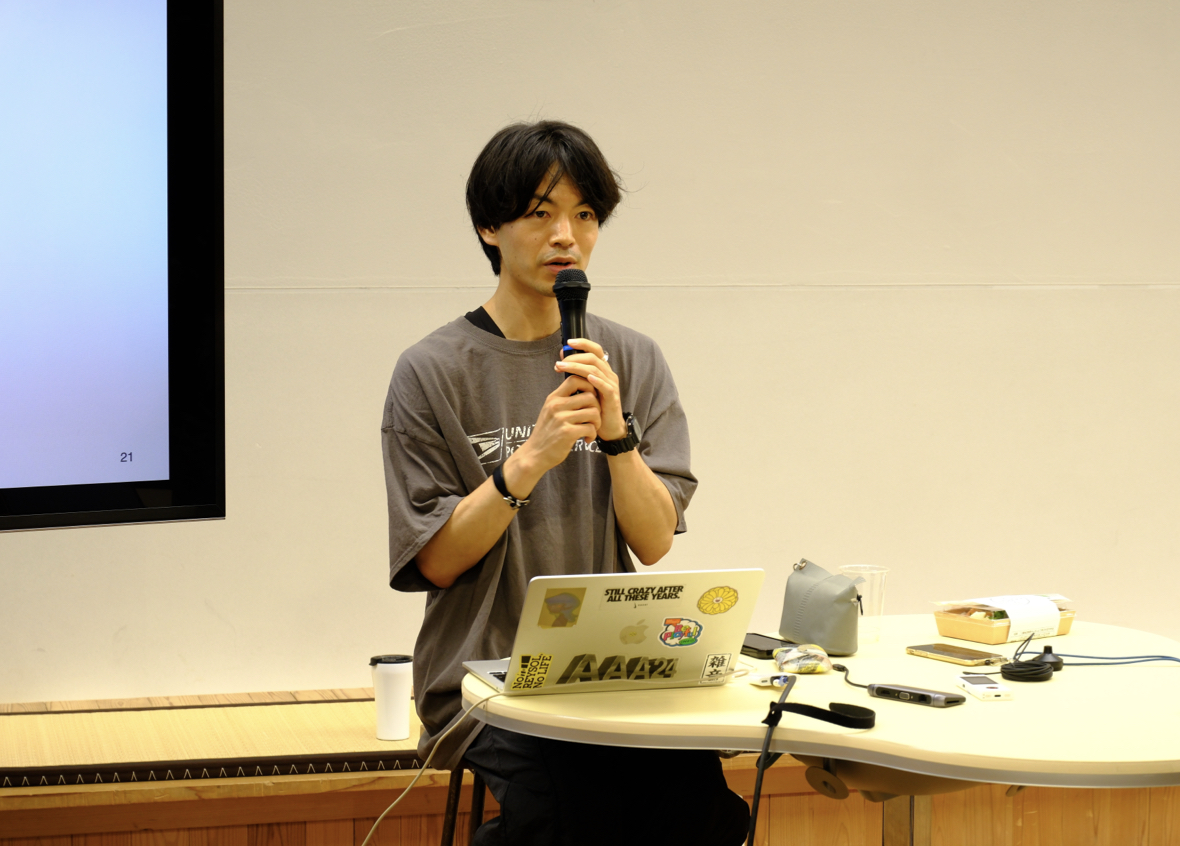 AIによってコミュマネはメンバーとの対話の時間が増えると加藤氏
AIによってコミュマネはメンバーとの対話の時間が増えると加藤氏
AI導入のインパクトを分析するため、加藤氏はカナダのメディア理論家マクルーハンのテトラッド分析を使ってさらに考察を加えます。テトラッド分析とは、メディアや技術が社会に与える影響を「強化」「時代遅れ」「回復」「反転」の4つの視点から捉える思考ツールです。
まずAIが増幅・強化するものについて、加藤氏は効率性とスケーラビリティを挙げ、「僕の知識の源泉をAIに全部読み込ませ、そのAIとメンバーが対話することで、僕が直接教えなくても多くのメンバーに学びを得てもらえる。またメンバー同士のマッチングなどもAIが自動で判定してくれ効率的」と具体例を挙げて説明しました。
AIによって時代遅れになっていくのはキュレーションや編集作業で、手動の価値は衰退すると言います。AIの特性上、受動的で感覚に強く訴えるホットなメディアは増える一方、受け手の補完や解釈が必要なクールなメディアは減少するだろうと予想しました。
AIによって回復していくものとしては目的志向の集団があり、「かつては友達になってから一緒に何をするか考えたが、これからは何を一緒にするかを決めて、集まった人たちと友達になるという目的志向の繋がりが増え、マナーより明示的なルールづくりが回復するのでは」と語りました。
そして反転では、AIが極限までいくとデジタル監視社会や、コミュニティ内の点数稼ぎを目的としたエンゲージメントファーム化のような未来も見えてくると分析していました。
このようなAIとコミュニティマネジメントの現在地や可能性を受けて、加藤氏は未来のコミュマネの役割が倫理設計者や調整役だと言います。「AIの導入は容易だが、なんとなく導入してしまうとAIが自動的に判断していくため、適切に判断されているかをコミュマネが追い切れなくなる。コミュマネは価値観や倫理観の枠組みを設計することが求められる。AIを導入するコミュマネはコミュニティの運営者から設計者になる必要がある」と講義を締めくくりました。
 加藤氏の講義を受け、感想や意見を出し合う参加者ら
加藤氏の講義を受け、感想や意見を出し合う参加者ら
加藤氏の講義を聞き終えた受講生らは、テーブルごとに感想や意見を出し合いました。例えば「AIは何でも効率化するが、効率化しないメリットもあるのでは」といった意見や、「ユーザーに迎合するAIには客観的で冷徹な判断ができないと思う」など、AI導入への疑問が出たほか、「AIによってエンゲージメントファーム化したら、それはもはやコミュニティではない」と、コミュニティの価値について改めて考えさせられたという声も上がりました。
AI時代のコミュニティにおける、人にしか果たせない役割とは
講義の後半戦では、加藤氏とともに3×3Lab Future館長の神田主税、3×3 Lab Future ネットワークコーディネーターの田邊 智哉子、ファシリテーターとして株式会社ファイアープレイスCEOの渡邉知氏も加わってクロストークが行われました。一部を抜粋してご紹介します。
 クロストークの登壇者たち(左から順に田邊、渡邉氏、加藤氏、神田)
クロストークの登壇者たち(左から順に田邊、渡邉氏、加藤氏、神田)
渡邉(敬称略、以下同):今回、コミュニティ×AIというテーマを選んだ理由は。
加藤:AIによってコミュマネはメンバーと話す時間が増え、存在価値が上がることを知ってもらいたかったからです。
神田:今日の話を聞いていると、非効率的で人間らしいところは、コミュマネの存在が依然として重要だと感じました。しかしAIがさらに進化するとそんな人間らしい部分も代替されていくのでしょうか。
加藤:AIは成功までに無数の失敗が必要で、コミュニティマネジメントでは失敗が繰り返されると実害が出てしまいます。いい塩梅に忖度できるのは人間の強みで、将来においてもコミュマネの価値だと思います。
田邊:AIマッチングの話題がありましたが、AIにあなたにはこの人が合うと言われてもあまり嬉しくないという気もします。コミュマネは五感をフルに使って相性の良さそうな人をつなげています。そのあたりはAIに負けられないと思っています。

渡邉:ここはAIではなく、人間がやりたいというところはありますか。
神田:コロナ禍でイベントやミーティングがオンラインになった時、なんとなく寂しさを感じました。その経験から、対面や雑談の場は大切だと感じています。対面で人と触れ合う場は3×3Lab Futureでは大事にしていきたいと思っています。
田邊:私の仕事はネットワークコーディネーターと言っています。単なるビジネスマッチングではなく、やわらかい繋がりを生み出したいと思っていて、そのためには皆さんのバックグラウンドからビジョンまで伺ったうえでマッチングしています。繋ぎの感性が問われるためAIには代われないと自負しています。

渡邉:コミュマネの仕事が運営から設計に変わっていくという話でしたが、「設計」の意味するところをもう少し説明してもらえますか。
加藤:やはり一番は、魂を込められる部分をどう作るかということだと思います。コミュニティメンバーが本気で熱中できること、自分の人生をかけてもいいと思えるような魂のこもった活動をつくれるかどうか。それこそが、広い意味での設計だと思います。
神田:僕もその部分は意識しています。3×3Lab Futureも社会課題解決を目標にしています。同じ想いを持ったコミュニティからプロジェクトを立ち上げ、社会課題解決につなげていくために、いま加藤さんが言われた設計の概念はとても大事だと共感します。
渡邉:コミュマネ大学では、これからの時代、コミュマネというスキルや役割は全ビジネスマンに必要だと考えています。加藤さんはどう思いますか。
加藤:全く同意見です。コミュマネはどの業界でも使えるマインドセットであり、世界の見方であり、コミュニティマネジメントも色んな人が多種多様に解釈して使ってくれればと思っています。
クロストークの最後には、会場の受講生からも質問を受け付けました。ある受講生から「AIを現実の人間のように良き相談相手に近づけるための工夫」について問われた加藤氏は「AIにも色んなキャラクターがある。多様なAIに同じ質問をしてみるといい。そうすると各AIの癖や個性が分かってくる。複数の友人を使い分けるようにAIを客観的に観察し、うまくパートナーとして付き合っていってほしい」と回答しました。
AIが進化し続ける今、コミュニティにおける人の役割や価値が改めて問われています。AIの活用で効率化を図りつつ、それによって得られた時間で人は何ができるのか、倫理や感性を持って人と人をつなぐ存在として、コミュニティマネジャーが果たすべき役割を考えることができた学びの場でした。
おすすめ情報
イベント
注目のワード
人気記事MORE
- 1
 丸の内プラチナ大学2025 逆参勤交代コース特別講座 飛騨ナイト
丸の内プラチナ大学2025 逆参勤交代コース特別講座 飛騨ナイト - 2
 【丸の内プラチナ大学】2025年度開講のご案内~第10期生募集中!~
【丸の内プラチナ大学】2025年度開講のご案内~第10期生募集中!~ - 3
 【大丸有シゼンノコパン】色彩豊かな冬の鳥を「観る(みる)」 ~極寒の今こそ絶好の"鳥"日和!~【まちの生きもの】
【大丸有シゼンノコパン】色彩豊かな冬の鳥を「観る(みる)」 ~極寒の今こそ絶好の"鳥"日和!~【まちの生きもの】 - 4
 大丸有でつながる・ネイチャープログラム大丸有シゼンノコパン 冬
大丸有でつながる・ネイチャープログラム大丸有シゼンノコパン 冬 - 5
 【大丸有シゼンノコパン】ビルや樹々の隙間に星空を「望る(みる)」 ~「すばる」や「月」はどこにある?~【まちの星座】
【大丸有シゼンノコパン】ビルや樹々の隙間に星空を「望る(みる)」 ~「すばる」や「月」はどこにある?~【まちの星座】 - 6
 【大丸有シゼンノコパン】都心の緑地に春の目覚めを「覗る(みる)」~生きものとの共生のヒントを探して~【まちの生きもの/親子・初心者の大人向け】
【大丸有シゼンノコパン】都心の緑地に春の目覚めを「覗る(みる)」~生きものとの共生のヒントを探して~【まちの生きもの/親子・初心者の大人向け】 - 7CSV経営サロン2025 第3回「資源循環の出口、有機性資源のアップサイクル」
- 8
 【レポート】関係資本の力を最大化する コミュニティデザインと持続的価値創造
【レポート】関係資本の力を最大化する コミュニティデザインと持続的価値創造 - 9
 3×3Lab Future個人会員~2025年度(新規・継続会員)募集のお知らせ~
3×3Lab Future個人会員~2025年度(新規・継続会員)募集のお知らせ~ - 10
 【丸の内プラチナ大学】逆参勤交代コース 高知県須崎市フィールドワーク
【丸の内プラチナ大学】逆参勤交代コース 高知県須崎市フィールドワーク





