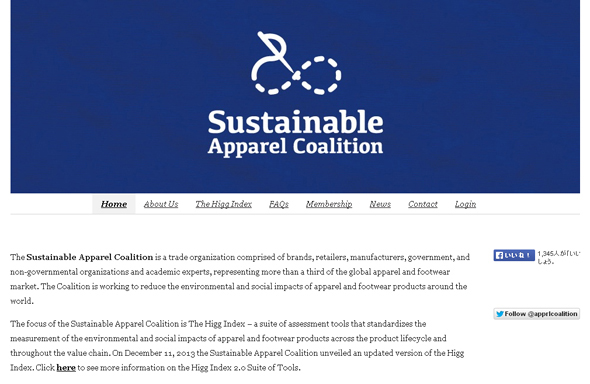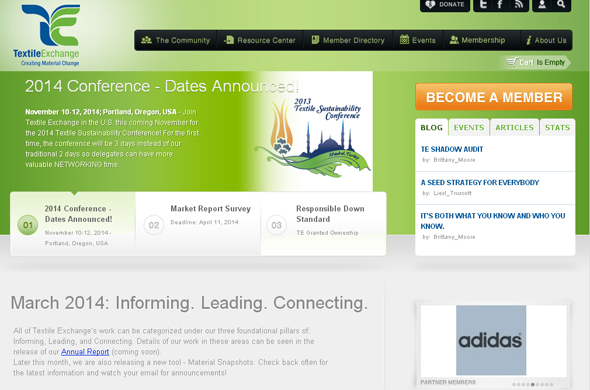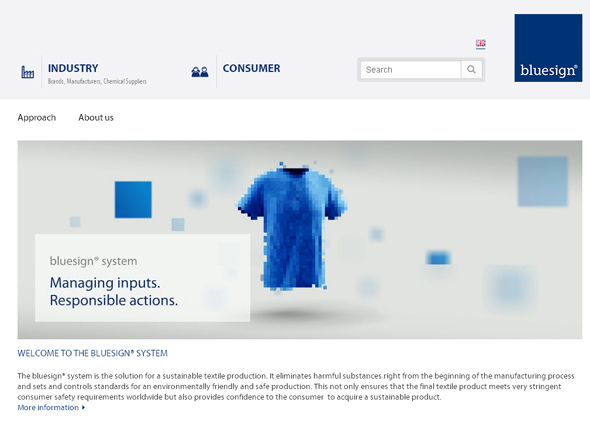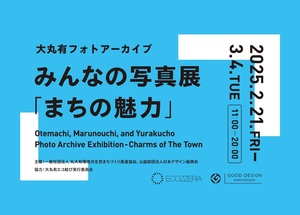アパレル業界が抱える問題と協働イニシアティブ
企業が果たすべき次世代の「責任」とは何か――。パタゴニアが2013年秋から2年計画で進めるキャンペーン「責任ある経済(レスポンシブル・エコノミー)」のシンポジウムが、3月20日、エコッツェリアで開催されました。
テーマは「環境・社会インパクト低減に向けたパートナーシップ」。
帝人フロンティア株式会社、興和株式会社、YKK株式会社の3社がゲスト企業として登場しました。いずれもパタゴニアと同じく、限りある資源のサステイナブルな利用法を目指し、次世代の経営・経済の形を模索しているアパレル関連企業です。早い段階からグローバルレベルの協働イニシアティブに参画しており、その取り組みは国内外で高く評価されています。今回は、各社の取り組みが紹介され、社会全体、業界全体が抱える構造的な問題を明らかにするとともに、企業間パートナーシップの可能性を探る充実した内容となりました。
司会は環境ジャーナリスト・翻訳家で幸せ経済社会研究所所長の枝廣淳子さんが務めました。
- 続きを読む
- アパレル業界の現状と課題とは
「こだわり」と「使命」を可視化する
冒頭、パタゴニア日本支社長・辻井隆行さんが基調講演を行いました。
 パタゴニア日本支社長 辻井隆行さんパタゴニアは「こだわり」と「使命」を持って活動しており「その両方が外に向かって見えるものでないといけない」と辻井社長は言います。パタゴニアでは、良い製品を作るというこだわりと、環境問題に対する使命として、1996年に全商品をオーガニックコットンに切り替えています。
パタゴニア日本支社長 辻井隆行さんパタゴニアは「こだわり」と「使命」を持って活動しており「その両方が外に向かって見えるものでないといけない」と辻井社長は言います。パタゴニアでは、良い製品を作るというこだわりと、環境問題に対する使命として、1996年に全商品をオーガニックコットンに切り替えています。
「綿花の耕作面積は全地球面積の2、3パーセントですが、地球上で使用される殺虫剤の25%、農薬の10%が綿花栽培で利用されているのです。それを知ったうえでも農薬を使用したコットンを使うのか?ということなんです」
また、2013年4月にダッカ(バングラディッシュ)で起きたビル崩壊事故に触れ、「安く縫製するために、4000台のミシンを違法に設置したために起きた事故。日本では大きく報道されませんが、1127名の死者を出した大惨事でした。1本750円という安いジーンズがどうやって作られ、マーケットに出ているのか。お金を使う側は考える必要があるのではないでしょうか」。そして、「クローゼットの中の服の何パーセントが、どこの誰が作ったのかが分かるようにするのがパタゴニアのチャレンジなのです」と語りました。
司会の枝廣氏は「食べ物は産地にこだわり、よく選ぶようになりましたが、着るものについて意識する人は少ない。選ぶときに、どういう選択軸があるのか、軸があることで、人間の行動はどう変わるのか。作る側で、どういった軸作りをしているのでしょうか」とゲスト・スピーカーに疑問を投げかけました。
グローバルな協働イニシアティブと日本企業
今回のテーマである「パートナーシップ」。ゲスト企業各社が参画するパートナーシップは、いずれも認証制度を伴っています。各社のプレゼンを引用しながら、どのようなものかを概観します。
●帝人フロンティア/繊維素材統括部・宮武龍大郎さん
=Sustainable Apparel Coalition(サスティナブル・アパレル・コーリション。SAC)
SACは2009年にパタゴニアとウォルマートが設立したもので、現在ではフットウェア、アパレルの売り上げの1/3に相当するメーカー、サプライヤーが参加しています。アパレル業界における持続可能性を評価するツール"Higg Index"を策定し、素材から製造、包装、輸送といったすべての工程での資源エネルギーの消費効率や汚染などの環境に与える負荷の低減を目指します。また、労働環境や人権なども評価項目に含まれています。
帝人フロンティアが参加しているのは「世界にどんな認証や指標があるか分からなかったのですが、SACの意識はとても高く、いずれ世界的な基準になるのではないかと思ったためでした。また、世界の潮流はどのように動いているのか、情報収集したいという思いもありました」。
●興和/「テネリータ」開発生産部品質管理課・稲垣貢哉さん
=テキスタイルエクスチェンジ(TE)
TEは、オーガニックコットンの利用拡大を目指して2002年に「オーガニック・エクスチェンジ」として発足(2010年に改称)。綿花・麻などの生産者から、テキスタイルのメーカー、流通業者など世界200社が加盟するプラットフォームです。主な事業は、オーガニックコットンの認証事業、農業教育、普及啓発イベント、情報提供の4つあると稲垣さんは説明します。
「2002年から始まった活動のおかげで2009年には加盟が20カ国になり、全綿に占めるオーガニックの割合が0.7%になり『1%を超えるのではないか』と大いに期待されたのですが、それ以降減少が続き、2013年には0.5%にまで低下しました」。しかし、「C&Aなどのメーカーで、オーガニックコットンの含有量が異なる廉価版の製品を開発販売が進んだために、オーガニックコットン市場の総売上は2001年の2億4000万ドルから、2012年の89億ドルに上昇しています」。
●YKK/CSR推進グループ・河西克哉さん
=ブルーサイン・スタンダード
YKKはアルミサッシなどの建材事業と、「年間85億本、220万キロ」というファスニング事業(ファスナー)を中核事業として1959年から海外展開を開始しています。「YKK精神」として、世界中どこでも同じ高い品質を目指すため、製造機械も自社製造する徹底ぶり。その一方で、「工程の健全性を担保するものがなかった」ため、ブルーサイン・スタンダードとのパートナーシップを結んだといいます。
「ブルーサインは、資源の生産性、消費者の安全性、排水、大気放出、職場環境の5項目で設定された目標達成を目指すもので、世界でもっとも厳しい基準のひとつです。また、"Input Stream management"というシステムがあり、原料から製品、そこから排出されるものすべてを監視・評価しています。ファブリックやテキスタイルでは、社内管理しているものだけでなく、サプライヤーから提供を受けているものも多いのですが、そのすべてをフォローしている企業はとても少ないと思います」
グローバルなパートナーシップの利点
 上から帝人フロンティア 宮武龍太郎さん、興和 稲垣貢哉さん、YKK 河西克哉さん後半は枝廣さんから質問を投げかける形でセッションが繰り広げられました。内容はさまざまなテーマに及びましたが興味深かったのは、「パートナーシップを提携するのはなぜか」という点と、企業・消費者含め「(認識が)広まらないのはなぜか」という点です。
上から帝人フロンティア 宮武龍太郎さん、興和 稲垣貢哉さん、YKK 河西克哉さん後半は枝廣さんから質問を投げかける形でセッションが繰り広げられました。内容はさまざまなテーマに及びましたが興味深かったのは、「パートナーシップを提携するのはなぜか」という点と、企業・消費者含め「(認識が)広まらないのはなぜか」という点です。
前者については、アパレル、テキスタイル産業の構造的な問題が大きく関わっているというのが共通した意見でした。
帝人フロンティア・宮武さんは「1社でできることは限られているから」と回答。「1社の取り組みが与える影響が及ぶ範囲は非常に狭い。外部のプラットフォームに乗せることで、影響が外にも広く広がっていくと思います」。YKKの河西さんは「自社だけで製品品質を高めていると言っても、特に海外の人には見えないし分かりにくい。グローバルに見て分かるようにしてあげることが大切」と指摘。また、「部材などを提供する場合、1社だけでやっても先方には聞いてもらえないことが多い。業者全体で取り組むことで、広く受け入れてもらえるようになる」と言います。
また、興和の稲垣さんは日本の分業制の多さも問題のひとつと指摘しています。 「日本は生産工程の多くが分業化されており、1社だけではやりきれない」。そして海外の事例に触れ、「たとえば環境負荷の低い染料や技術があればその内容を、メンバー全員がシェアします。日本ではそうした環境技術で他社との差異化を図ろうとしますが、海外ではその先の、たとえばデザインなどで勝負するのです」。
パタゴニア・辻井社長は、3つの理由を挙げています。ひとつは規模の問題。テクスタイル、ファッション業界の規模は大きく、1社ができるのはごくごく1部だということ。2つ目は「問題の複雑性にある」と指摘。「サプライチェーンはいっぱいある、ステークホルダーもいっぱいいる。関係している多くの人々が世界各地で物理的に離れていることも問題を複雑にしています」。そして3つ目が問題の本質が日々変化していくことだと言います。「1社だけでは何もできませんが、仲間となった企業が技術やノウハウを持ち寄ってレシピを作って普及すれば、オセロのように一気に黒を白に変えていくことができるのではないか」。
なぜ広まらないのか
 司会:枝廣淳子さん日本ではSAC、TE、ブルーサインに参画しているのは、まだまだ意識の高い一部の企業に限られています。なぜ企業側に広まらないのか。これについては帝人フロンティアの宮武さんの指摘がもっとも的を射ています。
司会:枝廣淳子さん日本ではSAC、TE、ブルーサインに参画しているのは、まだまだ意識の高い一部の企業に限られています。なぜ企業側に広まらないのか。これについては帝人フロンティアの宮武さんの指摘がもっとも的を射ています。
「国内企業の多くにとって、日本国内が大きな市場で、海外に出て行く必要がないからでしょう。海外に出れば必ずいずれぶち当たるようになる」
また、グローバル展開している協働イニシアティブに対して、敷居の高さを感じている企業も多いと推測されます。それは内容だけでなく、英語という言語の壁もしかりです。TEの理事を務めている興和の稲垣さんは、「日本企業でもアクセスしやすいように、サイトから日本語での情報発信などにも努めていきたい」と話していました。
そして最大の問題である「消費者」へのリーチについてです。
YKKの河西さんは長い海外の経験から、やはり日本人消費者の意識は高くないと指摘しています。「環境大国のドイツでは、環境負荷の低い製品について、"どこでどうやって作るのか"という情報が毎週テレビで放送されています」。とはいえ、「昔に比べれば格段に意識は向上している。長い時間はかかるかもしれませんが、情報発信を繰り返し、消費者に伝えていきたい」。
パタゴニア・辻井社長は、人が持っている美質を生かす仕組みがないだけではないかと指摘しています。
「人間誰でも共通しているのが、人を傷つけたくない、何かをすることで誰かが幸せになればうれしいという気持ちのはず。何かを選択することがうれしい気持ちにさせ、ポジティブで前向きになれる仕組みを作ればいいのではないでしょうか」
消費者からの声が大切
 tioproのサイトよりこれを受けて帝人フロンティア・宮武さんが出した同社の「tiopro(ティオプロ)」をめぐるエピソードが非常に示唆的です。「tio pro」は、"体操服!(t) いってらっしゃい(i)、おかえりなさい(o)"プロジェクトの略で、分子レベルでポリエステルをリサイクルする「エコサークル」を利用した取り組みで、児童が着られなくなった体操服を回収して100%リサイクルし、再び学校へ新しい体操服として提供するというもの。京都市の小中学校を中心に全国で約50校が参加しているそうです。
tioproのサイトよりこれを受けて帝人フロンティア・宮武さんが出した同社の「tiopro(ティオプロ)」をめぐるエピソードが非常に示唆的です。「tio pro」は、"体操服!(t) いってらっしゃい(i)、おかえりなさい(o)"プロジェクトの略で、分子レベルでポリエステルをリサイクルする「エコサークル」を利用した取り組みで、児童が着られなくなった体操服を回収して100%リサイクルし、再び学校へ新しい体操服として提供するというもの。京都市の小中学校を中心に全国で約50校が参加しているそうです。
「この取り組みは『永遠に捨てない服が着たい』という本で紹介され、2013年夏休みの課題図書にもなりました。これを読んで感動した静岡の女子小学生が、京都市の教育委員会に電話をして、まず『話を聞かせてほしい』、次に『見学させてほしい』、そして最後に『校長先生を説得してほしい』とお願いし、同校でもエコサークルが導入されたということがありました。良いものであれば、自然と輪が広がっていくのではないでしょうか」
このほかにも、アフリカのコンゴで、携帯電話で使われるレアメタルを採掘し、武装勢力の資金源として使われる結果、多くの少年兵が死んでいる現実と、それに疑問を持った消費者の問い合わせが、キャリア各社を動かした例なども出されました。つまり、企業を動かすのも、消費社会全体を動かすのも、まずは消費者一人一人が変わっていくことが第一歩ということ。
セッションの締めくくりとして、枝廣さんが来場者に向けて呼びかけます。
「現在、家電の廃棄量は年間60万トン。これに対して、衣料品は年間117万トンが購入され、106万トンが廃棄されています。国民一人当たり、9キロの服を買い、8キロ捨てているということ。Tシャツに換算すると42枚買って、38枚捨てているということです。そして、服を選ぶ基準として『安さ』を挙げている人は、1999年の38%から、2010年には51%に上昇しています。今、企業は消費者の声を無視することはできなくなっている時代。ぜひこうした現実を踏まえ、正しい問いを立て、自分の意見を表明するところから始めてほしい」
他の産業界に比べると技術的にも、意識的にも遅れていると感じざるを得ないアパレル・テキスタイル業界でしたが、今回のシンポジウムでは、より良い方向への確かな情熱と意志があることを感じさせてくれました。今後もパタゴニアでは「責任ある経済(レスポンシブル・エコノミー)」をテーマにしたシンポジウムやワークショップを展開していく予定です。興味を持った方は、ぜひここから、あなた自身の足で第一歩を踏み出してみてください。
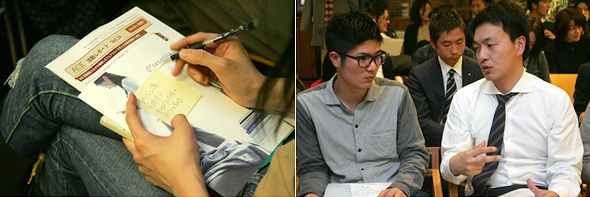 全体のトークセッション後、会場では近くの席同士での意見の交換や、気づきの共有などが行われました。
全体のトークセッション後、会場では近くの席同士での意見の交換や、気づきの共有などが行われました。
関連リンク
おすすめ情報
イベント
注目のワード
人気記事MORE
- 1
 【丸の内プラチナ大学】2024年度開講のご案内~第9期生募集中!~
【丸の内プラチナ大学】2024年度開講のご案内~第9期生募集中!~ - 2
 【大丸有シゼンノコパン】大手町から宇宙を「望る(みる)」ービルの隙間からみる、星空の先ー
【大丸有シゼンノコパン】大手町から宇宙を「望る(みる)」ービルの隙間からみる、星空の先ー - 3
 大丸有でつながる・ネイチャープログラム大丸有シゼンノコパン 冬
大丸有でつながる・ネイチャープログラム大丸有シゼンノコパン 冬 - 4
 【丸の内プラチナ大学】逆参勤交代コース 壱岐市フィールドワーク
【丸の内プラチナ大学】逆参勤交代コース 壱岐市フィールドワーク - 5
 【大丸有シゼンノコパン】【朝活】大丸有で芽吹きを「視る(みる)」ー春の兆しは枝先からー/まちの四季
【大丸有シゼンノコパン】【朝活】大丸有で芽吹きを「視る(みる)」ー春の兆しは枝先からー/まちの四季 - 6
 3×3Lab Future個人会員~2024年度(新規・継続会員)募集のお知らせ~
3×3Lab Future個人会員~2024年度(新規・継続会員)募集のお知らせ~ - 7
 【レポート】遊休資源が輝く未来へ 〜山形に学ぶ持続可能な地域づくりの挑戦〜
【レポート】遊休資源が輝く未来へ 〜山形に学ぶ持続可能な地域づくりの挑戦〜 - 8
 フェアウッド×家具~ものづくりを通じた自然や生態系への貢献~
フェアウッド×家具~ものづくりを通じた自然や生態系への貢献~ - 9
 指導経験ゼロから日本一のチームを作った「日本一オーラのない監督」が語る存在感と自己肯定感
指導経験ゼロから日本一のチームを作った「日本一オーラのない監督」が語る存在感と自己肯定感 - 10
 【大丸有フォトアーカイブ】第2回 みんなの写真展 2月21日~3月4日
【大丸有フォトアーカイブ】第2回 みんなの写真展 2月21日~3月4日