

6,14,15
2022年10月にカナダ・モントリオールで開催された第15回生物多様性条約締約国会議(COP15)では、2030年までに生物多様性の損失を止め、回復に向かせる「ネイチャーポジティブ」の重要性が議論されました。この時に採択された「昆明・モントリオール生物多様性枠組」で具体的な数字目標が盛り込まれたこともあり、今後は様々な国や企業がネイチャーポジティブの取り組みを強めていくことが予想されます。
こうした流れに対して、日本の企業や自治体はどのように相対していくべきなのでしょうか。それを知るために、2024年度のCSV経営サロンは「ネイチャーポジティブ」をテーマに掲げ、全3回に渡ってネイチャーポジティブの最新事情や取り組み方について考えていきます。
8月20日に開催された第1回目のセッションでは、環境省 大臣官房 広報室長(前・自然環境局 生物多様性主流化室長)の浜島直子氏と、JAXAスタートアップ企業である株式会社天地人COOの百束泰俊氏をゲストにお招きし、「ネイチャーポジティブ最前線」を学んでいきました。
生物多様性と企業のポートフォリオの多様化の類似点
 環境省の浜島直子氏
環境省の浜島直子氏
最初に登壇したのは、2022年から2024年まで環境省の生物多様性主流化室室長を務めた浜島氏です。生物多様性主流化室は、日本国内で生物多様性の保全を経済活動や社会活動の中で広めることを目的とし、生物多様性が当たり前のものになる状態を目指しています。浜島氏が着任してからは、「ネイチャーポジティブ経済」を推進することが大きな動きの一つとなりました。
「経済活動や企業の事業計画は、社会が健全であることを前提に成り立っていますが、その基盤は自然環境です。しかし、現状の地球環境を考えると、人間活動が原因で環境に大きな負荷がかかり、さまざまな問題が起きているため、経済活動もリスクにさらされる恐れがあるのです。だからこそ、ネイチャーポジティブと経済活動を結びつけることが不可欠です。」
浜島氏は続けて、単なる普及啓発活動ではなく、具体的なアクションを起こす必要があると強調しました。「企業の方々が市場に選択肢を提供できるようにすることが急務です。そこで、企業の視点に立ち、必要な施策に取り組んできました。考え方の出発点として、生物多様性を企業のポートフォリオに例える考え方を提案しています。企業のポートフォリオは、強みを発揮できる事業領域を追求していくと、結果的に多様化する。同様に、"生物多様性"を自然を構成する要素に分解し、それらを汚さない・使いすぎない、綺麗にする・増やす、と考えると、ビジネスチャンスを検討できるでしょう。」と述べています。フタバ産業のレーザー除草ロボなど、既存技術をネイチャーポジティブの観点から転用する技術も紹介されました。
環境省が主導するネイチャーポジティブ経済移行戦略とは

続いて浜島氏は、ネイチャーポジティブ経済への移行に向けた具体的な取り組みを紹介しました。2030年までに大企業の5割がネイチャーポジティブ経営に移行し、1000団体が「ネイチャーポジティブ宣言」をすることを目標に掲げています。生物多様性主流化室では、企業の行動変容を促進し、保全活動に関する法制度化を進めることなどを通じ、日本国内の自然保全価値を高める活動を行っています。また、企業が自然環境との接点を把握するためのワークショップや、自然関連財務情報開示タスクフォース(TNFD)に関する学習機会を提供しています。
さらに、ビジネスマッチングイベントの開催などを通じて、企業が自然保全に貢献する技術を結びつける支援を行っています。浜島氏は「ネイチャーポジティブはビジネスチャンスの宝庫」と位置づけ、企業にとってリスクだけでなく、積極的な取り組みを推進するための新たな機会と捉えることが重要であると述べています。
また、2023年にはネイチャーポジティブ経済アライアンス(G7ANPE)を日本が主導で設立しました。このアライアンスを通じて、世界中のビジネス事例を共有し、日本企業が技術力や取り組みをアピールする場を提供しています。2023年9月のワークショップでは、日本からは清水建設、住友化学、SynecOの各社がネイチャーポジティブに資する取り組み事例を紹介しました。
COP15で設定された「30by30(サーティ・バイ・サーティ)」目標にも、環境省は積極的に対応。2023年に184ヵ所が「自然共生サイト」として認定され、2024年には「地域における生物多様性の増進のための活動の促進等に関する法律」が制定されました。企業や地域が保全活動に取り組みやすい環境を整え、持続可能な社会を目指す流れを加速させる狙いです。
ネイチャーポジティブ経済移行戦略には、環境省のほか、連名で策定した農林水産省、経済産業省、国土交通省を始め様々な省庁の多くの促進策が掲げられています。
天地人のミッションは「人工衛星を通じて社会課題にアプローチする」
 天地人の百束泰俊氏
天地人の百束泰俊氏
次に登壇したのは、株式会社天地人COOの百束泰俊氏です。講演は「衛星データ利活用の最前線とその先の未来」をテーマに、宇宙技術とネイチャーポジティブの関係を探るものでした。
百束氏は、「『人工衛星』と聞くと、宇宙の謎を解明するものを連想するかもしれませんが、実際には気象衛星や通信衛星など、私たちの日常生活に直結する情報を提供しています」と説明しました。さらに、人工衛星は災害時にも活躍します。例えば、2024年元日の能登半島地震では、人工衛星を用いて被害状況を把握しました。また、8月に発生した日向灘地震でも、河川の氾濫状況を把握するために活用されました。
人工衛星の利点は、地上からでは見えない温度や地表の変化などの情報を把握できる点です。地表面温度は農業や漁業にも影響を与える重要なデータであり、このデータをもとにビジネスチャンスを探ることも可能だと百束氏は語りました。さらに、天地人は「天地人コンパス」という衛星データを活用した地理情報システム(GIS)プラットフォームを開発しています。これにより、特定地域の最適な農法や作物の選定など、自然環境に関する最適な意思決定を支援しています。
人工衛星✕ネイチャーポジティブの可能性
百束氏は、人工衛星の強みとして「抗堪性」「同報性」「継続性」「広域性」「越境性」の5つを挙げています。これらの特徴は、災害時や環境モニタリングにおいて特に有効です。また、人工衛星を使うことで、国や企業の境を越えてデータを取得できる越境性は、国際的な自然保護活動にも貢献すると述べました。
百束氏はさらに、宇宙ビジネスが今後10年間で大きく成長すると予測されていることを紹介しました。政府の支援や市場の拡大に伴い、人工衛星を活用した新たな産業が生まれつつあります。特に人工衛星によるデータは、森林の炭素蓄積量の観測や生物多様性の可視化に役立つ可能性があり、ネイチャーポジティブに寄与するビジネスモデルの創出が期待されています。
生物多様性を活かしたビジネスの未来

続いて、浜島氏と百束氏によるディスカッションが行われました。浜島氏は、生物多様性のビジネス化における定量化の難しさに言及しながらも、「土や水といった構成要素に分解して考えることで、保全に向けたアプローチが可能になる」と説明しました。 一方で、バイオテクノロジー産業に関する動向が日本にとってリスクとなり得る可能性についても議論され、国際的なルール作りに参加する重要性が強調されました。
百束氏は、人工衛星データの活用について「限界や制約があることを認識することが重要だ」と述べました。スタートアップ企業は新しいテクノロジーに対する期待値を高めがちですが、限界を認識し、それを補うための工夫が求められます。具体的には、人工衛星データを地上のデータや他の技術と組み合わせることによって限界を超えるビジネスモデルを構築することが必要だと説明しました。
さらに、会場からの質問に対して浜島氏は、脱炭素とネイチャーポジティブの取り組みについて、都道府県や流域などある程度広がりのあるエリアでの評価によって、自然環境のコネクティビティを評価しやすくし、投資家にとってもわかりやすい指標を提供することが有効だと提案しました。
また、自然エリアの重要性を地域の計画に位置づけることが、企業や自治体にとって持続可能な経済活動の一部として取り組む動機を強めるとしています。
最後に、浜島氏は次のように総括しました。「ネイチャーポジティブ経済への移行は、自然資本に基づいた新しい社会の礎を築くことに繋がります。企業は、生き残りを図るために地域や社会に何を提供できるかを常に考えていると思います。それは地域や社会にGDPを超えた価値をもたらします。自然資本も皆さんの価値提供の源泉に加えていただければ幸いです。」
百束氏も、衛星データの利活用によって自然環境のモニタリングが行いやすくなり、持続可能なビジネスチャンスが広がっていると強調。「人工衛星は、気候変動や災害、資源管理など多くの社会課題に対してアプローチする手段として大きな可能性を秘めています。特にネイチャーポジティブとの組み合わせにおいて、私たちは宇宙のデータを地球環境の保全に役立てていくことができるのです」と述べ、宇宙技術と自然保護の融合による未来の可能性を示唆しました。
日本企業の強みは「自然に対する謙虚さ」
 パネルディスカッションの様子。写真左がCSV経営サロン座長の小林光氏。左から2人目が同サロン副座長の吉高まり氏
パネルディスカッションの様子。写真左がCSV経営サロン座長の小林光氏。左から2人目が同サロン副座長の吉高まり氏
講演の後、それぞれCSV経営サロンの座長と副座長の、東京大学客員教授の小林光氏と一般社団法人バーチュデザイン代表理事の吉高まり氏を交えたパネルディスカッションが行われました。議論の焦点は、企業における生物多様性の取り組み方や、ネイチャーポジティブ経済を実現するための具体的なアクションに移りました。
吉高氏は、アメリカが生物多様性条約に未だ承認していないことや、30by30に対する一貫性のない姿勢について質問しました。浜島氏はこれに対し「確かにアメリカの動きはリスクとなり得ますが、現時点では民間同士の取り組みが中心であり、国際的なルール作りの流れに遅れを取らないよう努力するべきだ」と述べ、今後の国際協力の重要性を強調しました。
また、参加者からの質問に対し、百束氏は、衛星データが生物多様性の評価にどのように役立つかについても言及し、データの精度や限界を認識しながら、それを活かした新しいビジネスモデルの構築が必要だと強調しました。
 参加者からも多くの質問が飛び交った
参加者からも多くの質問が飛び交った
最後に浜島氏は、日本企業の強みは「自然に対する謙虚さ」であると指摘しました。「日本企業は自然の力を理解し、自然と共生する意識が高い」と述べ、TNFD(自然関連財務情報開示タスクフォース)の要求する基準も、その謙虚な姿勢がリスク対応力として評価される要素だと語りました。具体的には、データ収集だけでなく、現地の実際の状況を確認し、自然の不確実性に対して謙虚に向き合う姿勢が重要であると強調しました。
浜島氏は、「ネイチャーポジティブ経済への移行は、ビジネスだけでなく社会全体に恩恵をもたらすものであり、企業は自然資本を大切にしながら、自社の活動を見直すことが求められています」とまとめました。
また、百束氏も、人工衛星データが今後、自然環境の保全やモニタリングにおいてますます重要な役割を果たしていくとし、衛星技術とネイチャーポジティブの連携によって新しいビジネス機会が生まれる可能性を示唆しました。
その他にも多くの質問が飛び交い、ネイチャーポジティブに対する関心の高さが伺えました。こうして2024年度最初のCSV経営サロンは幕を閉じました。今年度は引き続き有識者を招きネイチャーポジティブへのアプローチを検討していくようです。乞うご期待ください。
CSV経営サロン
2011年からサロン形式でビジネスに関する様々なプログラムを提供。発足当初から小林光氏に座長を、2017年からは吉高まり氏に副座長をお願いし現在に至っています。
2015年度からは「CSV経営サロン」と題し、さまざまな分野からCSV経営に関する最新トレンドや取り組みを学び、 コミュニケーションの創出とネットワーク構築を促す場として取り組んでいます。
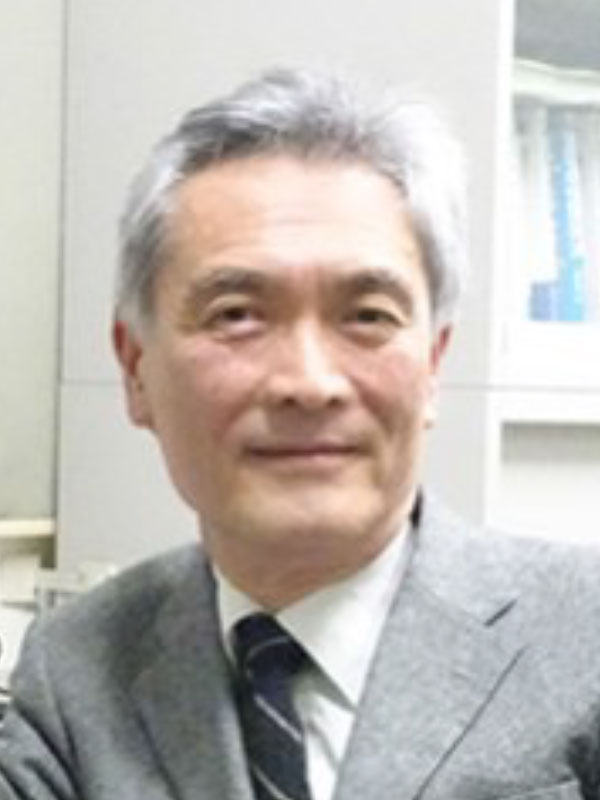
座長:小林光 氏
東京大学先端科学技術研究センター研究顧問 /
教養学部客員教授
慶應義塾大学経済学部卒(1973年)、東京大学大学院工学系研究科都市工学専攻修士、博士(2010・2013年、共に工学)。
1973年環境省(当時環境庁)入省。京都議定書交渉の担当課長、環境管理局長、地球環境局長、官房長、総合環境政策局長、2009年から2011年まで次官を務め退官。
慶應大学教授、米国イリノイ州にて派遣教授、2016年から現在まで東京大学客員教授。その他日本経済研究センター特任研究員、国立水俣病研究センター客員研究員、地方の環境審議会委員や脱炭素対策検討の委員等を歴任。
再生可能エネルギーを主要なエネルギー源とする資源循環型の社会を構築するために必要な価値観の転換、諸制度の整備などに取り組む。

副座長:吉高まり 氏
一般社団法人バーチュデザイン代表理事 /
東京大学客員教授/
慶慶應義塾大学総合政策学部特別招聘教授
明治大学法学部卒、米国ミシガン大学環境サステナビリティ大学院科学修士、慶應義塾大学大学院政策・メディア科博士(学術)。
IT企業、米国投資銀行等での勤務を経て2000年より現三菱UFJモルガン・スタンレー証券において気候変動関連の資金枠組みづくり、カーボンクレジット組成などに関与。政府、地方自治体、金融機関、事業会社などに向けて気候変動、GX、サステナブルファイナンスの領域について講演、アドバイスなどを提供し、新たにサステナビリティ経済の推進の実装を図る。
おすすめ情報
イベント
注目のワード
人気記事MORE
- 1
 【丸の内プラチナ大学】2025年度開講のご案内~第10期生募集中!~
【丸の内プラチナ大学】2025年度開講のご案内~第10期生募集中!~ - 2
 丸の内プラチナ大学2025 逆参勤交代コース特別講座 飛騨ナイト
丸の内プラチナ大学2025 逆参勤交代コース特別講座 飛騨ナイト - 3
 【大丸有シゼンノコパン】色彩豊かな冬の鳥を「観る(みる)」 ~極寒の今こそ絶好の"鳥"日和!~【まちの生きもの】
【大丸有シゼンノコパン】色彩豊かな冬の鳥を「観る(みる)」 ~極寒の今こそ絶好の"鳥"日和!~【まちの生きもの】 - 4
 大丸有でつながる・ネイチャープログラム大丸有シゼンノコパン 冬
大丸有でつながる・ネイチャープログラム大丸有シゼンノコパン 冬 - 5
 【大丸有シゼンノコパン】都心の緑地に春の目覚めを「覗る(みる)」~生きものとの共生のヒントを探して~【まちの生きもの/親子・初心者の大人向け】
【大丸有シゼンノコパン】都心の緑地に春の目覚めを「覗る(みる)」~生きものとの共生のヒントを探して~【まちの生きもの/親子・初心者の大人向け】 - 6
 【大丸有シゼンノコパン】ビルや樹々の隙間に星空を「望る(みる)」 ~「すばる」や「月」はどこにある?~【まちの星座】
【大丸有シゼンノコパン】ビルや樹々の隙間に星空を「望る(みる)」 ~「すばる」や「月」はどこにある?~【まちの星座】 - 7
 【レポート】関係資本の力を最大化する コミュニティデザインと持続的価値創造
【レポート】関係資本の力を最大化する コミュニティデザインと持続的価値創造 - 8
 3×3Lab Future個人会員~2025年度(新規・継続会員)募集のお知らせ~
3×3Lab Future個人会員~2025年度(新規・継続会員)募集のお知らせ~ - 9
 【レポート】共創がもたらす新たな価値創造 〜リビングラボが描く未来の地域経営~
【レポート】共創がもたらす新たな価値創造 〜リビングラボが描く未来の地域経営~ - 10
 【レポート】共感が未来を動かす 〜 クリエイティブが地域に灯す、新しい価値のつくり方
【レポート】共感が未来を動かす 〜 クリエイティブが地域に灯す、新しい価値のつくり方





