

社会人や学生が実践的な学びを得るための市民大学「丸の内プラチナ大学」が東京・大手町の3×3Lab Futureで開催されています。その中のひとつ、アートフルライフコースは、アートの持つ魅力を体感することで人生を豊かにし、自分らしい感性を磨くことを目的として開設されています。今期のテーマは「重なる、交わる、つながる」。講師の臼井清氏は「アートの視点を通して、自分らしい「つながり」を皆さんなりに探しながら受講してほしい」と話します。今回のトピックは能。臼井氏は「能楽の『わからない』を楽しみながら、謡(うたい)や舞で自分をみつめてみましょう。とことん能を体感しましょう」と受講生に呼びかけました。
- 続きを読む
- 世界最古の演劇「能」のいろは
世界最古の演劇「能」のいろは
 冒頭、「能」にフォーカスした狙いを説明するアートフルライフコース講師の臼井清氏
冒頭、「能」にフォーカスした狙いを説明するアートフルライフコース講師の臼井清氏
アートフルライフコースでは通例ウォーミングアップとして「けんちく体操©」から始まります。けんちく体操©は、お題として提示された写真(建築物など)になり切ってポーズをとる体操です。しかし、今回は能がテーマということで「自分なりの能のイメージをポーズで表す」がお題になりました。受講生たちは開始の合図とともに全身を使って「能」を自由に表現します。鳥のようなポーズをとる人、バレエのようなポーズをとる人など、さまざまなポーズが見られました。
 能を思い思いに表現する受講生たち
能を思い思いに表現する受講生たち
ウォーミングアップが終わると、いよいよゲスト講師であるシテ方金春流能楽師の柏崎真由子氏の登場です。柏崎氏は北海道函館市出身ですが「函館の一般家庭で育った18年間は一度も能を見たことがなかった」と話します。そんな柏崎氏が美術大学に進学後、身体表現の講義を受講する中で、体を使って表現することの面白さに目覚め、様々なジャンルの舞台を観るうちに能と出会い、「初めて能を観た時はよくわからなかったが、何回か観ているうちにすごい!面白い!と思うようになり、『これはきっと生涯をかけて追及するに値するものだ』と確信した」と語りました。
 DAY4のゲスト講師、能楽師の柏崎真由子氏
DAY4のゲスト講師、能楽師の柏崎真由子氏
柏崎氏は「能とは何か」というシンプルな疑問から講座を始めました。「能は演劇であり、人から人へと受け継いで行くものとしては世界最古の演劇と言われている。その歴史は奈良時代に散楽という物まねや曲芸が大陸から伝わったことに遡る。それが日本に伝わり猿楽(申楽)と名前を変え、観阿弥・世阿弥という二人の親子によって芸術的なものに昇華していった」と発祥を解説。能面を用いる理由については「能楽は今では能楽堂という専用舞台があるが、かつては寺社仏閣や貴族の屋敷などどこにでも出向いて公演していたため、手っ取り早く変身できる仮面劇である必要があった。古くは翁が神として出現し、祈りの形を具現化した神事が、演劇的なものへと変化していった。
さらに能の分業制についても説明します。例えば柏崎氏が属するシテ方(かた)というのは役割の名称だそうで、「能はシテ方、ワキ方、囃子方、狂言方の4つの役割によって一つの舞台が成立する分業制になっている。シテ方は謡と舞を担当して主役を演じる役割の一方で、ワキ方はシテと応対することでシテ(主人公)の想いや胸の内を引き出す役割を担ってくれる。現代風に言えばカウンセラー。囃子方は音楽を担当し場面を盛り上げ、狂言方は狂言を演じるほか、能の前後半をつなぐエピソードを語る役割を担っている」ようです。

柏崎氏は能の構成についても解説しました。「能の曲分類は全部で5つあるが、初番目物と呼ばれるのは神様が主役(シテ)の曲。二番目物は修羅物とも呼ばれ、武将の霊が主人公で出てくる曲。三番目物は源氏物語や伊勢物語などの王朝文学作品のヒロインや精霊が主人公になる曲。五番目物は切能とも呼ばれ、鬼や天狗、竜神などが主人公になるダイナミックな曲が多い。そしてこの4つのどれにも当てはまらないのが四番目物に分類される」ということでした。
能を体感する 謡、能面、舞から感性を研ぎ澄ます
このような能に関する基礎知識の後、いよいよ能の体感に入ります。まずは『敦盛』の謡を使った自己紹介。敦盛では「これは東国の住人。○○と申す者にて候」という一節がありますが、そこに自分の名前を入れて、ペアになって謡でお互いの自己紹介を行いました。それが終わると、難易度をあげて『高砂』の待謡(まちうたい)に挑戦。柏崎氏は「高砂は大阪にある住吉大社の主祭神住吉明神が主人公。神様の訪れを待っている謡だから待謡と言われる。この待謡は結婚式やお祝い事で謡われるため知っている人も多いかもしれない。節による音の移り変わりがあるが、是非挑戦してほしい」と紹介しました。柏崎氏は謡をいくつかに分割しながら丁寧に音の変遷を説明し、受講生はその指導に従って能独特の節回しを何度か練習しました。
 高砂の待謡を練習する受講生たち
高砂の待謡を練習する受講生たち
謡の後も、能独特の構えや能面の装着など「能の体感」は続きます。能面について柏崎氏は「能面は翁、女、男、鬼神など基本型は60種類ほどある。能面はよく無表情だと言われるが、それは面の角度を調整する「面当て」を面の裏面に貼り、わざと無表情な状態にしているからだ。でも実は能面は表情が豊かで、話の進行に従って悲しい時にはうつむき、嬉しい時には上を向くなど角度の調整によって表情が変わる」と語りました。受講生は普段は縁がない能面を実際に着け、「思ったよりも視野が狭い」「椅子に座るのも大変」といった驚きを語るとともに、写真撮影をするなど貴重な体験を存分に楽しんでいました。
 左:生成の能面について解説する柏崎氏
左:生成の能面について解説する柏崎氏
右:能面(左から増、小面、生成)
そののち、いよいよ受講生一人ひとりの感性を試される課題が与えられました。この課題では柏崎氏の舞を見て、それがどのようなシーンだと感じたかを考えるものです。1問目は柏崎氏が謡と舞で出題したのち、受講生たちが各グループで感じたことを発表しました。回答では「謡の中で剣や兜、潮という言葉も出ていたので、海辺で戦っている兵士を回想しているシーン」「船で出陣のイメージ」など、多くの受講生が戦いを連想したようでした。柏崎氏は「これは『八島』という曲の一場面。『八島』は源義経が主人公で、平家の水軍との合戦シーン」と明かし、多くの受講生がイメージした通りだったようです。
 曲目「羽衣」を舞う柏崎氏
曲目「羽衣」を舞う柏崎氏
2問目は少しレベルを上げて、謡なしで舞だけが出題されます。謡がないため、受講生からは「太陽を拝んで迎え入れるイメージが湧いた」「鳥、孔雀や白鳥などが羽を広げているシーンなのでは」「神様に何かを奉納しているように見えた」といったさまざまな意見、中には「サウナの熱波師に見えた」というユニークな回答も出ました。しかし、次に謡とともに舞うと、多くの受講生が「七宝を国土にと聞こえたので、土に恵みをもたらしている」「国土に宝を返すというような話」などと同様のイメージを共有しました。柏崎氏によると、正解は『羽衣』という演目で、「三保の松原に伝わる羽衣伝説に取材した曲。ある春の朝、、漁師は松の枝にかかっている美しい衣を見つけ持ち帰ろうとする。すると、漁師を呼び止める女性の声がする。その衣は天女の羽衣であった。天女は衣がないと月の世界へと帰れない為、衣を返して欲しいと懇願する。漁師は月の世界の舞を披露してくれたら衣を返すと約束し、天女は求められるまま舞を舞う。天女は舞いながら国土に色々な宝をもたらし満月の空へと帰っていったという話」だと解説しました。その後も柏崎氏からの出題は続き、受講生らは自らの感性を駆使して想像を膨らませ、物語を創り出していました。
 舞を見て感じたことを語り合う受講生たち
舞を見て感じたことを語り合う受講生たち
柏崎氏は授業の最後に次のように語りました。「能には老若男女貴賤貧富さまざまな主人公が登場する。その主人公の物語を目撃し、追体験するところから始まる。そしてその物語と皆さんの経験を重ね合わせて、人生を振り返る良い機会になると思う。皆さんが能を見て感じたことはすべて正解であり、こう観なければいけないということは一切ない。能は観る人の想像力で舞台を補うことによって、初めて1つの舞台が完成する、自由度が高い芸能だ。だからこそ私は能が面白いと思うし、皆さんにもぜひ能楽堂に足を運んでほしい」

講義終了後、受講生は「学生時代に能を観た時は面白さが分からなかったが、今日の講座で深みを感じた」と感想を語り、また別の受講生は「『能を観てどのように感じるかはその人次第』という柏崎氏の言葉で、自分とは縁遠いと感じていた能が身近に感じることができた」と語っていました。
日本の伝統芸能である能について知っている方は多いと思いますが、なんとなく敷居が高いと感じているのではないでしょうか。しかし柏崎氏は、「能は古いから価値があるのではなく、時代を問わず人の心に必要な何かがあるからこそ現代まで残ってきた」と言います。今昔変わらぬ心の機微を追体験し、それを自分の経験と照らし合わせ人生を振り返る。それが能の楽しみ方だと考えれば、敷居が少し低く感じられるのではないでしょうか。
丸の内プラチナ大学
あなたの「今後ありたい姿」「今すべきこと」とは?
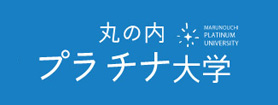
丸の内プラチナ大学では、ビジネスパーソンを対象としたキャリア講座を提供しています。講座を通じて創造性を高め、人とつながることで、組織での再活躍のほか、起業や地域・社会貢献など、受講生の様々な可能性を広げます。
おすすめ情報
-

【丸の内プラチナ大学】逆参勤交代コース 石川県七尾市フィールドワーク
2025年11月7日(金)~9日(日)
-

【丸の内プラチナ大学特別連携講座】すさきがすきさフェス Vol.1 ~須崎市交流イベント 2025 in TOKYO~
2025年10月25日(土) 16:00~19:00
-

【FCAJ共催イベント】EMICoフォーラム2025 「産学官民の地域共創の場 イノベーションコモンズの現在地とこれから」
2025年11月5日(水) 15:00~18:00
-

【レポート】AI時代に求められるコミュニティマネジャーの価値と役割
丸の内コミュマネ大学~AI×コミュニティの未来~ 2025年7月10日(木)開催
イベント
注目のワード
人気記事MORE
- 1
 丸の内プラチナ大学2025 逆参勤交代コース特別講座 飛騨ナイト
丸の内プラチナ大学2025 逆参勤交代コース特別講座 飛騨ナイト - 2
 【丸の内プラチナ大学】2025年度開講のご案内~第10期生募集中!~
【丸の内プラチナ大学】2025年度開講のご案内~第10期生募集中!~ - 3
 【大丸有シゼンノコパン】色彩豊かな冬の鳥を「観る(みる)」 ~極寒の今こそ絶好の"鳥"日和!~【まちの生きもの】
【大丸有シゼンノコパン】色彩豊かな冬の鳥を「観る(みる)」 ~極寒の今こそ絶好の"鳥"日和!~【まちの生きもの】 - 4
 大丸有でつながる・ネイチャープログラム大丸有シゼンノコパン 冬
大丸有でつながる・ネイチャープログラム大丸有シゼンノコパン 冬 - 5
 【大丸有シゼンノコパン】ビルや樹々の隙間に星空を「望る(みる)」 ~「すばる」や「月」はどこにある?~【まちの星座】
【大丸有シゼンノコパン】ビルや樹々の隙間に星空を「望る(みる)」 ~「すばる」や「月」はどこにある?~【まちの星座】 - 6
 【大丸有シゼンノコパン】都心の緑地に春の目覚めを「覗る(みる)」~生きものとの共生のヒントを探して~【まちの生きもの/親子・初心者の大人向け】
【大丸有シゼンノコパン】都心の緑地に春の目覚めを「覗る(みる)」~生きものとの共生のヒントを探して~【まちの生きもの/親子・初心者の大人向け】 - 7
 【レポート】関係資本の力を最大化する コミュニティデザインと持続的価値創造
【レポート】関係資本の力を最大化する コミュニティデザインと持続的価値創造 - 8CSV経営サロン2025 第3回「資源循環の出口、有機性資源のアップサイクル」
- 9
 3×3Lab Future個人会員~2025年度(新規・継続会員)募集のお知らせ~
3×3Lab Future個人会員~2025年度(新規・継続会員)募集のお知らせ~ - 10
 【丸の内プラチナ大学】逆参勤交代コース 高知県須崎市フィールドワーク
【丸の内プラチナ大学】逆参勤交代コース 高知県須崎市フィールドワーク

