

7,13,17
エコッツェリア協会では法人会員に向けて、知見の共有や新しい連携のきっかけを探ることをめざして、法人会員や注目企業の関連施設を訪れる視察ツアーを定期的に開催しています。2025年7月15日には、東京ガスが運営する「横浜テクノステーション」と、北海道を中心にドラッグストア事業などを展開するサツドラホールディングスが運営する「EZOHUB TOKYO」の視察を実施しました。
普段なかなか触れることができない最先端技術の研究施設と、新たなイノベーションを生み出すイノベーション施設は、会員たちの目にどのように映ったのでしょうか。ツアーの模様をレポートします。
カーボンニュートラルへの挑戦の最前線・横浜テクノステーション
 左:東京ガスがメタネーションに力を入れる理由を説明する東京ガスエンジニアリングソリューションズ株式会社都市エネルギー営業本部の水守博史氏。今回は参加者としてツアーにも帯同した
左:東京ガスがメタネーションに力を入れる理由を説明する東京ガスエンジニアリングソリューションズ株式会社都市エネルギー営業本部の水守博史氏。今回は参加者としてツアーにも帯同した
右:東京ガスの取り組みや横浜テクノステーションの概要について説明を受ける参加者たち
今回のツアーに参加したのは、エコッツェリア協会法人会員等に所属する17名です。エネルギー、金融、メーカー、行政など幅広い分野に携わる人々が集まりました。
最初に訪れた横浜テクノステーションは、「CO2ネット・ゼロ」に向けた脱炭素関連技術の開発や、社会実装に向けた取り組みを推進する、東京ガスの技術開発拠点です。2050年のカーボンニュートラル実現に向けて、東京ガスは様々な取り組みを展開していますが、その中でも力を入れているのが「メタネーション」です。
近年注目を集めているメタネーションは、水素とCO2を化学反応させて都市ガスの主成分であるメタンを生み出すもので、発電所や工場などで排出されたCO2を使うことで、燃焼時にCO2を排出しても大気中のCO2量は増加しないため、脱炭素化に大きく貢献すると考えられています。メタネーションで生み出されたメタンはe-メタンと呼ばれ、このe-メタンはもともと用いられていた天然ガスと同じ性質を持つため、都市ガスのパイプラインや貯蔵設備、ガス機器といった既存インフラをそのまま活用して顧客に供給することができます。つまり顧客側には新たなインフラ投資が不要となります。
メリットが多い一方で、普及には課題もあります。合成メタンの製造国と利用国のどちらでCO2排出量をカウントするか、証書制度の確立、既存の燃料よりも割高になるため価格差をどう埋めるか、といった問題です。東京ガスでは、社会実装に立ちはだかるこうした課題に対して、業界一丸となり様々な関係者と連携しながら解決策を模索しています。
 左:メタネーションへの取り組みについて説明を受ける参加者たち
左:メタネーションへの取り組みについて説明を受ける参加者たち
右:メタネーション実証設備を見学する様子
 カナデビア社製のメタネーション実証設備は、12.5Nm3/h-CH4の製造能力を持つ
カナデビア社製のメタネーション実証設備は、12.5Nm3/h-CH4の製造能力を持つ
施設概要や東京ガスの取り組みについて説明を受けた一行は、2つの班に分かれて施設内の見学へと移ります。東京ガス社員の案内の下、本館コンセプトルームとメタネーション実証設備を巡ります。
本館コンセプトルームでは、東京ガスの研究開発部門が取り組む技術開発について説明を受けました。水電解水素の製造に関しては、既存の燃料との競争力を持つためにコストの削減を進めています。例えば水電解装置の心臓ともいえる部位である「セルスタック」製造のコストを削減するため、AIを活用してより安価な触媒を探したり、機器の大型化を進めたりしているそうです。また風力発電の運用効率化や、CO2の削減だけでなく回収・貯留・利活用の取り組みについても紹介がありました。CO2の利活用では、空気中のCO2を吸収して固まるCO2吸収型コンクリートや、排出されたCO2を石けんや肥料などに転換する技術などが紹介され、「まだまだ実証段階なので、普及や社会実装に向けた良いアイデアがあればぜひご意見をください」との呼びかけもありました。
メタネーション実証設備は、e-メタンの製造から利用まで一貫して試せる小規模サプライチェーンを構築したものです。実験に使うCO2は横浜市のごみ焼却工場や下水処理場で回収したものを活用しています。地域連携によるメタネーションのあり方の検討を進めることで、将来的には地産地消モデルの構築につなげたいとのことです。
またe-メタン製造のエネルギー変換効率向上を目指して、新しい技術開発にも取り組んでいます。そのひとつが、e-メタンを生成する際に出る熱を水電解に利用してエネルギー効率の向上とコストダウンが実現できる「ハイブリッドサバティエ」という技術です。ハイブリッドサバティエは順調に研究開発が進んでいて、2030年代初頭の社会実装が目指されています。
説明を受けた後、施設内に立つ高さ約10mのメタネーション装置を実際に見学した参加者たちは、カーボンニュートラルへの挑戦の最前線に立つ機械を興味深く眺めていました。最後に質疑応答を行い、横浜テクノステーションの見学を終えました。
北海道と日本をつなぎ、東京から北海道を盛り上げるEZOHUB TOKYO
昼食を取った一行は、バスで東京・品川へと移動し、第二の目的地であるEZOHUB TOKYOに到着します。EZOHUB TOKYOは「北海道と日本をつなぐ"出島"」というコンセプトの下、北海道から東京をはじめとした全国に進出を狙う企業や自治体、あるいは他地域から北海道での事業展開を考える企業などを支援するリージョナルインキュベーションセンターです。施設内にはプライベートオフィスやコワーキングスペース、会議室などがあり、北海道にまつわる書籍や、道内の企業や自治体のパンフレットなどが置かれ、北海道のビジネスと情報発信拠点としての役割も持っています。
EZOHUB TOKYOの運営企業は、主に北海道でドラッグストア事業や地域マーケティング事業のグループ会社を展開するサツドラホールディングスです。なぜ北海道の企業が東京でインキュベーション施設を運営するのでしょうか。EZOHUB TOKYOでインキュベーターを務める笠井泰士氏は、その理由を次のように説明します。
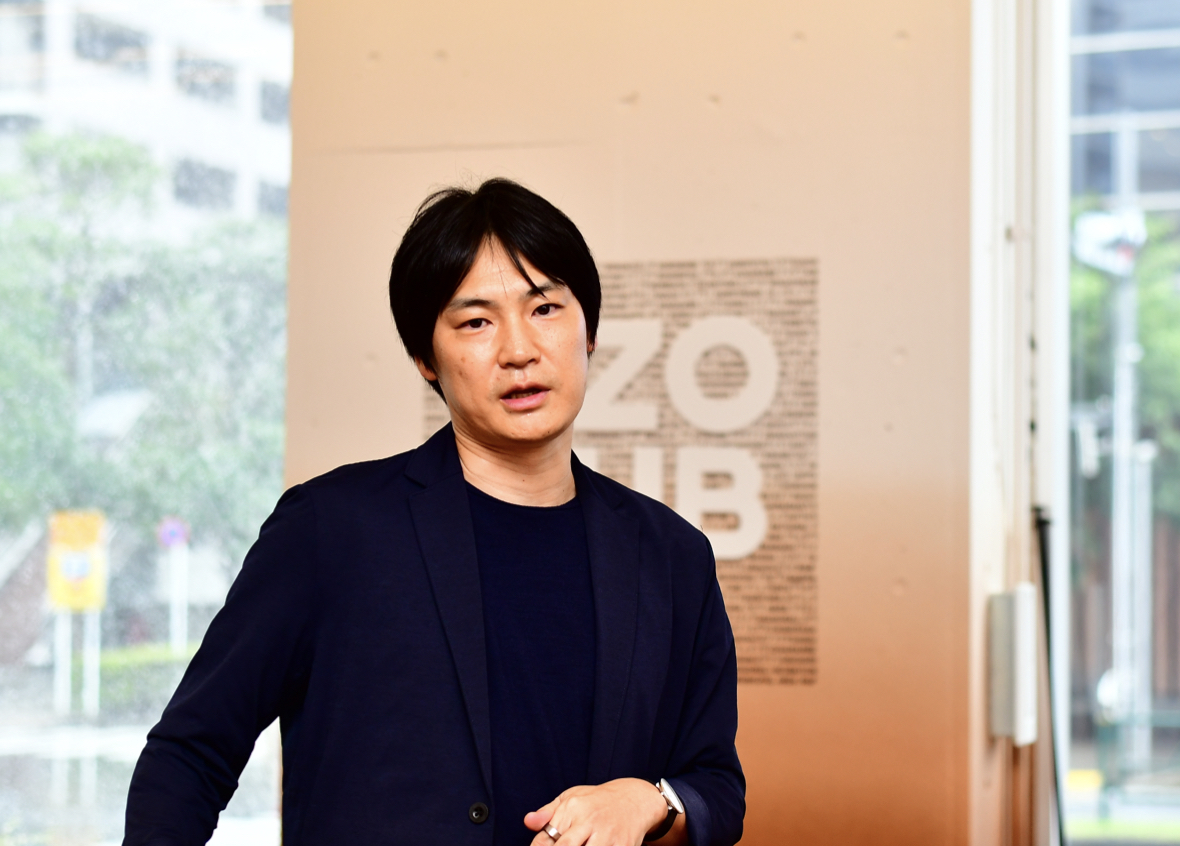 EZOHUB TOKYOでインキュベーターを務める笠井泰士氏
EZOHUB TOKYOでインキュベーターを務める笠井泰士氏
「サツドラホールディングスは、『ドラッグストアビジネスから地域コネクティッドビジネスへ』というビジョンを掲げています。地域としっかりとつながり共にビジネスをしていくことを目指し、さまざまな取り組みをする中で、コミュニティ事業のひとつとしてEZOHUB TOKYOの運営にチャレンジしています。北海道にある179市町村の約半分は人口5,000人未満の自治体で、地域には課題が山積しています。北海道を中心に店舗展開している私たちにとっても各地域の抱える課題は無関係ではないため、地域と連携して地域課題の解決とビジネスチャンスの創出を重視しています。経済的価値と社会的価値の両輪に取り組むことは、サツドラの成長にもつながると考えています」(笠井氏)
さらに笠井氏は、このようなリージョナルインキュベーションセンターを民間主導で運営し、成功に導くことにも重要な意味があると話します。
「EZOHUB TOKYOのような地域特化型の施設は、これまでの私の印象では、自治体や行政が取り組んでいるものが馴染むと思います。しかし、サツドラホールディングスのように地域の中核企業が自社だけの軸ではなく、地域全体を軸として、こうした事業を展開し、経済活性化や地域課題の解決を実現することは非常に意義深いと考えており、私たちが新たな可能性を切り開き成功を収めることができれば、きっと北海道以外の他地域の中核企業も呼応していくのではないかと思っています。」(同)
 左:プライベートオフィスは北海道に拠点を置く企業・団体が登録
左:プライベートオフィスは北海道に拠点を置く企業・団体が登録
右:「EZOHUB TOKYO」のロゴの背景には北海道の179市町村の名前が記載されていて、視察では人気のポイントに
 左:オフィススペースに併設される売店は無人店舗。小売店における実証実験の場としても活用されている
左:オフィススペースに併設される売店は無人店舗。小売店における実証実験の場としても活用されている
右:質疑応答の様子
こうした考えから、EZOHUB TOKYOはいわば「北海道の東京事務所のひとつ」としての機能を持っていると言えます。自治体が東京事務所を開設するためには、当然ながらその分の財源や人手が必要となるため、全ての自治体が東京に事務所を構えることができるわけではありません。そこでEZOHUB TOKYOが北海道179市町村とコミュニティパートナーの関係として東京事務所の機能のひとつとなることで、シティプロモーションやネットワーク支援、政策支援、官民連携事業の創出などに取り組んでいるのです。
目標達成のためにEZOHUB TOKYOが積極的に取り組んでいるのが交流機会の創出です。2024年5月の施設オープン以降、多種多様なテーマのイベントが毎週のように開催され、それをきっかけに北海道の情報発信や、自治体・企業の新たなネットワーク構築につなげています。例えば、北海道の企業と首都圏企業のマッチングイベントのように具体的なイノベーションを目指すイベントや、釧路市での二地域居住を推進するイベント、「函館市と旭川市のどちらが"北海道第二の都市か"」を議論するというエンタメ性のあるイベントなども開催されました。例えば、釧路市の二地域居住推進イベントでは、単に地域の魅力を発信するだけでなく、釧路市の事業者や国土交通省の二地域居住推進担当者、北海道の不動産事業者などが登壇し、実際に釧路市と他地域の人々をつながるきっかけとなっています。一過性のイベントで終わらせず、その先を見据えた企画が展開されています。
最後に笠井氏は、自身の取り組みに対する思いや担うべき役割について、次のように話しました。
「北海道と日本、地域と地域をつなぐ取り組みの中で、私が意識していることは、相手の課題や実現したいこと、意志を把握し、その課題や取組において足りないピースは何か、どのように持続的な事業化・自走化につなげることができるかを考え、チャレンジしています。本日訪れていただいた皆様とも、ぜひ一緒に盛り上げていければと思います」(同)
「私たちの活動は北海道を盛り上げることに重きを置いています。だからこそEZOHUB TOKYOをきっかけに、弊社の店舗がない地域や自治体とも連携が広がっていますし、私たちだけが考えるのではなく、皆さんがEZOHUB TOKYOを起点とした連携を考えてくださっています。もちろん我々は民間企業ですから、この事業をきっかけとして、地域とともに稼ぐ、新たなビジネスにつなげることにもチャレンジしています」(同)
カーボンニュートラルの実現に取り組む横浜テクノステーションと、地域活性化に取り組むEZOHUB TOKYOを巡る視察ツアーは、こうして終了の時間を迎えました。テーマは異なりますが、それぞれが重要な社会課題に挑む施設であるだけに、今後社会を変革に導く成果が出てくることが期待されます。また、この日ツアーに参加した人々が両施設とどのように関わりを持っていくのかも楽しみなところです。
エコッツェリア協会では、今後も法人・個人会員の皆さまを対象にしたフィールドワークなどを実施していく予定です。エネルギーや環境課題、地方創生などのテーマに興味のある皆さまの参加をお待ちしています。
 EZOHUB TOKYOで集合写真
EZOHUB TOKYOで集合写真
おすすめ情報
イベント
注目のワード
人気記事MORE
- 1
 【丸の内プラチナ大学】2025年度開講のご案内~第10期生募集中!~
【丸の内プラチナ大学】2025年度開講のご案内~第10期生募集中!~ - 2
 【大丸有シゼンノコパン】色彩豊かな冬の鳥を「観る(みる)」 ~極寒の今こそ絶好の"鳥"日和!~【まちの生きもの】
【大丸有シゼンノコパン】色彩豊かな冬の鳥を「観る(みる)」 ~極寒の今こそ絶好の"鳥"日和!~【まちの生きもの】 - 3
 大丸有でつながる・ネイチャープログラム大丸有シゼンノコパン 冬
大丸有でつながる・ネイチャープログラム大丸有シゼンノコパン 冬 - 4
 丸の内プラチナ大学2025 逆参勤交代コース特別講座 飛騨ナイト
丸の内プラチナ大学2025 逆参勤交代コース特別講座 飛騨ナイト - 5
 【大丸有シゼンノコパン】都心の緑地に春の目覚めを「覗る(みる)」~生きものとの共生のヒントを探して~【まちの生きもの/親子・初心者の大人向け】
【大丸有シゼンノコパン】都心の緑地に春の目覚めを「覗る(みる)」~生きものとの共生のヒントを探して~【まちの生きもの/親子・初心者の大人向け】 - 6
 さんさんネットワーキング~2026春~
さんさんネットワーキング~2026春~ - 7
 3×3Lab Future個人会員~2025年度(新規・継続会員)募集のお知らせ~
3×3Lab Future個人会員~2025年度(新規・継続会員)募集のお知らせ~ - 8
 【レポート】共創がもたらす新たな価値創造 〜リビングラボが描く未来の地域経営~
【レポート】共創がもたらす新たな価値創造 〜リビングラボが描く未来の地域経営~ - 9
 【レポート】共感が未来を動かす 〜 クリエイティブが地域に灯す、新しい価値のつくり方
【レポート】共感が未来を動かす 〜 クリエイティブが地域に灯す、新しい価値のつくり方 - 10
 【レポート】マーケットイン思考がもたらす食農ビジネスの可能性
【レポート】マーケットイン思考がもたらす食農ビジネスの可能性





