

これまで同一性が高い働き方やライフスタイルが、現代において大きく変わってきています。人々が属するコミュニティの種類は多様になり、それと同時に、コミュニティの管理・運営、活性化や方針策定などを担うコミュニティマネージャーの重要度が高まっています。
コミュニティを取り巻く環境の変化により、イノベーションを生み出す共創型コミュニティの醸成のノウハウや、コミュニティマネージャーの人材要件の定義づけなどが求められます。そうしたことを話し合い、深めていく場を目指して、2025年春以降、丸の内でコミュニティを運営する人々が中心となって「丸の内コミュマネ大学」の開校が予定されています。設立に先立ち、2024年11月22日、「コミュニティの未来予測」について考えをめぐらすプレイベントを開催しました。その模様をレポートします。
 この日は、誰でも簡単に食事会を行えるWebサービス「shokujii(ショクジー)」を活用し、夕食を食べながらのセッションとなった。恒例の参加者全員による「いただきます」の合唱を経て講演がスタート
この日は、誰でも簡単に食事会を行えるWebサービス「shokujii(ショクジー)」を活用し、夕食を食べながらのセッションとなった。恒例の参加者全員による「いただきます」の合唱を経て講演がスタート
コミュニティマネージャーに求められる3つの人材要件
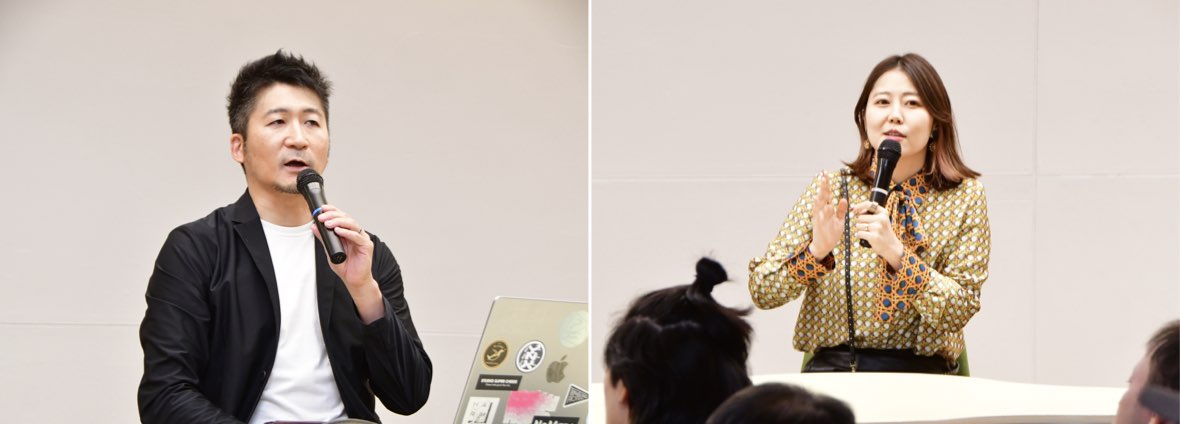 写真左:株式会社ファイアープレイスの渡邉知氏
写真左:株式会社ファイアープレイスの渡邉知氏
写真右:株式会社日建設計 イノベーションデザインセンターの吉備友理恵氏
この日のプレイベントでは、実際にコミュニティマネージャーとして活躍したり、コミュニティに関する研究を行ったり、場作りやコミュニティマネージャーの育成などに携わる先駆者と言える人々をゲストにお迎えし、これから求められるコミュニティやコミュニティマネージャーのあり方について、講演とパネルディスカッションを通して深掘りしていきました。
最初に登壇したのは、渡邉知氏(株式会社ファイアープレイス)と吉備友理恵氏(株式会社日建設計イノベーションデザインセンター)です。吉備氏は、日建設計が2023年4月にオープンしたPYNTという共創の場の企画・運営も行う人物です。両氏からは、事業をベースとしたイノベーション創出に不可欠な共創型コミュニティの必要性や、過程で生じる課題解決策、人材要件などに関する共同研究について報告いただきました。
組織は、課題が起点で強制力のある課題解決型の「タテ組織」と、想いが起点で強制力のない価値創造型の「ヨコの組織」のふたつに大きく分けられます。従来の企業体は前者の形が多く、コミュニティは後者に当たります。ヨコの組織を設立する上で渡邉氏が大切にしているのは、つながり」だといいます。
「弊社は、何もない"空間"に機能が加わると"場所"になり、場所で人と人のつながりが生まれると"場"となり、場で人間関係が醸成されていくとやがてコミュニティとなっていく、と考えています。では、つながりの定義は何か。こちらは、共感が生まれること、と定義しています」(渡邉氏)
日建設計の共創の場であるPYNTでも、「人と人との出会い」を起点として、社会課題を解決する「共創」が生まれることを目指しています。共通していることはつながり。この親和性を通して、渡邉氏と吉備氏は、それぞれが取り組んできた事例などを振り返りながら、共創推進に必要な要素を見出していくことに取り組みました。そして見えてきたもののひとつが、共創型コミュニティを構築するための3つの人材要件です。
①人間関係を醸成する人材
②プロジェクトを遂行する専門性を有した人材
③人間関係とプロジェクトの架け橋を担い、インテグレートできる人材
「私はよく、『技術・場所・資金・課題を意識して、つなぎ合わせよう』という話をしています。課題意識だけの人が何人集まってもなかなか話は進みません。課題に対して何をどうするかを意識し、チームでできる形を模索し、いろいろなレイヤーの人をつなげて、インテグレートしながらプロジェクトを構築できる人材が重要だからです」(吉備氏)
現代では、コミュニティマネージャーという職業の認知度が徐々に高まり、重要性の理解も進んでいます。この流れを加速させるためにも、共創推進の最適な方法を考えることで、人材獲得や育成を促進し、コミュニティの醸成を進めることに貢献していきたいと、両氏は語りました。
 質疑応答の様子
質疑応答の様子
働く場所の変化は、企業力の強化に結びつく
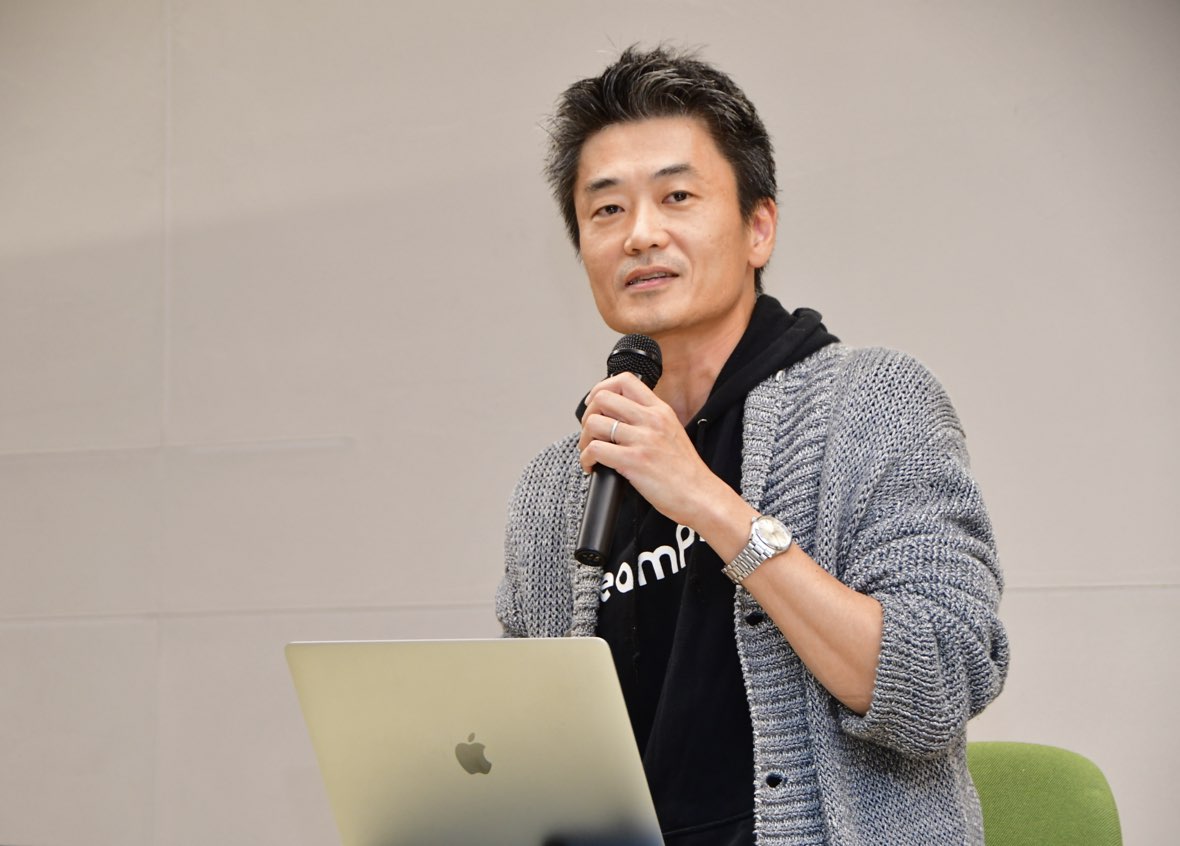 株式会社AnyWhereの斉藤晴久氏
株式会社AnyWhereの斉藤晴久氏
続いて登壇したのは、働き方やデジタルノマドの研究に取り組む斉藤晴久氏(株式会社AnyWhere 代表取締役CEO /PerkUP株式会社 代表取締役COO)です。斉藤氏からは、国内外の働く場所事情と企業コミュニティに関する事例紹介が行われました。
働き方の多様化や、コロナ禍の影響で、日本のみならず世界中でリモートワークやテレワークが一般化しています。それによって特定の場所に縛られずに働ける「デジタルノマド」と呼ばれる人々が増加し、その数は世界で3,500万人にも達していると言われています。それに伴い、働く場所にも変化が生じ、かつては単なるレンタルオフィスとしての役割しかなかったコワーキングスペースは、コミュニティ形成やビジネス支援の拠点へと進化しています。
斉藤氏は国内外の特徴的なコワーキングスペース、コミュニティスペースの事例を取り上げ、日本では人と人の繋がりを作ることで最初の接点づくりを担うコミュニケーターの傾向が高く、コワーキングでは仕事のしやすさが重視される一方で、海外はビジネス伴走型のコミュニケーターが所属しはそこにいる人との出会いが求められる傾向があることを紹介。そして最後に、次のようにコミュニティに関する考察を述べて講演を締めくくりました。
「仕事という一日の大半を占める活動がオンラインで賄えるようになったことで、現在では『日常はオンライン、非日常はリアル』という価値観が浸透し、リアルの価値が高まっています。働く場所の多様化は、企業が従業員に対してどのような価値を提供するかが問われることを意味し、企業文化自体の進化にもつながるでしょう。そして、働く場所がコミュニティ化したり、貢献機会を作ることで、有機的なつながりが生まれ、企業自体の力も強くなってくるのではないかと考えています」(斉藤氏)
ソーシャルな場とクロージングな場におけるコミュニティマネジメントの違い
 株式会社ディー・サイン代表取締役社長/株式会社大村湾商事代表取締役の長尾成浩氏
株式会社ディー・サイン代表取締役社長/株式会社大村湾商事代表取締役の長尾成浩氏
3番目に登壇した長尾成浩氏(株式会社ディー・サイン代表取締役社長/株式会社大村湾商事代表取締役)は、企業内のコミュニティ形成と、それを実現するための働き方の変革について語りました。
「環境が変われば行動が変わり、行動が変わると意識が変わる」という考えを持つ長尾氏は、企業が社員の意識を変えたい場合、オフィスに投資することを推奨しています。その対象となるのは、表層的・物理的なものだけではなく、ツールや仕組み、仕掛けといった運用環境も含まれます。そのバランスによって組織内のコミュニケーションの形が変わり、コミュニティのあり方も変わります。ただし、作り手がどれだけの意図をオフィスに込めても、使用者側がその意図に沿って使えなければ効果は現れません。そのため、企業内におけるコミュニティマネージャーには、コミュニティが拠点を置く場のファシリティを含め、空間を有効活用することを意識したマネジメントが求められるのです。
こうした点を踏まえて、長尾氏は「企業内においてコミュニティをマネジメントするのは、社内のファシリティを管理する総務部門であることが望ましく、総務部の中にコミュニティマネジメント部課のようなチームを設けることが、コミュニティ醸成の近道になる」「ソーシャルな場と企業内のようなある程度閉じた場におけるコミュニティマネジメントは、似て非なるもの」と説明しました。
コミュニティマネージャーの視点を持つ意味
 株式会社qutori CEO / 株式会社ロフトワーク コミュニティデザイナーの加藤翼氏
株式会社qutori CEO / 株式会社ロフトワーク コミュニティデザイナーの加藤翼氏
最後の登壇者となった加藤翼氏(株式会社qutori CEO / 株式会社ロフトワーク コミュニティデザイナー)は、自身が運営するコミュニティマネージャーの学校「BUFF」を通して見えてきたものについて紹介しました。
2018年にスタートし、これまで19期に渡って累計222名の受講生、34名の認定取得者を輩出しているBUFF。そのカリキュラムは「コミュニティマネジメントをするうえで、集団をどのような視点で捉え、どのような感性でアプローチできるかが大事になる」という加藤氏の考えの下、単純にHowを教えるのではなく、コミュニティマネージャーの心構えからスタートし、施設やメンバー、イベントやメディア、セルフリソースまでをマネジメントする方法が含まれます。
BUFFのカリキュラムは、開設から現在に至るまで、日々社会情勢やコミュニティを取り巻く環境の変化に合わせてアップデートされてきました。そうした背景を踏まえてこれまでの5年間を振り返った加藤氏は、今後さらに変化していくコミュニティ運営に求められるものについて、次のように語りました。
「コミュニティマネージャーが世の中で一般化し、かけがえのない存在になりつつありますが、その反面、明らかに人が足りていない状況です。必ずしもこの職種に就かなくてもいいのですが、コミュニティマネージャーの視点を持って組織や社員、地域に関わっていくと、大切な人たちを幸せにできるのではないかと考えています」(加藤氏)
企業内におけるコミュニティマネージャーのあり方とは
 パネルディスカッションの様子。3×3Lab Future館長の神田(写真左)とネットワークコーディネーターの田邊智哉子(写真左から2人目)も登壇。
パネルディスカッションの様子。3×3Lab Future館長の神田(写真左)とネットワークコーディネーターの田邊智哉子(写真左から2人目)も登壇。
それぞれの講演を終えると、パネルディスカッションへと移りました。真っ先に議論のテーマとなったのは、「企業内におけるコミュニティマネージャーのあり方」でした。例えば吉備氏は「開放的なオフィスでは、誰に何を聞いていいのかわからないことがよく起こります。そこで、その場に相談ができる人がいる環境を作ることは喜ばれます。それによって社内のコミュニケーションが活性化し、さまざまなつながりが生まれることは、社内からも評価されています」と、社内のコミュニティマネージャーの意義を語りました。
また、コミュニティを醸成する上で、社員の意識を改革していくにはどうすればよいか、という問いに対して、長尾氏は「コミュニティを作っているプロセスをどれだけ社員と共有できているか」が、ポイントになると指摘。その上で、「我々が担当する場合は、設計そのものだけでなく、それを考え、作られるプロセスを、企業の内部に向けて発信していけるか」が鍵になると話しました。
その後、参加者からの質問も積極的に飛び交い、コミュニティやコミュニティマネージャーの未来について活発な議論がかわされました。
 会場はほぼ満員で、コミュニティマネージャーに対する関心の高さが伺えた
会場はほぼ満員で、コミュニティマネージャーに対する関心の高さが伺えた
最後に、3×3Lab Future館長の神田は、「コミュニティマネージャーという職種は定義が広すぎるので、企業内における位置づけや必要性をさらに深掘りし、定義付けしていく必要があると感じています。しかし、"人類皆コミュマネ"になれば、イノベーションが進み、社会課題の解決にもつながるはずです。この動きを推進してコミュマネ大学の開校を実現したいと考えています」と語りました。
この言葉のように、今後もコミュニティマネージャーのあり方について考えながら、2025年春頃を目処に丸の内コミュマネ大学オープンキャンパスの開校を進めていきます。今後の展開に乞うご期待ください!
 登壇者で記念写真
登壇者で記念写真
おすすめ情報
-

【レポート】ビルよりも緑が多い!? 大丸有のまちの魅力を映す写真展
【大丸有フォトアーカイブ】第2回みんなの写真展 オープニングイベント 2025年2月22日(土)開催
-
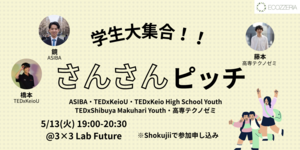
さんさんピッチ 学生団体集合!「ASIBA・TEDx慶應・TEDx慶應高校・高専テクノゼミ」
2025年5月13日(火) 18:00 - 20:30
-

【開催決定!】丸の内サマーカレッジ2025
■オリエンテーション
2025年8月6日(水)18:30-20:00
■メインプログラム
2025年8月13日(水)~8月15日(金)各日10:00-17:30
(15日のみ~18:00) -

【Viva Málaga!】スペイン・マラガの知られざる魅力
#5 スペイン南部に根付く日本の絆――アンダルシアで活躍する日本人と特別な村
イベント
注目のワード
人気記事MORE
- 1
 【丸の内プラチナ大学】2024年度開講のご案内~第9期生募集中!~
【丸の内プラチナ大学】2024年度開講のご案内~第9期生募集中!~ - 2
 【大丸有シゼンノコパン】大手町から宇宙を「望る(みる)」ービルの隙間からみる、星空の先ー
【大丸有シゼンノコパン】大手町から宇宙を「望る(みる)」ービルの隙間からみる、星空の先ー - 3
 大丸有でつながる・ネイチャープログラム大丸有シゼンノコパン 冬
大丸有でつながる・ネイチャープログラム大丸有シゼンノコパン 冬 - 4
 【丸の内プラチナ大学】逆参勤交代コース 壱岐市フィールドワーク
【丸の内プラチナ大学】逆参勤交代コース 壱岐市フィールドワーク - 5
 【大丸有シゼンノコパン】【朝活】大丸有で芽吹きを「視る(みる)」ー春の兆しは枝先からー/まちの四季
【大丸有シゼンノコパン】【朝活】大丸有で芽吹きを「視る(みる)」ー春の兆しは枝先からー/まちの四季 - 6
 3×3Lab Future個人会員~2024年度(新規・継続会員)募集のお知らせ~
3×3Lab Future個人会員~2024年度(新規・継続会員)募集のお知らせ~ - 7
 【レポート】遊休資源が輝く未来へ 〜山形に学ぶ持続可能な地域づくりの挑戦〜
【レポート】遊休資源が輝く未来へ 〜山形に学ぶ持続可能な地域づくりの挑戦〜 - 8
 フェアウッド×家具~ものづくりを通じた自然や生態系への貢献~
フェアウッド×家具~ものづくりを通じた自然や生態系への貢献~ - 9
 指導経験ゼロから日本一のチームを作った「日本一オーラのない監督」が語る存在感と自己肯定感
指導経験ゼロから日本一のチームを作った「日本一オーラのない監督」が語る存在感と自己肯定感 - 10
 【大丸有フォトアーカイブ】第2回 みんなの写真展 2月21日~3月4日
【大丸有フォトアーカイブ】第2回 みんなの写真展 2月21日~3月4日

