
イベント特別イベント・レポート
【レポート】大丸有から考える「ペットフレンドリー」のあり方
第0回さんさんわんわんDAY2024~大丸有からドッグスマートシティを考える~ 2024年12月6日(金)開催

8,11
人々が活動しやすく配慮されたまちである大丸有エリアですが、これまで「ペットとの共生」というテーマが大きく取り上げられることはありませんでした。アクセスが良く、緑も多く、人間にとっては歩きやすいエリアですが、ペットと一緒に入れる施設は必ずしも多くはないのが現状です。
そこで、エコッツェリア協会は、大丸有エリアからペットフレンドリーなまち、社会とはどのようなものなのかを考えていくために、さんさんわんわんDAY2024と題したイベントを開催しました。犬や猫などのペットを飼っている方や好きな方、ペットに関する事業や活動を展開している方などが集まり、ドッグスマートシティの観点から、ペットと共に暮らす環境づくりについて考えていきました。
「ペットフレンドリーな社会」は、ペットを飼っていない人こそが重要
 株式会社PETSPOTの羽鳥友里恵氏
株式会社PETSPOTの羽鳥友里恵氏
まずは、株式会社PETSPOTの羽鳥友里恵氏にご登壇いただき、ペットとの共生社会を目指す上でのポイント、実現する意義や社会にもたらすインパクトなどについてお話しいただきました。
社会人1年目の頃、長年飼っていた愛犬を亡くした際になかなか仕事を休めなかった経験から、「ペットも大事な家族という認識は広がっているのに、社会環境や企業の制度が整っていない現状に戸惑いを感じた」と語る羽鳥氏。ペットと人間が共存できる「ペットフレンドリー」な社会を作ることにより、すべての人が生きやすくなるだけでなく、その取り組みを企業の成長や社会課題解決に結びつけることを目指しています。
同社の具体的な事業内容としては、ペットに関する取り組みを行う企業に対してコンサルティングやブランディング、企業等のペットに関する取り組みや福利厚生に関するアドバイス、ペット関連商品の共同開発、ペットと触れ合うことにより人間が受ける影響の数値化といったものです。
こうした取り組みを通じて、ペットと人が豊かに過ごせる環境を構築することにより、次のような社会的・経済的な効果が期待されています。
①高齢化社会におけるウェルビーイングの向上と医療費負担の削減
②都市の魅力向上と地域経済の活性化、雇用促進
③人々のメンタルヘルス改善と生活の質の向上
④環境への影響と持続可能な社会の実現
⑤地域コミュニティ形成と防犯対策
一方で、ペットフレンドリーな社会は多面的に好影響を及ぼすと考えられる反面、注意も必要です。それは、「ペットとその飼い主だけが暮らしやすければいい、というわけではない」という点です。羽鳥氏は続けて次のように言いました。
「日本でペットを飼っている世帯は2023年時点18%ほどで、マイノリティといえます。そのため、すべての場所をペット連れ可能にすれば良いとは思っていませんし、いかにしてマジョリティの人々が、同じ環境に飼い犬や飼い猫がいることを受け入れられるようにしていけるか、どうすればペットを連れていない人が嫌ではない空間づくりができるかを考えなければなりません。そうすることで、結果的にペットフレンドリーになっていくはずです」
では、ペットフレンドリーな社会を作るにはどのようなアクションが必要となるのでしょうか。羽鳥氏は、「国内において、ペットを飼うことによる心身や社会への影響の可視化」、「ペットを飼っている人と飼ったことがない人の相互理解を深めるために、ペットに触れられる機会を増やす」、「『ペットも家族の一員』という文化を浸透させていくために、自治体や企業において、制度や福利厚生の中にペットに関連した項目を増やしていく」といった動きを挙げ、講演を締めくくりました。
ペットを通じた対話がイノベーションにつながる
 左上:昭和女子大学現代ビジネス研究所研究員/橿原市職員の大賀暁氏
左上:昭和女子大学現代ビジネス研究所研究員/橿原市職員の大賀暁氏
右上:株式会社SHINMEの高野洋氏
左下:株式会社ANIMANECTの飯塚秀幸氏
右下:3×3Lab Futureネットワークコーディネーター田邊智哉子(右)
続いて、パネルディスカッションとグループワークへと移りました。パネルディスカッションに登壇したのは、羽鳥氏に加え、ペットを中心とした成熟社会づくりに取り組む大賀暁氏(昭和女子大学現代ビジネス研究所研究員/橿原市職員)、日本の動物園水族館探求メディア"wizoo"を運営する高野洋氏(株式会社SHINME)、高齢者のペットライフ事業に取り組む飯塚秀幸氏(株式会社ANIMANECT)。モデレーターは、3×3Lab Futureネットワークコーディネーターの田邊智哉子が務めました。
さんさんわんわんDAYの発起人でもある大賀氏は、羽鳥氏の講演について次のように感想を述べました。
「自分とは違う視点で物事を見て考えることは、イノベーションの基本です。そこで、犬や猫という理解しがたい存在がいる環境に身を置き、その子たちが何を考えているのか思いを馳せることは、とてもクリエイティブな行為だと思います。それに、ペットを飼っている人と飼っていない人が意見交換し合えば新しい発見が得られるので、チームワーク形成にもつながると感じます。そのため、人がペットと触れ合うことで得られるメリットを科学的に説明しようとする羽鳥さんの取り組みに賛同します」(大賀氏)
また、大丸有エリアとペットとの関係性についての意見も出されました。羽鳥氏は「このエリアは犬を連れて入れるかどうか分からないお店・施設が多く、ペット可を明確にするためのインフラや制度が欲しい」、飯塚氏は「緑豊かでペットと散歩をしていると気持ちいいものの、働き方とペットの共存は決して簡単ではない」とも話しました。
さらに、大賀氏はペットと共存した働き方について、次のように述べていました。
「オフィス空間にペットがいる環境を整えるには、散歩やご飯、排泄や睡眠などペットのペースに合わせる必要があります。それを実現するには、飼い主が柔軟に動けるように就業時間や就業規則を柔軟に変更する必要があり、経営者側の理解と協力が必要不可欠です」
 グループディスカッションの様子
グループディスカッションの様子
パネルディスカッションの後には、参加者同士がいくつかのグループに分かれ、日頃から抱えているペットに関する課題や職場とペットの関係性について意見交換する時間が設けられました。ここで注目されたのが、「避難所など緊急時のペットの扱い」についての意見でした。ある参加者は次のように話しました。
「地域の中でペットに関する話をすると、『ペットと一緒に避難できる場所を整備してほしい』という意見をよく耳にします。最近ではペットと共用できるインスタントハウスの開発も進んでいますが、自治体側もこの点を意識し、準備する必要があると感じます。また、犬や猫といった一般的なペットだけではなく、例えば爬虫類や昆虫など、苦手とする人もいるペットに対してどこまでケアするのかといったことも、今後は議論を深めていくべきだと思います」(参加者)
ペットを飼っている場合、災害時には在宅避難が推奨されていますが、自宅が損壊した場合などには同行避難が可能となります。しかし、避難所にペットを連れて行くことによってトラブルが発生するケースもあり、ペットとの避難は社会課題となっています。こうした問題に対して、高野氏は次のようにコメントしました。
「避難所にペットの餌が備蓄されているわけではありませんし、ペットの避難に関しては自分たちで何とかしなければならない部分が多いのが現状です。ただ、防災には個人でできることとできないことがありますし、組織でやるべきこと、あるいは組織ではできないことなど、さまざまなレイヤーがあります。一番よくないのはそれらがぶつ切りになってしまうことです。社会全体でカバーできるようにしていきたいです。特に今は防災意識が高まっているので、啓蒙活動や、個人やコミュニティでの備えを進めるには良いタイミングではないでしょうか」(高野氏)
また、「企業経営にペットに関する取り組みを組み込むことで、客観的に評価される指標を作り、株価が上がるようになるとペットフレンドリーが進むのではないか」、「ESG投資の評価項目にペットに関する取り組みが入れば、環境は大きく変わる」といった意見も挙がりました。
 イベント中、とても静かに、飼い主と一緒にイベントに参加したワンちゃんたち
イベント中、とても静かに、飼い主と一緒にイベントに参加したワンちゃんたち
ペットとのおでかけ促進は、ウェルビーイングな社会の醸成につながる
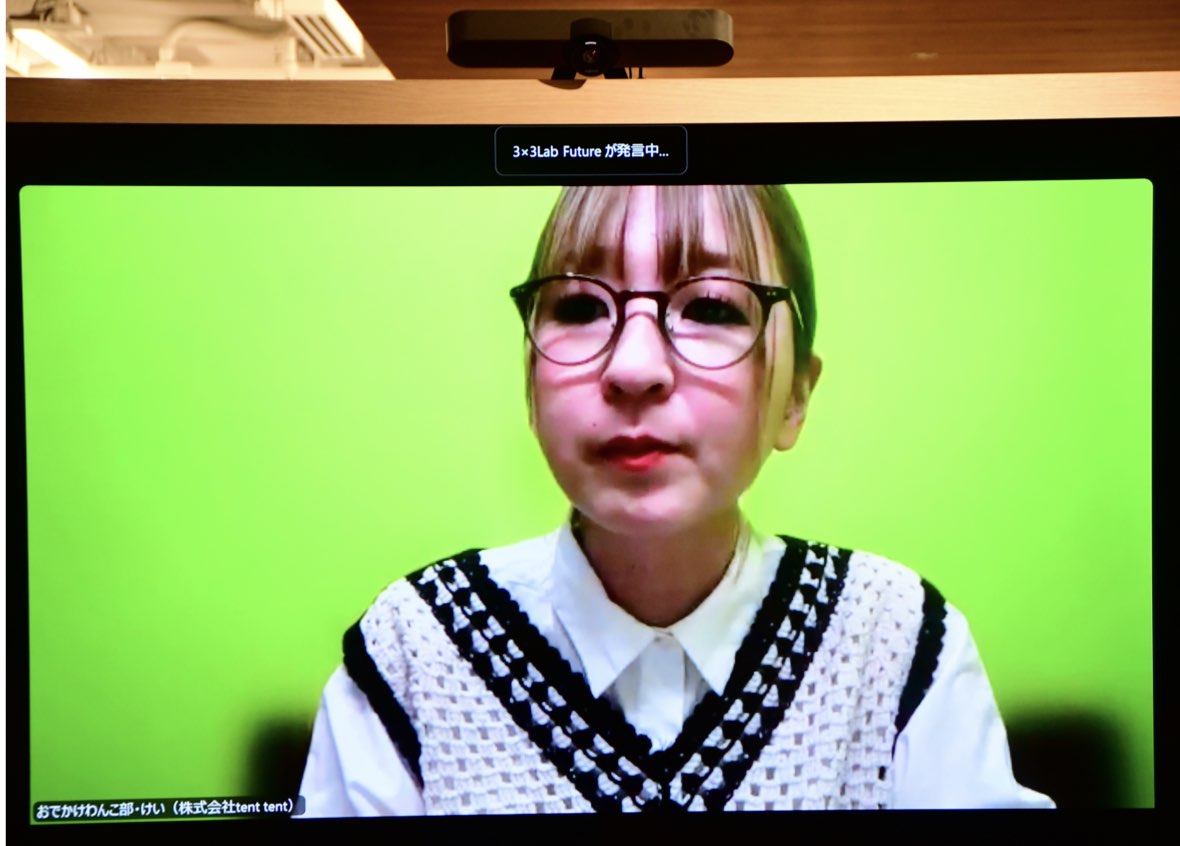 株式会社tent tentの小西恵子氏。この日はオンラインで参加
株式会社tent tentの小西恵子氏。この日はオンラインで参加
最後に登壇したのは、「おでかけわんこ部」という、愛犬とのおでかけ情報メディアを運営する小西恵子氏(株式会社tent tent)です。おでかけわんこ部は、全国のユーザーから提供された情報をもとに、愛犬とお出かけしやすい場所を紹介するというユーザー参加型のポータルサイトで、「ペットとのおでかけ情報が見つけにくい」という課題を解決するサービスです。2019年のサービス開始以降、順調に利用者が増え、自治体や企業との協業も活発に行われています。
このように、人とペットのおでかけを促進することは、人、犬、事業者、社会それぞれに影響を与えることになると、小西氏は話します。
「愛犬とのお出かけは、人の心を豊かにし、愛犬との絆を深めます。飼い主同士のコミュニティが生まれることで、人と社会がつながるきっかけにもなるでしょう。さらに、お出かけをすることで犬も幸福度が上がり、普段とは違った景色やにおいに触れることで、犬としての本能の回復にもなります。事業者にとっては、ペットフレンドリーな施設としてブランディングをすることで、新しいターゲット層の獲得につながり、稼働率や客単価のアップが期待できます。そして、ペットフレンドリーなまちづくりは新たな観光振興の起爆剤となり得るものですから、地方創生にもつながるでしょう」
また小西氏は、「もちろん、施設や交通機関におけるガイドラインの整備、ペットを飼っていない人にとっても快適な空間づくり、動物アレルギー対策など、乗り越えなくてはならない壁も多くあります」と付け加えた上で、こうした領域の知見を持つ企業や人への協力も呼びかけました。

すべてのプログラムを終えたところで、企画者の一人である田邊は、このプレイベントと今後の展望について、次のように話しました。
「当初は飼い主の方々とその愛犬と共に丸の内を散策する計画もありましたが、参加者同士で会話をしたいという意見が多かったため、このようなイベントの形となりました。それだけ、情報交換をしたいというニーズが多いことは大きな気付きでした。ディスカッションも積極的に交わされ、『とにかく自分のペットだけを大切にしたい』という内向きな考えではなく、『私たちの家族をどうやってまちに溶け込ませていくか』という視点で議論できたのも大事なことだと感じています。その他にも、防災やまちづくり、交通機関等による移動の観点など、さまざまな意見が出ました。それぞれのキーワードと大丸有エリア、あるいはこの地域の企業と連携の形を探りながら、再びこうした場をセッティングしていきたいと考えています」(田邊氏)
大丸有エリアからペットフレンドリーについて考えていくことで、日本全体に波及していくきっかけになることが期待されます。「さんさんわんわんDAY」の本格始動にご期待ください。
おすすめ情報
イベント
注目のワード
人気記事MORE
- 1
 丸の内プラチナ大学2025 逆参勤交代コース特別講座 飛騨ナイト
丸の内プラチナ大学2025 逆参勤交代コース特別講座 飛騨ナイト - 2
 【丸の内プラチナ大学】2025年度開講のご案内~第10期生募集中!~
【丸の内プラチナ大学】2025年度開講のご案内~第10期生募集中!~ - 3
 【大丸有シゼンノコパン】ビルや樹々の隙間に星空を「望る(みる)」 ~「すばる」や「月」はどこにある?~【まちの星座】
【大丸有シゼンノコパン】ビルや樹々の隙間に星空を「望る(みる)」 ~「すばる」や「月」はどこにある?~【まちの星座】 - 4
 【大丸有シゼンノコパン】色彩豊かな冬の鳥を「観る(みる)」 ~極寒の今こそ絶好の"鳥"日和!~【まちの生きもの】
【大丸有シゼンノコパン】色彩豊かな冬の鳥を「観る(みる)」 ~極寒の今こそ絶好の"鳥"日和!~【まちの生きもの】 - 5
 大丸有でつながる・ネイチャープログラム大丸有シゼンノコパン 冬
大丸有でつながる・ネイチャープログラム大丸有シゼンノコパン 冬 - 6CSV経営サロン2025 第3回「資源循環の出口、有機性資源のアップサイクル」
- 7
 【丸の内プラチナ大学】逆参勤交代コース 高知県須崎市フィールドワーク
【丸の内プラチナ大学】逆参勤交代コース 高知県須崎市フィールドワーク - 8【丸の内プラチナ大学】逆参勤交代コース 北海道上士幌町フィールドワーク
- 9
 【レポート】関係資本の力を最大化する コミュニティデザインと持続的価値創造
【レポート】関係資本の力を最大化する コミュニティデザインと持続的価値創造 - 10
 3×3Lab Future個人会員~2025年度(新規・継続会員)募集のお知らせ~
3×3Lab Future個人会員~2025年度(新規・継続会員)募集のお知らせ~





