

NTTデータの吉田淳一氏は、主にインバウンドや地方創生関連で、経産省、観光庁のプロジェクトメンバーとして参画しつつ、年間70本以上ものプレゼンを全国で実施している。映像を駆使したそのドラマチックなプレゼンは、「吉田劇場」とも呼ばれ、多くの人を惹きつけてやまない。また、3×3Laboでも、いくつもの共同イベントを開催しており、その活動の内容は実に多彩だ。3×3Laboの仕掛け人、田口真司氏が聞く対談シリーズ。今回はNTTデータの吉田氏をお招きし、「吉田劇場」のルーツや、今吉田氏が取り組んでいる"コト"、目指すところについてお聞きした。
インバウンドに必要なのは「コト・コミュニケーション」

田口:吉田さんは年間70本以上講演をされていると聞いていますが、今、現在は、どういったことをされているのでしょうか。
吉田:今は宮崎をはじめさまざまな地域から地方創生に関するプロジェクト組成の相談をいただいています。
たとえば、グリーンツーリズム関連で、「全国の『農家民泊』の活性化をどうするか」について某省庁より意見を求められました。地方でムーブメントとして農家民泊が起きているけれど、行政サイドとしてどう仕切ればいいのかわからない。個の集団が全国に散っている中で、お互い何をやっているか、わからない状況なんです。
 吉田氏は、全国どこでも、何時でもプレゼン出来るよう旅芸人道具としてPCに接続できるスピーカーやボリュームチェンジャーなどを常備しているというそういった点で、宮崎プロジェクトは、東京の丸の内ワーカーと地方の農家民泊の方々がコミュニケーションを取るにはどうすれば良いかにチャレンジしているので、行政サイドも興味を持って頂いております。
吉田氏は、全国どこでも、何時でもプレゼン出来るよう旅芸人道具としてPCに接続できるスピーカーやボリュームチェンジャーなどを常備しているというそういった点で、宮崎プロジェクトは、東京の丸の内ワーカーと地方の農家民泊の方々がコミュニケーションを取るにはどうすれば良いかにチャレンジしているので、行政サイドも興味を持って頂いております。
また彼らの思考の中には、今まで「IT」というキーワードが入っていませんでした。
そこで、今回は、自身がこだわっているキーワード「空間共有」の解説をしました。遠く離れている人同士でも、ITを使うことでなんとなくお互いの気持ちがわかりあえる。「まず、お互いを知ろうよね」という部分が、今どこでも必要になってきています。この部分を広めていきたいと考えています。
田口:自治体の方からのお話が多いのですか?
吉田:自治体もありますが、企業も結構あります。たとえば、全国チェーン展開している某アパレルブランドからは、売っているものは同じだけれど、「地域に根差した個店」になるために、どうすればよいか、といった話もきています。
田口:今までの20世紀型は、首都圏側でブランドを一つ作って金太郎飴的に同じものを作って、地方で売ってきた。そのほうが、大量生産で効率がよかった。でも、今はそこのつまらなさや限界に気づいてきたんですね。
吉田:そうなんです。それから、今やっているメインの仕事では、インバウンド関連もあります。今、訪日外国人の「爆買い」と言われてますけれど、爆買いは一時的なもので、あくまで「コト・コミュニケーション」、つまり体験と相互理解が重要となってきます。そのためには、送客をどうすればいいか。送客された際に受ける側が「何をすればいいのか」「どうもてなせばいいか」って意外とできていないし、とても重要なんです。
今、アジアの人は必ず東京で買い物をしますが、最近は、ほかの人がやっていない「コト体験」をやりたい。やったことを母国の友だちに自慢したいという心理が働いています。インターネットで探せる情報は少ないし、発信しているところも少ない。
たまたま我々がやっている宮崎県小林市(西諸地域)のプロジェクトでは、フランス人を起用した映像で、少しずつ名が知られるようになったかもしれません。でも、まだまだ、小林市を含め、地域の"コト"っていうのは、情報発信ができていない。そういったところをお手伝いできないかと考えているところです。
「タダ」でもっとも効果的に日本をアピールする方法
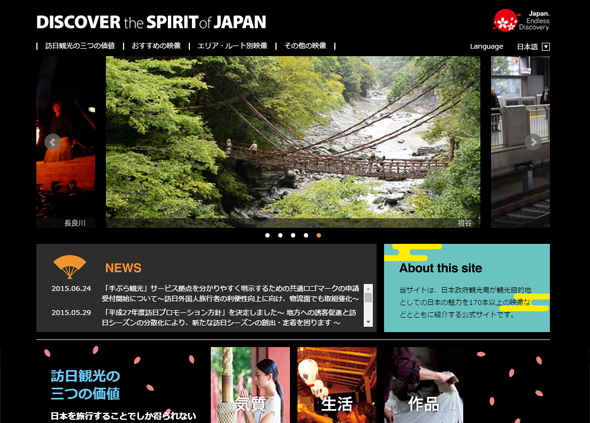 ビジット・ジャパンのキャンペーンサイト
ビジット・ジャパンのキャンペーンサイト
田口:地方創生や吉田劇場はいつぐらいから始められているんですか。
吉田:2011年に観光庁が、既に「ビジット・ジャパン・プラス」のワーキングを立ち上げていた際に、飛び込みでメンバーを志願したところからはじまります。まだ当時は、「インバウンド」という言葉があまり知られていないころです。その後WGメンバーと共にジャパンショッピングツーリズム協会を発足して、観光庁と連携した官民連携のプロモーションをひたすら推進して、今のインバウンドブームを迎えたような感じです。
それ以前も、少子化が進む中、日本は何で食べていくのか。どんどん人口減少し、旅行もしなくなる。そうした中で、外から胃袋を持ってきて日本の食を食べてもらえばいい、とずっと考えていましたね。そのそもそものきっかけは学生時代にさかのぼります。
僕は、バックパッカーでアメリカとオーストラリアの全州を回りました。1日10ドルとか、15ドルで、寝泊まりも食も全部まかなう旅行。日本でいうところの「青春18きっぷ」を買って、40~50日かけてバスでぐるぐる回ったんです。
そこで感じたことは、「日本人ってスゴイ」ということ。特に感性や五感の細やかさ。
 たとえば、食です。僕はずっとユースホステルに泊まり、食はすべて自炊していました。貧乏旅行ですから、近所のスーパーで賞味期限の過ぎた安い食材を買って、同じ宿泊者にふるまいながら、コミュニケーションしていました。初めての日本人と初めての日本食、文化に触れた人たちは、異口同音に「ヘッ~美味しい!」「毎日、こんな美味しいもの食っているのか」って驚く。ほんの些細なおもてなしですが、そこで日本文化の奥深さを自分が逆に痛感するんですね。「日本は外国人」を受け入れるべきだな、と思いました。
たとえば、食です。僕はずっとユースホステルに泊まり、食はすべて自炊していました。貧乏旅行ですから、近所のスーパーで賞味期限の過ぎた安い食材を買って、同じ宿泊者にふるまいながら、コミュニケーションしていました。初めての日本人と初めての日本食、文化に触れた人たちは、異口同音に「ヘッ~美味しい!」「毎日、こんな美味しいもの食っているのか」って驚く。ほんの些細なおもてなしですが、そこで日本文化の奥深さを自分が逆に痛感するんですね。「日本は外国人」を受け入れるべきだな、と思いました。
それから、海外でバックパッカーや現地の人たちと接して強く感じるのは、彼らの日本(人)に対する先入観、認識がとても表面的で、きっちりと日本のナショナリティ含めて情報が伝わっていない点が、とてももどかしく思えていました。
それで、2010年ごろから、会社の仕事は全然関係なしに(笑)、ふらふら地方を回ったりして、「これは仕事になるし、社会貢献もできる」という思いを深めて、徐々に行動を起こしてきました。
最初、飛び込みで観光庁の門を叩いたら、「NTTデータさんは観光と関係ないでしょ」と冷たく言われましたが、折角なので「一度だけプレゼンの機会を作りますので、やってみてください」とチャンスを頂きました。
それで、旅行業界を仕切っているそうそうたる皆さまの目の前で、自身の思いの丈をミニ「吉田劇場」でぶつけてみました。プレゼンの後、皆さんが名刺交換で列なして頂いてうれしかったですね。それを見た観光庁の人が「こいつもビジット・ジャパンのプロジェクトのメンバーに入れよう」と考えてくれたのだと思います。
 当日のプレゼン資料より
当日のプレゼン資料より
プレゼンでは、観光分野に携わっていない素人目線で、慣例を無視したさまざまなアイデア提案をしました。例えば、「見てよし、食べてよし」のオールジャパンで和菓子のフェスティバルを計画して、それをニューズウィークの表紙などで取り上げ、一気に知名度を上げていくという少しとがった提案をしたような気がします。
以来、いろんな人から話を聞いたりして、「地域創生っておもしろいな」と思うようになりました。まだまだ始めたばかりです。
田口:観光庁の門を叩いたところをもう少し知りたいのですが、鎌倉投信の新井和宏さんが、「自分がこれをやらなければいけない、という"勝手な使命感"が下りてきた」とおっしゃった。それをやらない自分が想像できない、と。吉田さんはどうですか。
吉田:ほかの人もできるかもしれないけれど、自分が動けば、こういう動き方ができるし、こういう見せ方ができる、こういう世界観が作れるんじゃないかと思いました。
僕、会社の中で「暴走族吉田」って言われてまして(笑)。考えて戦略を立ててから動くというよりもむしろ、まず人と会ってみて、感じていることを話す。そうすると、自分が考えていることは意外と間違っていないかも、って感じることがあるんです。
田口:「自分が正しい」と信じられるときってありますよね。
吉田:前に田口さんが、Facebookの中で、「コトをやろうとするなら、その気があって、前向きで、決してネガティブじゃなく、オープンマインドでやろう、という人たちと話したほうがいい。そのほうがスピード感がある」と書いていましたね。
僕もその通りだと思っています。
自分で発信していると、なんとなく同じことを感じる人が集まってくる。最初は、会社の中で、「観光とか、インバウンドって、なにそれ?」っていう感じで、意外と冷めた目で見られた。それが、5年間くらいやってきて、今は、社内外で少しずつではありますが、「観光は吉田」「インバウンドは吉田」「地方創生は吉田」と自然と言われるようになってきました。
それは僕だけじゃできないことで、いろんな人との関係があるからこそなんだと思っています。某省庁の話も、ここ(3×3Labo)で情報発信をしてくれたからつながっている。ここで撮った写真を会社の受付に持ってきて、「この人に会いたい」と言ってくる方もいるんです(笑)。今、情報発信はすごく大事ですね。
田口:伊藤園の笹谷さんは「発信型CSV(共通価値の創造)」とよく言っています。「いいことをやっていても、発信をしないと伝わらない。どんどん発信していこうよ」と。
日本人的美的感覚で内に秘めているのもいいんだけれど、いいものは発信して伝えていかないと広がらないですよね。
吉田:伝え方も大切です。目上の人、若者、女性......と人によって言い方を変えないと伝わらないことがあります。でも、今吉田劇場をやっている中で、ビジュアルに見せるとわりとそこが広くなる。みんなが見て感じることが共有化、共通化できる。だから今、文字よりも映像で見せるというスタイルを取っているんです。
 分かりやすい吉田氏のプレゼン資料の例
分かりやすい吉田氏のプレゼン資料の例
- 続きを読む
- 無駄な経験はない
無駄な経験はない
 その筋で「吉田の4象限」と呼ばれるインバウンドのロジック
その筋で「吉田の4象限」と呼ばれるインバウンドのロジック
田口:ITの会社にいらして、「人に伝える、伝え合う」というところを掘っていくと、映像に行きつくのかもしれません。吉田さんは、ネタ仕入れもすごいですね。ものすごく専門誌を読まれているし、情報収集能力が半端じゃない。
吉田:でも、まだどうしても足りていません。その点、田口さんは多くの人に会っていて見ていて素晴らしいと思います。私はいろんな媒体から入ってきた情報を精査して、世の中の動きがどうなっているかを考えている。人の体験を通した情報は重みが違う。田口さんはそのあたりのしっかりとした生の情報をもっている。そこがすごい。
田口:ありがとうございます。吉田劇場を見ていると、人を楽しませたいという欲求が強いと感じます。
吉田:そう、自分の行いが、人を笑顔に変える、笑顔が見られるって素敵ですよね。僕は昔から人を楽しませるのが好きでした。大学のときは、社会を見たくてアルバイトをたくさんやったのですが、特に大学時代、ちょうどディズニーランドがオープンの時に、2年間ほど、キャストとして働いた経験が、今のサービス創造に対する感性の元になっています。
 田口:若い人たちや人事部の人に今の話を聞かせたいですね。今はみんな若いときから専門性を高めようとします。そのほうが即戦力になるから。企業側も専門的なことをやってきた若者がいいと思っている。でも、それだけじゃないと思います。私も前職はネットワークのエンジニアをやっていましたが、やってきたことは、今も何かしら使える。いつか、使えるかもしれない経験を若い時にしていると、あとあと効いてきますよね。
田口:若い人たちや人事部の人に今の話を聞かせたいですね。今はみんな若いときから専門性を高めようとします。そのほうが即戦力になるから。企業側も専門的なことをやってきた若者がいいと思っている。でも、それだけじゃないと思います。私も前職はネットワークのエンジニアをやっていましたが、やってきたことは、今も何かしら使える。いつか、使えるかもしれない経験を若い時にしていると、あとあと効いてきますよね。
吉田:そうですね。とにかくいろんな経験の積み重ねが今の自分を作っていますからね。当時、ディズニーランドのアルバイトでもいろいろ学びました。
オリエンタルランド(ディズニーランド)は、夢を提供する企業・場です。ゲストのお客様の良い思い出つくりをお手伝いすることに関しては、徹底しています。例えばプロのカメラマンを講師に招いて、1万人のスタッフに対して、カメラ教室を開いたんです。家族でディズニーランドにくると、必ず記念撮影しますよね。でも、誰かがカメラマンになると、一人だけ被写体から抜けてしまいますよね。それって、キャストからするととても悲しい光景なのです。そこで、スタッフは全部カメラを使えるようにして、必ず1日100枚、来たゲストの写真を撮ってあげなさい、と言われました。撮ると記念になりますから、家に帰ってからいろんな人に見せますよね。そうするとディズニーランドはお金を払わなくても、ものすごい宣伝になるわけです。現代のクチコミの原点です。
田口:賢いですね。
吉田:インターネットで考えると、1日平均5、6万人の人が最低でも1枚写真を撮ると月間にすると何百万にもなって、その画像が世界をかけめぐるわけです。
オリエンタルランドで学んだのが、ゲストの皆さんが経験をどうやって伝えるか?
言語体系で整理したことがあります。
英語圏の人は、たとえば、英字新聞のように文字がたくさんあって写真がほんの少し載っているようなもの。日本人は、意外と文字と写真のバランスがいい。但し、撮るのは、料理だけとか、商品だけ掲載されるのが普通。
驚いたのは、中国、韓国、台湾、香港などのアジアの人は、必ず自分が被写体に入っていること。30年前から自撮り文化が普通にあったんですね。「I LOVE ME」の、この世界観があると、自然と情報発信されます。世界の国や地域によって、表現の仕方が異なることを、当時オリエンタルランドで学びました。
田口:30年前に学んだとは早いですね。
吉田:僕が経験したことを実現したのが、渋谷のあるファッションのショップです。外国語の話せないカリスマ店員に、「アジアの人が来たら、3回試着させなさい。そして、一回一回彼女たちが持っているスマホで、着た写真を撮ってあげなさい」と伝えました。
アジアの人たちはそれを友達にすぐに見せようとします。中国人であれば、Wi-Fiを通して、「シナウェイボー(新浪微博)」というソーシャルメディアに上げます。日本のLINEみたいなもので、1人あたり平均500人の友だち登録されているので、写真をアップしたら、さあ~何が起きるか分かりますか? スマホを通じてリアルタイムの会話がはじまります。
「今、日本にいるの?」「そのワンピース、もっとほかの色ないの?」「サイズはある?」って。結果として、1人のお客さんが何十人分もの買い物をしていく。売り上げは、どっかんと上がっていきます。
これは、当時、ディズニーランドで学んだことの応用です。商売で人にどうやって情報を伝えていくかのベースになっています。企業側からすると、広告宣伝費を払わずに、彼女の勇気と行動力によって、お客さんが売り上げを上げていく。この仕組みを地方で応用できないかと思っています。

田口:すごくいいですね。IT業界って、「ITを使うと人件費が安くなるよ」ってすぐにコストダウンに走る。受けた方も説得しやすい。初期投資は必要だけれど、3年でペイオフしますと。それをやっていくと、最終的にはITもいらない、というところに行き着いてしまう。今は個別サーバーではなく、クラウドでシステム構築するから、人はどんどんいらなくなる。自分たちのフィールドを自ら壊していったのがIT業界だと思っています。
一方で、Appleとか、今の吉田さんの話には、ITの可能性を感じます。価値を高める、広げるというところに、いち早くIT業界がいかないと共倒れになってしまう。大げさな話じゃなくて、吉田さんのやっていることはIT業界も変えていくことだと思います。
吉田:僕はあまりITの話はしないんです。正直なところ、インバウンドの領域では、ITを使っての仕組みまで、みんなの気持ちもノウハウも経験もまだ行き着いていない。カリスマ店員の話は、確かにそれを実現するために必要なものはWi-Fiです、という話にはなるんですけれど、全体の中で中心的な話ではない。
「Wi-Fiってなぜ必要なんですか」って聞かれると、僕はこう答えています。
アジアの人たちは自分が体験したことを自慢したい。「こんな人と会った」「こんなおいしいものを食べた」と一秒でも早く人に伝えたい。それが無料でできるのがWi-Fiで、情報を集めるというより、むしろ情報を発信するために必要なんです。爆買いのお客さんが情報を発信すれば、Wi-Fiのコストは一気に飛びますよ、と。そうすると、ストンと腑に落ちる。
これを知っている人、伝えられる人は、地方にはまだ少ない。だから、個人巡業をして啓蒙活動をしています。僕ができるのはきっかけづくり。あとのアイデアは地方の人に考えてもらう、ということをしています。
東京を地方同士をつなぐハブにしたい
 吉田氏のプレゼン資料より
吉田氏のプレゼン資料より
田口:今後、地方の情報発信がうまくなってきたと仮定して、地方ごとの色をどう出していくかが、課題になってくると思います。「水がおいしい」「空気がきれいです」「夜空がきれいです」「地元産の野菜がおいしいです」と、どうしても今は似てくる傾向があります。
もし、吉田さんが地方創生大臣だったら、それをどうお互いすみ分けていきますか? あるいは勝ち負けを作っていくのか。いろいろやり方はあると思う。
僕の答えを先に言ってしまうと、「足るもの」「足らないもの」が、それぞれの地域にあって、地方と地方がつながることで相乗効果が出てくると。東京がやることはきっかけづくりで、地方と地方がつながるためのハブになれればいいと思っています。お見合いじゃないけれど、その後は「二人でよろしく」というようにしていきたい。吉田さんが考える先々の地方創生はどういう感じですか。
吉田:僕は「今あるもの」を生かしていくことだと思います。地域性にしろ、人にしろ、文化にしろ、言葉にしろ、今は無形なものであっても、地域には非日常を感じられるものがある。どの地域でも活性化はできると思っています。
田口:お話を聞いていると、吉田さんのベースにあるのは、「おらが町がほかの町より秀でる」ということじゃなくて、「うちの町はこんなことやっているよ」というアイデアを共有して、それを一緒にやってもいいし、ほかのことをやってもいいよと。そこに笑顔がつながっていく、という気がします。
吉田:今、自治体が力を入れているふるさと納税にしろ、一つの地方ではできない商材っていうのがある。地方と地方の商材を組み合わせて、ふるさと納税の品物にしましょうとか。
田口:おもしろいですね。ふるさと納税でフルコースを作るとか。
吉田:無限の組み合わせができます。たとえば、10万円を寄付した人には、宮崎牛&イベント体験にご招待とか、物理的なものとコト・コミュニケーションを組み合わせて、楽しく見せる。それはアイデア勝負だと思っています。そのときに大事なのが、僕らのITでいう「デジタル情報を伝える」ということと、それを何度も見て感じてもらう「アーカイブ環境」を整えるということ。それはあくまでも黒子なんですが、ITがやるべき範囲なのかなと思っています。記録を残すことが大事なのです。
農家民泊は人の人生を変える

吉田:最後にひとつお話ししたいことがあります。今、年に一度、NTTデータがお客様を呼んで、「世の中がこうなります」とお伝えする場がある。そこで、私も、先日、ブースを担当して、「地方がコミュニケーションを取るにはどうしたらいいか」ということで、東京と宮崎をつないで中継をしたんです。
向こう側にいるのは、宮崎の農家民泊の事務局の方をはじめとする関係者の方々でした。僕は後で知ったのですが、そのとき、モニターの脇にいた宮崎の方々はみなさん大泣きしていたらしいんです。宮崎のことを東京の人がこれだけ一所懸命に伝えてくれている、と。大事なことは、こういう「気持ちを伝える」ことなんですね。
そのときに併せてお話ししたのは、宮崎大学の女子学生の話です。
その学生は、高校生の頃、高校を続けるかどうか迷っていた頃に、母親に連れられて宮崎の農家民泊に2泊3日で泊まったそうです。そこで、農家の人たちと触れ合うことで、自分の考えが180度ひっくりかえされた。その恩返しとして、農家民泊をできる範囲で支えていきたいと、宮崎大学の農学部に入って、卒論を「農家民泊」にした記事が、宮崎の地元新聞で掲載されていました。
つまり、農家民泊、人との出会い、コミュニケーションが人の人生を変えたんです。
農家民泊の何がいいかというと、宮崎の農家民泊の会長がおっしゃっていたのは、「野菜を採ったり、土と戯れたり、自然を満喫したり、美味しい料理を食べたりと非日常の感動がありますが、それよりも、農家のおじいちゃんやおばあちゃんが、自分たちの考えを話すと耳を傾けて受け入れてくれる。ちゃんと親身になって会話してくれる、そこに感動と感謝が生まれるんです」ということ。だから、修学旅行で体験した学生たちが、卒業証書を抱えて農家民泊にまた来るらしいんです。「卒業したよ」って。農家側の人たちは、自分たちがこれまで歩んできた農家の文化を、若い人たちに伝えられることに喜びを感じているということです。
観光って、その人に会うことが究極の旅であり、何時でも会える人がいるからリピートするんですよ。
もう一つの例を紹介すると、地鶏を絞めてさばいているところを若い人たちが見たりすると、自然と手を合わせるそうなんです。鶏のささみのパックじゃないもの、まさに生きている鶏を今絞めたものを食べるということに対する申し訳なさや、命の大切さに対して自然と拝む。これは都会では絶対にありえないことだと思いますし、これを映像化して、人に伝えていくことが、文化として、観光資源としても大事なものだと思っています。
それをITで知ってほしいと思っています。
一方でリアルに情報を伝えることも重要だと思いますから、3×3Laboのリアルな場とITの技術を組み合わせていくことで、もっと価値が出てくると感じています。
田口:それはいいと思います。新施設「3×3Lab Future」も活用して、どんどん新しい価値を生み出せればと思います。今日はありがとうございました。


吉田 淳一(よしだ・じゅんいち)
株式会社エヌ・ティ・ティ・データ イノベーション推進部 オープンイノベーション事業創発室 部長
1987年NTT入社。現在NTTデータ イノベーション事業推進にてインバウンド事業 の創出並びに世界のICTトレンド・観光等に関する講演活動『吉田劇場』を展開中。
■社外
○観光庁「ビジットジャパン+」の東京・大阪WGメンバー(~2013)
○ジャパンショッピングツーリズム協会 理事
○外国人向け免税制度を考える協議会 副会長
○経済産業省「おもてなしタスクフォース」メンバー(2014)
○NICT(総務省)グローバルコミュニケーション開発推進協議会メンバー
関連リンク
おすすめ情報
注目のワード
人気記事MORE
- 1
 【丸の内プラチナ大学】2024年度開講のご案内~第9期生募集中!~
【丸の内プラチナ大学】2024年度開講のご案内~第9期生募集中!~ - 2
 【大丸有シゼンノコパン】大手町から宇宙を「望る(みる)」ービルの隙間からみる、星空の先ー
【大丸有シゼンノコパン】大手町から宇宙を「望る(みる)」ービルの隙間からみる、星空の先ー - 3
 大丸有でつながる・ネイチャープログラム大丸有シゼンノコパン 冬
大丸有でつながる・ネイチャープログラム大丸有シゼンノコパン 冬 - 4
 【丸の内プラチナ大学】逆参勤交代コース 壱岐市フィールドワーク
【丸の内プラチナ大学】逆参勤交代コース 壱岐市フィールドワーク - 5
 【大丸有シゼンノコパン】【朝活】大丸有で芽吹きを「視る(みる)」ー春の兆しは枝先からー/まちの四季
【大丸有シゼンノコパン】【朝活】大丸有で芽吹きを「視る(みる)」ー春の兆しは枝先からー/まちの四季 - 6
 3×3Lab Future個人会員~2024年度(新規・継続会員)募集のお知らせ~
3×3Lab Future個人会員~2024年度(新規・継続会員)募集のお知らせ~ - 7
 【レポート】遊休資源が輝く未来へ 〜山形に学ぶ持続可能な地域づくりの挑戦〜
【レポート】遊休資源が輝く未来へ 〜山形に学ぶ持続可能な地域づくりの挑戦〜 - 8
 フェアウッド×家具~ものづくりを通じた自然や生態系への貢献~
フェアウッド×家具~ものづくりを通じた自然や生態系への貢献~ - 9
 指導経験ゼロから日本一のチームを作った「日本一オーラのない監督」が語る存在感と自己肯定感
指導経験ゼロから日本一のチームを作った「日本一オーラのない監督」が語る存在感と自己肯定感 - 10
 【大丸有フォトアーカイブ】第2回 みんなの写真展 2月21日~3月4日
【大丸有フォトアーカイブ】第2回 みんなの写真展 2月21日~3月4日





