

日本の伝統産業の技術を活かしてベビー・キッズ向けの商品づくりを手掛けている「和える」の代表取締役 矢島里佳さんに、その志と伝統文化への思い、文化を継承するために必要なことを聞いた。
和える
部活や取材を通じて、
日本の伝統産業の素晴らしさに触れる
―矢島さんが代表を務める「和える」では、子ども向けの商品に日本の伝統産業の技術を取り入れるという、今までなかった取り組みをされていますね。なぜ、伝統産業に目を向けられたのですか?
私が最初に日本の伝統産業品に触れたのは、中学・高校時代に所属していた茶道や華道の部活動を通じてでした。その際に感じていたのが、茶室に入ると心が落ち着く、ということ。なぜ、落ち着くのかと考えてみると、茶室はすべて手仕事が活きた伝統産業品で構築されているからなんですね。でも、今の若い人たちはこうしたモノがどうやってつくられているのか、どうやって使うのかを知らない。日常で触れる機会がほとんどないからです。しかも、そういう世代がすでに子育てを始めています。このままでは日本の伝統産業が廃れてしまうと感じ、なんとかして、若い人たちに日本の伝統産業品について知ってもらう機会をつくり、次の世代につなぎたいと考えるようになったのです。
しかも、伝統産業の現場には、20〜40代くらいの若い世代でがんばっている人が少なくないことに気がつきました。そこで、若い職人さんたちの仕事ぶりを知ってもらおうと、19歳の時に旅行会社に企画書を持ち込んだのです。これが採用されて雑誌に連載をもたせていただくようになり、3年間にわたりライターとして職人さんたちを取材して回りました。現在までの6年間で出逢った職人さんは、徳島の本藍染、愛媛の砥部焼、石川の山中漆器など、さまざまなジャンルにわたり、約180人を超えています。
伝統産業が廃れようとしているのは、
触れる機会がないから
―その後、大学卒業と同時に和えるを設立されたわけですが、どういうきっかけがあったのですか?
職人さんに会うと、皆さん口を揃えて、「このままでは伝統産業が衰退してしまう」とおっしゃるんですね。しかし、現場には若い方がいるだけでなく、素晴らしい技があって、私にとっては魅力的なものばかりでした。そこで、私が出逢った大好きな職人さんたちに私が欲しいものをつくっていただけたら、と思ったのがきっかけです。
 そして、具体的に何をつくってもらおうかと考えているときに、現在、和えるの人気商品「愛媛県から 砥部焼の こぼしにくい器」をつくっていただいている、砥部焼の職人さんと出逢ったのです。この方は、以前から子ども向けの商品をつくっていらっしゃいました。これらの商品は、ご自身のお子さんのパパ友さん、ママ友さんから、子ども向けのいい器がないからつくって欲しいとお願いされて手掛けるようになったのだと言います。それを聞いて、当たり前のことに思い至ったのです。考えてみると、伝統産業品って大人向けの商品ばかりですよね。それでは、若い世代に引き継いでいくことなんてできるはずがない。私自身、茶道・華道以外でそうしたものに触れる機会がなかったわけですから。知らないものを欲しいとは誰も思わないでしょう。
そして、具体的に何をつくってもらおうかと考えているときに、現在、和えるの人気商品「愛媛県から 砥部焼の こぼしにくい器」をつくっていただいている、砥部焼の職人さんと出逢ったのです。この方は、以前から子ども向けの商品をつくっていらっしゃいました。これらの商品は、ご自身のお子さんのパパ友さん、ママ友さんから、子ども向けのいい器がないからつくって欲しいとお願いされて手掛けるようになったのだと言います。それを聞いて、当たり前のことに思い至ったのです。考えてみると、伝統産業品って大人向けの商品ばかりですよね。それでは、若い世代に引き継いでいくことなんてできるはずがない。私自身、茶道・華道以外でそうしたものに触れる機会がなかったわけですから。知らないものを欲しいとは誰も思わないでしょう。
この気づきがきっかけとなって、将来生まれてくる日本の子どもたちのために、職人さんと一緒に何かものづくりができないかと思うようになりました。せっかく日本に生まれてくる以上は、日本のモノで「ようこそ」と言って祝ってあげたいですよね。そういう私の想いを職人さんたちにお伝えすると、皆さん共感してくださり、一緒にやろう!と言ってくださったのも、大きな後押しになりました。
常識にとらわれることなく、
自分の感性に正直な経営をしたい
ちなみに、会社名の「和える」というのは、お世話になったある方から学生時代にいただいた名前なのですが、起業する際にピッタリの名前だと思って使わせていただくことにしました。あくまでも「混ぜる」じゃなく、「和える」。何かの商品に人気キャラクターをただくっつけるのは混ぜるでしかないと思うんですね。古き良き伝統や先人の知恵と、今を生きる私達の感性や感覚、両方の魅力的な部分を引き出し、それらを和えることで革新的なものが生み出されるとも思っています。つくること自体は職人さんにお任せして、つくること以外のことをすべてお引き受けし、お客さまにものづくりの背景や物語をお伝えしていくのが、和えるの役割だと思って活動しています。
―「和える」うえで、とくに大事にされていることは何ですか?
 0から6歳の伝統ブランド「和える」のホームページ感性です。目指すは「感性経営」。常識や非常識、従来の貨幣経済の価値観にとらわれることなく、「無常識」のなかで自分たちの感性に耳を傾けながら経営をしていきたい。確かに伝統産業品は不便な部分もあるかもしれません。ほとんどが電子レンジで使えないし、食洗機にも入れられません。でも、これらの商品は一生モノで、「ホンモノ」なんですね。私たちのホンモノとは、"本"当に子どもたちに贈りたい日本の"物"ということ。だからできるだけ自然の物を使って、職人さんが時間をかけて一つひとつつくっています。また、漆が剥げたら塗り直しもできるし陶器や磁器が欠けたりすれば、金継ぎでお直しもできるのです。そう考えると、それなりの値段がするのは当然ですよね。しかも、これらの商品をもし自分でつくろうと思ったら、何年もかけて修業するところから始めなくちゃいけないわけですから(笑)。
0から6歳の伝統ブランド「和える」のホームページ感性です。目指すは「感性経営」。常識や非常識、従来の貨幣経済の価値観にとらわれることなく、「無常識」のなかで自分たちの感性に耳を傾けながら経営をしていきたい。確かに伝統産業品は不便な部分もあるかもしれません。ほとんどが電子レンジで使えないし、食洗機にも入れられません。でも、これらの商品は一生モノで、「ホンモノ」なんですね。私たちのホンモノとは、"本"当に子どもたちに贈りたい日本の"物"ということ。だからできるだけ自然の物を使って、職人さんが時間をかけて一つひとつつくっています。また、漆が剥げたら塗り直しもできるし陶器や磁器が欠けたりすれば、金継ぎでお直しもできるのです。そう考えると、それなりの値段がするのは当然ですよね。しかも、これらの商品をもし自分でつくろうと思ったら、何年もかけて修業するところから始めなくちゃいけないわけですから(笑)。
ホンモノを取り入れることが文化都市への道
―和えるの試みは、日本の伝統産業を見直す大きな気づきを与えていると思うのですが、一方で、まだ、巷ではそうした試みはさほど多くはありません。とくに東京には、日本の文化を感じ取れる場が少ないという指摘もありますが、いかにして現代の東京にそういうものを取り入れていったらいいと思われますか?
 幼い子どもでもこぼしにくい器(愛媛・砥部焼、徳島・大谷焼、石川・山中漆器)東京は日本の玄関口でありながら、日本のホンモノを探したとしても、観光客が行くような場所に並べられているものは「日本ぽい」お土産物がほとんどだと思います。なんとなく日本風のものをつくっておけば外国人の人たちが喜ぶだろう、という発想でつくられた観光地も多いように感じます。こうした場では、残念ながら、私が本当に外国人の人たちに贈りたいもの、つまり「ホンモノ」を探すことは難しいと感じていました。
幼い子どもでもこぼしにくい器(愛媛・砥部焼、徳島・大谷焼、石川・山中漆器)東京は日本の玄関口でありながら、日本のホンモノを探したとしても、観光客が行くような場所に並べられているものは「日本ぽい」お土産物がほとんどだと思います。なんとなく日本風のものをつくっておけば外国人の人たちが喜ぶだろう、という発想でつくられた観光地も多いように感じます。こうした場では、残念ながら、私が本当に外国人の人たちに贈りたいもの、つまり「ホンモノ」を探すことは難しいと感じていました。
そうしたなか、昨年、一昨年と私は国際交流基金のお仕事で、スペインを訪れる機会があったのですが、一度も日本に来たことがないのに流暢な日本語でしゃべる人がいらっしゃったり、日本文化の根底にある精神性まで学び取ろうと質問してくる人がいたりと、とても驚かされました。それに対して、日本から発信されている情報は表層的なものが多いように感じました。とくに外国人がよく訪れる玄関口や観光地において、ホンモノに触れる機会や場がないのは、とても残念なことだと思っています。
確かに、大量に生産された千円の扇子に比べて、手づくりの一万円の扇子はたくさんは売れないかもしれません。けれども、ホンモノを伝えようとしないかぎり、東京は文化都市にはなれないと思うのです。日本のものづくりが、「ぽい」もので語られるのは残念でなりません。これからは、一万円のものがなぜ一万円なのかを伝える方法を考えていかなければならない時代ではないでしょうか。一万円という数字だけを見ると高いと感じるかもしれませんが、一生モノだと考えると、けっして高くはありませんよね。
ものづくりもまちづくりも、自分が本当に子どもたちに贈りたい日本の物や、残したいもの、外国人の大切なお友だちに贈りたいものを、おもてなしの心をもってつくっていくことがとても大切だと感じています。皆が真剣に、日本の伝統と、現代の都市のいい部分を「和える」ことができれば、間違いなく素敵な空間が生まれるはずですし、日本は大きく変わっていくのではないかと思っています。
―大変示唆に富むお話をしていただきまして、ありがとうございました。いっそうのご活躍を心よりお祈りしています。

矢島里佳(やじま・りか)
株式会社 和える 代表取締役
1988年生まれ。大学時代にライターとして日本全国の職人の取材記事を執筆。大学3年生のときに企画したビジネスプランが、日刊工業新聞のキャンパスベンチャーグランプリで特別賞を受賞。ブラッシュアップした案が東京都主催の学生起業家選手権で優勝。優勝賞金150万円を資本金として、2011年3月に株式会社和えるを設立。全国の職人らとともにものづくりをしながら、子ども向けの商品を開発、販売をしている。
和える
おすすめ情報
-

【さんさん対談】殻を破って見えた、行政の役割と"人に向き合う力"
井上航太さん(宮崎県職員)×田口真司(3×3Lab Futureプロデューサー)
-
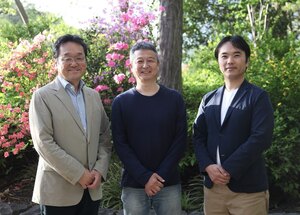
【さんさん対談】これまでも、これからも、自分らしく
佐藤岳利氏(株式会社 佐藤岳利事務所)×田口真司(エコッツェリア協会 3×3Lab Futureプロデューサー)×松井宏宇(エコッツェリア協会 シニアディレクター)
-

【レポート】大手町の4つのラボにサステナブルな社会変革に挑戦する企業が集結 大手町ラボフェス
大手町ラボフェス#3 食と農業とサステナブル 2025年8月26日(火)開催
-

【大丸有フォトアーカイブ】
第3回 みんなの写真展 2月4日(水)から開催「GOOD DESIGN MARUNOUCHI」にて14日(土)まで
注目のワード
人気記事MORE
- 1
 【丸の内プラチナ大学】2025年度開講のご案内~第10期生募集中!~
【丸の内プラチナ大学】2025年度開講のご案内~第10期生募集中!~ - 2
 【大丸有シゼンノコパン】色彩豊かな冬の鳥を「観る(みる)」 ~極寒の今こそ絶好の"鳥"日和!~【まちの生きもの】
【大丸有シゼンノコパン】色彩豊かな冬の鳥を「観る(みる)」 ~極寒の今こそ絶好の"鳥"日和!~【まちの生きもの】 - 3
 【大丸有シゼンノコパン】都心の緑地に春の目覚めを「覗る(みる)」~生きものとの共生のヒントを探して~【まちの生きもの/親子・初心者の大人向け】
【大丸有シゼンノコパン】都心の緑地に春の目覚めを「覗る(みる)」~生きものとの共生のヒントを探して~【まちの生きもの/親子・初心者の大人向け】 - 4
 大丸有でつながる・ネイチャープログラム大丸有シゼンノコパン 冬
大丸有でつながる・ネイチャープログラム大丸有シゼンノコパン 冬 - 5
 丸の内プラチナ大学2025 逆参勤交代コース特別講座 飛騨ナイト
丸の内プラチナ大学2025 逆参勤交代コース特別講座 飛騨ナイト - 6
 さんさんネットワーキング~2026春~
さんさんネットワーキング~2026春~ - 7
 3×3Lab Future個人会員~2025年度(新規・継続会員)募集のお知らせ~
3×3Lab Future個人会員~2025年度(新規・継続会員)募集のお知らせ~ - 8
 【レポート】共創がもたらす新たな価値創造 〜リビングラボが描く未来の地域経営~
【レポート】共創がもたらす新たな価値創造 〜リビングラボが描く未来の地域経営~ - 9
 【レポート】共感が未来を動かす 〜 クリエイティブが地域に灯す、新しい価値のつくり方
【レポート】共感が未来を動かす 〜 クリエイティブが地域に灯す、新しい価値のつくり方 - 10
 【レポート】マーケットイン思考がもたらす食農ビジネスの可能性
【レポート】マーケットイン思考がもたらす食農ビジネスの可能性

