

CSRイノベーションワーキンググループの第8回が、2月14日(木)に開催されました。昨年6月よりスタートした今年度のワーキンググループも、現在制作中の「エコのまど」完成お披露目会となる第9回を除くと、ワークショップとしては今回が最終回となります。
前半ではこれまで練り上げてきた"社食"イベントアイデアのプロトタイプとして、1月30日に実施したパソナグループ社食訪問についての情報をシェアしました。後半では、こういったアイデアのプロトタイプ実施などを含め、来年度以降このワーキンググループをどうすすめていくかを考えるワークショップを行いました。
まず、企画を担当した田口真司さんより、社食訪問の振り返りを共有。社食はもちろん、VIPルーム、屋上までと2時間にわたって社内中をくまなく見学させていただいた様子が紹介されました。
参加者からの声
 パソナさんのユニークな社食(左上)と社内の模様。至る所に植物があり、田口さんいわく「畑のなかにオフィスがあるという感じ」。
パソナさんのユニークな社食(左上)と社内の模様。至る所に植物があり、田口さんいわく「畑のなかにオフィスがあるという感じ」。
実際に訪問に参加した参加者からは、
「会社に入った瞬間、ここは会社じゃないなと驚いた。楽しく仕事をする、会社が社員に貢献できることはなにかを考えているという、会社のコンセプトがあるからこそ、キラキラしてるんだなと」
「優秀な人を会社にひきとめておきたい、会社が魅力的じゃなかったら会社自体の存続が危ないという危機感。その目の付け所がすすんでいるなと思いました。また、若い人の意見を具現化する仕組み、障がい者、芸術家が活躍できる仕組みはすごいなと感じました」
「ビルの前をよく通るので入ってみたかったのですが、野菜を社内で育てている会社を見たのは初めて。社員にとって楽しい会社というのはうらやましい。こういう会社が増えると、良い社会ができるのでは?!」
「Googleなど西海岸の会社の取り組みは有名ですが、社員と会社の良い循環。パソナさんの場合、その見えるカタチとして社食があるんだなと思いました」
などなど、社食のすばらしさはもとより、社食を具現化させた会社、その背景にあるものを考えさせられたという意見が多数出されました。
同行したファシリテーターの櫻井亮さん(NTTデータ経営研究所)も、
「クローズアップされる社食というと、外食チェーンをいれて、お金をかけてというものが多いが、パソナさんの場合は違う。ハードの面では、三菱地所の協力もあって取り壊す予定のビルを借り、例えば低い天井を取り払って高くするなど、ドラスティックにやりたいようにやっている。ソフト面では、会社の成り立ちとして人材派遣業が違法なのか違法じゃないかというところからチャレンジしてきたという経緯もあって、社内に創意工夫のティップスがたくさんある。そのパソナさんのノウハウの蓄積のなかから生み出されてきたもの、有機体として生きていると感じました」
とコメント。
「良いところしか目に入らない、隣の芝は青いということもあるかもしれませんが、すれ違う社員の方々が活き活きしていて楽しそうという一言に尽きる。ツアー実施後のアンケートには転職したいなんてコメントもありました(笑)。実際に他社に行き、見て、成り立ちを聞いたからこそ、座学では得られない、新たな発見があったのではないでしょうか」
と田口さんが締めくくり、前半を終了しました。
CSR/CSV活動に他社訪問をどう活かす?
続いての後半は、ワールドカフェ形式に。「パソナグループ社食訪問の話をきいてどう感じましたか?」「社食をはじめとするコミュニティスペースの役割は何でしょうか?」「これからのCSR/CSV活動に向けて、他社訪問をどう活かしていきますか?」との3つの問いを、グループのメンバーを入れ替えながら、話し合いました。

グループでのディスカッションを終えて、全体で結果と感想を共有しました。
「コミュニティスペースに欠かせないのは、場所、そして人。社食はともかくとして、喫煙スペースのコミュニティは強いですよね」
「たばこは公然と休憩としてみとめられているが、さぼっていると見られることにすごい抵抗感がある。公私混ざった"何か"の目的のある場所を作れないか。社食も、食べる、リラックスする以外のフックが設計できると面白い」
「箱として場所を設置するだけでは限界があるが、カフェで仕事をするように、場所や雰囲気を変えることで効率があがることもある。他社を訪問してわかったことなどから成功事例を紹介していけば、そういった環境づくりに社内の理解も得られるのかなと」
最後に、プロデューサーの鈴木菜央さんより、"光りが見えた!"という明るい発言が飛び出しました。
「大成建設さんが工事現場に設置している自販機は、購入するとボルネオの植林活動に10円寄付される仕組みがあるそう。自社では当たり前と思っているものが、他社からみると『おおっ!』と驚くこともある。実際に他社訪問などで見に行って、『我が社でも、このアイデア取り入れよう』という具合に、広がって行ったり、共同でプロジェクトを始めるとなれば、社会的にもインパクトがあるんじゃないか。みんなそうだが、自分では自分の良いところや可能性に気付かず、アウトプットが下手な部分というのはあると思うので、このワーキンググループが、他社やNPOや役所などに皆で出かけて行って、働きかけていくそういう場所になっていくと面白いのでは?!」
来年度以降のCSRイノベーションワーキンググループ、進化の予感大ですね!今後のこのワーキンググループの動きが楽しみです。
今回の参加企業
関連記事
- 【CSRイノベーションWG:番外編】オフィスビル内で地産地消も実現!"社食"アイデア実現のため、ユニークすぎるパソナグループの「アーバンファーム」を見学に行ってきました。
- 【CSRイノベーションWG】頭ではなく手で考える!? 第7回ワークショップでは「デザイン・シンキング」を体感。
- 【CSRイノベーションWG】意外性があって感情に訴えるCSRポスターづくりに挑戦。第6回は「エコのまど」制作ワークショップ
- 【CSRイノベーションWG】第5回を迎えいよいよ後半戦へ。"社食"イベントアイデアが実現に向けて動き出した!
- 【CSRイノベーションWG】「電車ごっこ」に「宝探し」に「ミ社食ラン」!?「丸の内でCSRを象徴するイベントをするなら?」アイデアを実現に向けてブラッシュアップ−第4回ワークショップ
- 【CSRイノベーションWG】第3回のゲストは鎌倉投信新井和宏氏!"いい会社ってなんだろう? いい社会ってなんだろう?"+"丸の内でイベントをするなら?"アイデア創出ワークショップ
- 【CSRイノベーションWG】みんなの未来への想い、絵巻物にしたら見えてきた!グラフィックファシリテーションでCSRのビジョンを可視化する、第2回ワークショップレポート
- 【CSRイノベーションWG】協創的、創発的CSRを実践する「環境コミュニケーションワーキンググループ」第1回に密着!
2011年度の環境コミュニケーションWG
- 「未来のCSR」とは何か?昼間っからサラリーマンが粘土をこねる環境コミュニケーション・ワーキンググループ
- 実践講座4.「共通価値の創造」CSV 水上武彦氏
- 実践講座1.「各社CSRの相互評価とディスカッション」
- 新時代のCSRを学ぶ 「日本財団CANPANプロジェクト」高島友和氏
- 新時代のCSRを学ぶ 「LIGHT UP NIPPON」高田佳岳氏
- 新時代のCSRを学ぶ 「ガリバータッグプロジェクト」北島昇氏
- これからの企業のCSRはどうなる?を話しあう「環境コミュニケーションワーキンググループ」に密着!
2010年度の環境コミュニケーションWG
CSV経営サロン
2011年からサロン形式でビジネスに関する様々なプログラムを提供。発足当初から小林光氏に座長を、2017年からは吉高まり氏に副座長をお願いし現在に至っています。
2015年度からは「CSV経営サロン」と題し、さまざまな分野からCSV経営に関する最新トレンドや取り組みを学び、 コミュニケーションの創出とネットワーク構築を促す場として取り組んでいます。
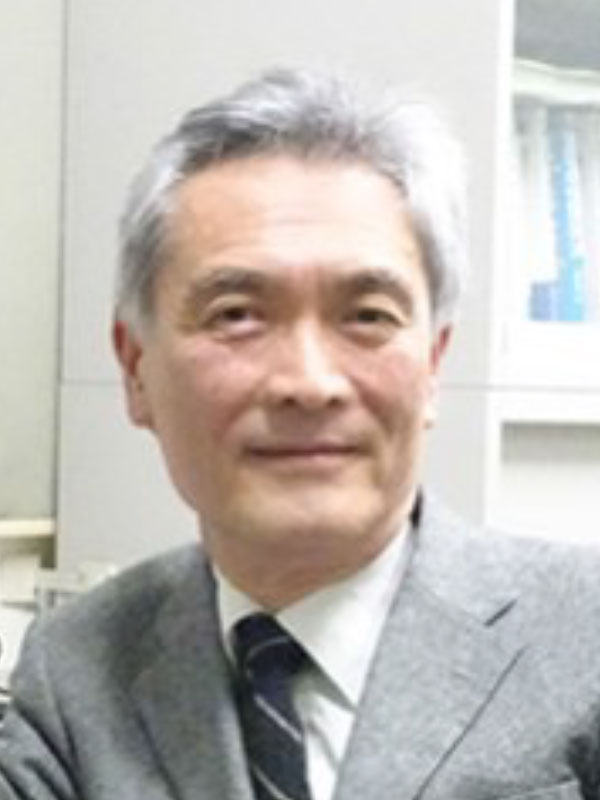
座長:小林光 氏
東京大学先端科学技術研究センター研究顧問 /
教養学部客員教授
慶應義塾大学経済学部卒(1973年)、東京大学大学院工学系研究科都市工学専攻修士、博士(2010・2013年、共に工学)。
1973年環境省(当時環境庁)入省。京都議定書交渉の担当課長、環境管理局長、地球環境局長、官房長、総合環境政策局長、2009年から2011年まで次官を務め退官。
慶應大学教授、米国イリノイ州にて派遣教授、2016年から現在まで東京大学客員教授。その他日本経済研究センター特任研究員、国立水俣病研究センター客員研究員、地方の環境審議会委員や脱炭素対策検討の委員等を歴任。
再生可能エネルギーを主要なエネルギー源とする資源循環型の社会を構築するために必要な価値観の転換、諸制度の整備などに取り組む。

副座長:吉高まり 氏
一般社団法人バーチュデザイン代表理事 /
東京大学客員教授/
慶慶應義塾大学総合政策学部特別招聘教授
明治大学法学部卒、米国ミシガン大学環境サステナビリティ大学院科学修士、慶應義塾大学大学院政策・メディア科博士(学術)。
IT企業、米国投資銀行等での勤務を経て2000年より現三菱UFJモルガン・スタンレー証券において気候変動関連の資金枠組みづくり、カーボンクレジット組成などに関与。政府、地方自治体、金融機関、事業会社などに向けて気候変動、GX、サステナブルファイナンスの領域について講演、アドバイスなどを提供し、新たにサステナビリティ経済の推進の実装を図る。
おすすめ情報
-

【レポート】SMBCと東近江市の事例から学ぶ、国内で進むネイチャーポジティブ✕金融の動向
CSV経営サロン2024年度第3回2024年11月25日(月)開催
-

【レポート】日本のネイチャーポジティブ×水をリードするサントリーグループの理念とは
CSV経営サロン 2024年度 第2回 2024年9月17日(火)開催
-

【丸の内プラチナ大学】開講のご案内~第6期生募集中!~
2021年9月−3月
-

【さんさん対談】地方創生は「犬」から始める。産官学連携で描く「ドッグ・スマートシティ」構想とは
大賀暁氏(昭和女子大 現代ビジネス研究所 研究員、橿原市職員)×田口真司(3×3Lab Futureプロデューサー)
イベント
注目のワード
人気記事MORE
- 1
 【丸の内プラチナ大学】2024年度開講のご案内~第9期生募集中!~
【丸の内プラチナ大学】2024年度開講のご案内~第9期生募集中!~ - 2
 【大丸有シゼンノコパン】大手町から宇宙を「望る(みる)」ービルの隙間からみる、星空の先ー
【大丸有シゼンノコパン】大手町から宇宙を「望る(みる)」ービルの隙間からみる、星空の先ー - 3
 大丸有でつながる・ネイチャープログラム大丸有シゼンノコパン 冬
大丸有でつながる・ネイチャープログラム大丸有シゼンノコパン 冬 - 4
 【丸の内プラチナ大学】逆参勤交代コース 壱岐市フィールドワーク
【丸の内プラチナ大学】逆参勤交代コース 壱岐市フィールドワーク - 5
 【大丸有シゼンノコパン】【朝活】大丸有で芽吹きを「視る(みる)」ー春の兆しは枝先からー/まちの四季
【大丸有シゼンノコパン】【朝活】大丸有で芽吹きを「視る(みる)」ー春の兆しは枝先からー/まちの四季 - 6
 3×3Lab Future個人会員~2024年度(新規・継続会員)募集のお知らせ~
3×3Lab Future個人会員~2024年度(新規・継続会員)募集のお知らせ~ - 7
 【レポート】遊休資源が輝く未来へ 〜山形に学ぶ持続可能な地域づくりの挑戦〜
【レポート】遊休資源が輝く未来へ 〜山形に学ぶ持続可能な地域づくりの挑戦〜 - 8
 フェアウッド×家具~ものづくりを通じた自然や生態系への貢献~
フェアウッド×家具~ものづくりを通じた自然や生態系への貢献~ - 9
 指導経験ゼロから日本一のチームを作った「日本一オーラのない監督」が語る存在感と自己肯定感
指導経験ゼロから日本一のチームを作った「日本一オーラのない監督」が語る存在感と自己肯定感 - 10
 【大丸有フォトアーカイブ】第2回 みんなの写真展 2月21日~3月4日
【大丸有フォトアーカイブ】第2回 みんなの写真展 2月21日~3月4日

